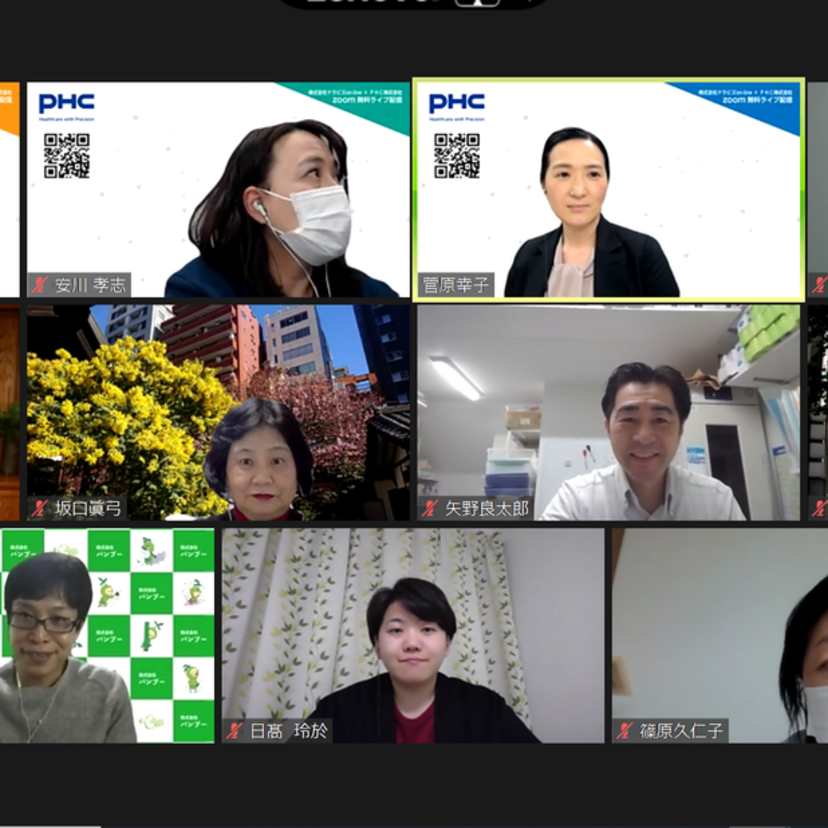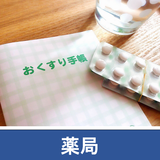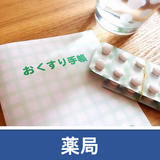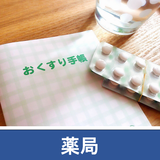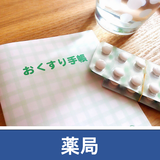「医療提供施設になったら報酬が付くのか?」という視点
まず印象的だったのは、講演の中で、平成の約30年の間に法的にどのように薬剤師、あるいは薬局が位置付けられてきたのか、説明されたことです。
1992年の第二次医療法改正(薬剤師が医療の担い手として明記)、2004年の薬学教育6年制に関する法律(学校教育法や薬剤師法)、2006年の第五次医療法改正(薬局を医療提供施設として位置づけ)などなどです。
冒頭、ここまでを聞いて、少し頭が冷静になりました。
法律に薬局や薬剤師をどう位置付けるのかということは、時代や社会の要請を法律の中にも反映させていくということだと理解できたのです。
それを「どう報酬に結びつくのか?」と拙速に考えるのは少し違うのではないかと感じました。
「医療提供施設にしたのだから、調剤報酬が高くなるのですよね?」とは誰も聞かないと思います。
地域連携薬局は「地域のリーダー薬局」
一方で、「医療提供施設は薬局全体がなったのだから…(認定薬局とは違う)」という視点もあると思います。
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局が、一部の薬局を認定することには、どういう意味があるのか。
ここには“目星”という意味があると思います。
今後、医療政策、例えば地域包括ケアや在宅医療に向けた政策を打っていくに当たって、行政にとって、このぐらいの数、このぐらいのことができる薬局があるよという“目星”がつけられることにつながると思います。
ここには、調剤報酬はダイレクトには付かなくても、これまでも医療政策上の様々な場面で法律での位置づけが影響を及ぼしてきたメリットに近いものが出てくると思います。当たり前と言えば当たり前ですが、新型コロナワクチンの優先接種に薬剤師が入っているのも、法律的に医療の担い手としっかり定義されてきたことと無関係ではないと思います。
もう一つ、セミナーを通して妙に納得したことがあります。
セミナー前には「なぜ、このように薬局の手間をかけさせることばかりを行政はするのか」と思っていたのです。
その点に関して、セミナーを通して感じたのは、「どうやら行政は中学校区に1つ、地域包括ケア構築、特に在宅医療体制構築を牽引できるような薬局を育成しようとしているのではないか」ということです。無菌調剤体制を条件に含めているあたりは、在宅が強く意識されていることを感じます。ですから、地域連携薬局の数に関して、「中学校区に1以上」としているわけです。その薬局は、他の薬局にも気を配れる薬局であってほしいわけです。
つまり、「手間をかけられる」ということは、「一定の余力がある」ということでもあり、地域の事情を鑑み、他の薬局のリーダー的な存在にもなれることを意味するのかもしれないと思ったのです。
健康サポート薬局と同じ轍は踏めない
とは言え、認定を申請する薬局の中には、「余裕があるから申請するわけではなく、負担を抱えて必死でやっている」という薬局があることも事実だと思います。
ですから、「認定を取ったのに、社会から何の評価もないのはおかしい」と考えるのも、人の道理ではないかと思います。
健康サポート薬局を理念では理解していても、申請までいかない薬局が多く、健康サポート薬局が2200軒程度から増えていかない理由の一つだと思います。
このことに関しては、行政も課題意識は当然、持っていると思います。
ですから、今回のセミナーだけでなく、行政から発せられているメッセージでは、調剤報酬とリンクさせることを真っ向から否定するものではなくなっています。
行政としては、せっかくつくった認定薬局は、当然普及させていく必要があるため、今後、「どのようにインセンティブを設定するか」は検討が進むのではないかと考えています。
ただし、その方策を考えるのは、行政だけでなく、薬局自身が、現場の活動の中からアイデアを出す必要があると思います。
蛇足ですが、今回、認定薬局の基準に関して薬局関係者から異論も出ています。
完璧な基準はないですから、決まった基準に異論が出るのはある程度仕方がありませんが、薬局業界が考えるべきは、「より良い制度設計にどのように関わっていくか」ではないかと感じています。「一部の人が決めている」という批判もあります。では、どうしたらその仕組みを少しでも改善していく手法があるのか。過去の経緯にとらわれず、新しい手法の検討があってもいいのではないでしょうか?
地域連携薬局になるのは大手調剤か? ドラッグストアか?
薬局が業態ごとに細分化してきていることは、誰もが承知していると思います。
こうした中で、はてさて、地域連携薬局とは大手調剤チェーンを指すのでしょうか、O T C薬も販売している調剤併設ドラッグストアを指すのでしょうか、はたまた地域に根ざした個人経営の薬局を指すのでしょうか?
このどれでもないのではないかと思います。
個人経営の薬局であっても、一定の余力がなければ、条件には当てはまらないでしょう。
勢いのある調剤併設ドラッグストアであっても、月に30回のように医療機関との情報連携が密にできていなければ条件には当てはまらないでしょう。
規模の大きな大手調剤チェーンであっても、地域の他の薬局を支える視点がなければ、条件には当てはまらないでしょう。
細分化する薬局業界にあって、地域医療にとって必要な条件で“横串”を刺して目星を付けたのが、まさに「地域連携薬局」ではないでしょうか。
その枠組みに、どんな業態が入ってくるのか。
それは、個々の取り組み次第でしょう。
少なくとも、今後の在宅医療体制の基礎情報となる地域連携薬局の申請なくして、在宅医療における薬局活用の話は進まないのではないかと思います。
最後に、健康サポート薬局と地域連携薬局の違いは何かという議論もありますが、地域連携薬局は在宅医療のリーダー、健康サポート薬局は予防のリーダーだと感じています。
ですので、“インセンティブ”に関していうと、健康サポート薬局の方が、より、行政として調剤報酬などには付けづらい対象だと思います。しかし、現在、調剤報酬だけではなく、保険者の保健事業など、“出所”は多面化していっていますので、健康サポート薬局のインセンティブについても多角的な検討が進むでしょうし、進めるべきだと感じています。

【地域連携薬局要件】「月30回以上の医療機関の連絡」に疑義照会は含まれず
https://www.dgs-on-line.com/articles/698【2021.01.30配信】厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は、地域連携薬局の要件に関する通知を発出した。地域連携薬局の要件である「月30回以上の医療機関の連絡」に疑義照会は含まれないなどとしている。

【地域連携薬局の要件Q&A】「医療機関への連絡実績」例は「服薬情報等 提供料」や「服用薬剤調整支援料」
https://www.dgs-on-line.com/articles/699【2021.01.30配信】1月29日、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」を発出した。「医療機関への連絡実績」の要件に関しては、例として「服薬情報等 提供料1」、「服薬情報等提供料2」「退院時共同指導料」「服用薬剤調整支援料1」、「服用薬剤調整支援料2」、「吸入薬指導加算」、「調剤後薬剤管理指導加算」を挙げた。また、調剤報酬の算定の有無にかかわらず、情報共有を実施していれば実績とする。