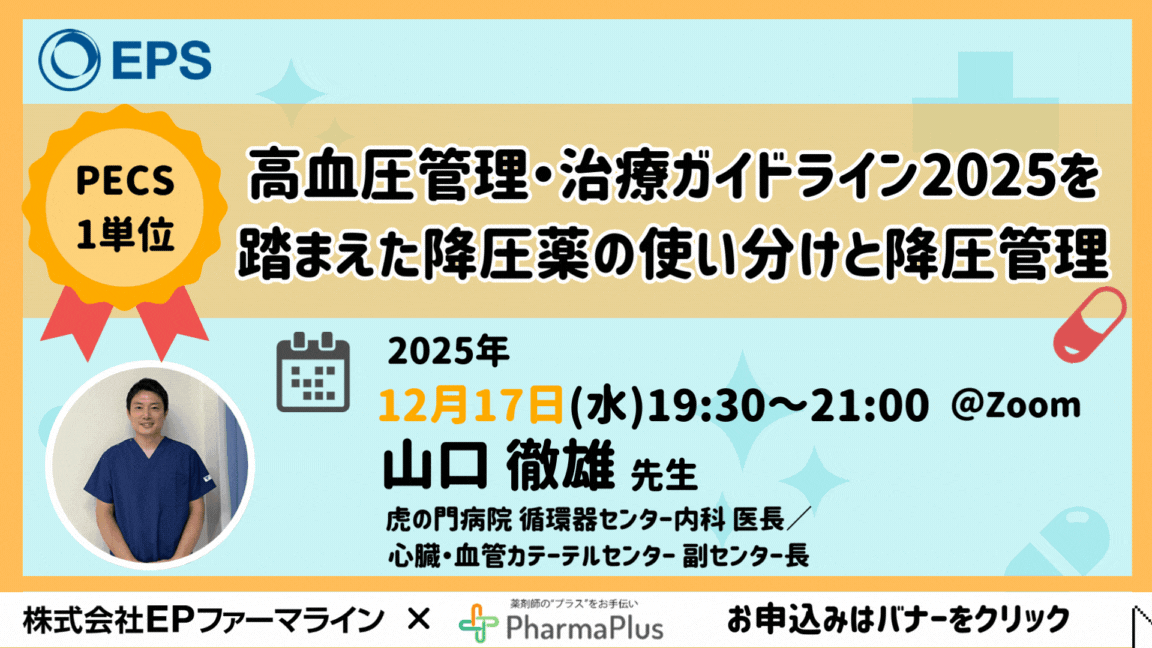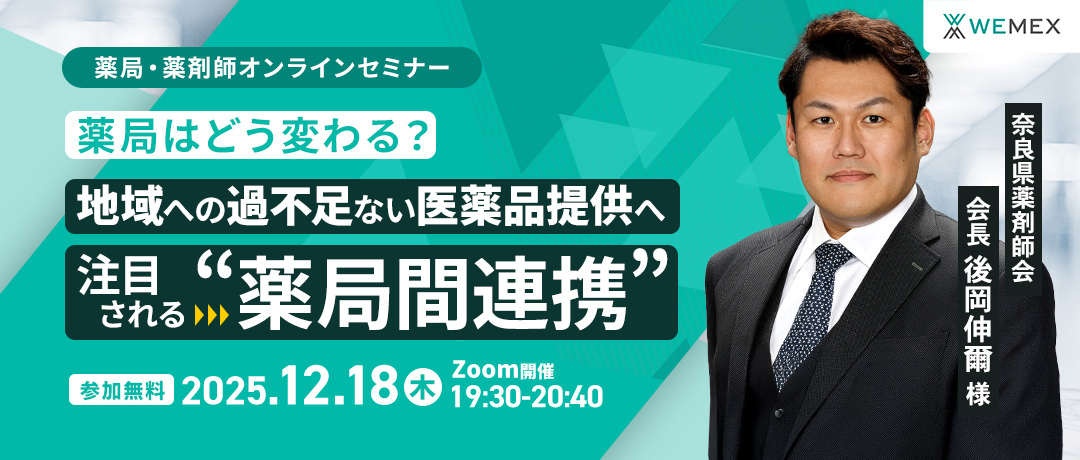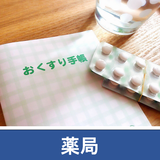<座談会出席者>
田畑裕明氏 自民党衆議院議員 富山一区(5期)<写真右>
勝目康氏 自民党衆議院議員 京都一区(2期)<写真左>
本田あきこ氏 自民党参議院議員 比例代表全国区 (1期)<写真中央>
現在はフリーハンドの立場、問題意識を当局や政府、同僚と共有する“接着剤”の仕事する/田畑裕明議員
--まずは、それぞれのプロフィールといいますか、最近のご活動を含めてお願いします。
田畑 今、13年目の議員活動させていただいておりますが、約10年間は厚生労働委員会に所属をしてまいりました。この間、厚生労働大臣政務官ですとか、党の厚生労働部会部会長、衆議院の厚生労働委員会の委員長、また国会対策委員長の副委員長として厚生労働委員会を担当してまいりました。表の舞台と、また舞台回しの方も、いろいろな皆さんのご指導いただいて経験をさせていただいたわけであります。
私の地元は製薬産業が大変盛んな富山ということでありまして、300年を有する歴史があって、地元の経済の基幹産業ということになります。製造拠点も多いわけでありますが、創薬ですとか、薬業人材、薬剤師の方々を含めて、非常にご縁のある方がたくさんいらっしゃいます。やはり、そうして働いている方々、また人の命を守り助ける医薬品というものをこれからもしっかり開発し、届ける、できれば富山発の創薬を含めて、ご支援を頑張りたい、国益にかなう仕事をしたいと思って、この仕事を自ら望み活動しています。
--今、たまたま田畑議員が政府側ではないタイミングということで、意見発信に皆さんが注目されているところかと思います。
田畑 たしかに、現在はフリーハンドの立場でありますので、今日の発言も全く一個人としての発言でありますし、問題意識をやはり当局や政府、また同僚の皆さんと共有するため、いろんな意味で接着剤みたいな仕事ができたらというふうに思っています。当然、立法府において法律を作ること、法案に対して質疑するというのは大変重いことです。いろんな国民の声を代弁をするということでありますので、非常に久方として質問に立てる今のポジションはある意味、新鮮であります。
--今国会の質疑でも引きこもり対策について熱弁をふるわれていたのが印象的でした。
田畑 そうですね。この分野は経済困窮や医療的な対応の問題もあり、どこに相談をするか、明確な所管がないという側面もあります。苦しい思いをしているけれど、それが外に発することができないまま時間が経過したり、親亡き後の問題も顕在化しつつあります。自治体と国政をしっかりつないでいかなければいけないという危機感をもとに取り組んでいます。病気ではなく状態ですので、その状態をときほぐしたり、その方に適した居場所、そして活躍の場などいろんな選択肢をもっと整えていく必要があると思っています。

田畑裕明氏
自民党衆議院議員 富山一区(5期)
昭和48年生まれ、52歳。獨協大学経済学部卒業後、富山第一銀行入社。富山鋼機勤務などを経て、平成15年富山市議会議員選挙において初当選。富山市議会議員3期を経て、平成23年富山県議会議員選挙で初当選。平成24年衆議院議員選挙にて初当選。政府では厚生労働大臣政務官や総務副大臣を務めたほか、国会では厚生労働委員長を務めた。党内では、厚生労働部会部会長、国会対策委員会副委員長などを歴任。現在は自民党厚生労働部会薬事に関する小委員会委員長。議員連盟ではひきこもり支援推進議員連盟事務局長も務める
高齢化の中で平穏に暮らせて、それぞれの持ち場で活躍できる、その前提条件を作ることは政治そのもの/勝目康議員
--勝目議員、お願いします。
勝目 私はもともと総務省、省庁再編前の自治省で四半世紀仕事をしてきました。前々回の総選挙で初めて衆議院議員としての立場をいただきました。私は当選してから、いわゆる部会や委員会で総務関連に入ろうというのは全く思わなかったのです。厚生労働、そして文部科学を中心に活動してきました。個人的な話なんですけれども、私の家業は医者でして、父、祖父、曽祖父、叔父、大叔父、妹、その夫、みんな医者なんです。私自身は長男家の長男が医者を継がなくて文系に行ってしまったんです。けれども政治に場をいただいて、医療政策の面から医療、社会保障に貢献したいと思っています。
じゃあ、なぜ医療、社会保障かというと、別に家族がそうだからということを越えて、やはり今の日本社会において、経済的に発展をしていくにも大前提として社会が安定していないといけない。高齢化が進んでいく中でいかに社会の一体性を保って平穏に暮らせて、それぞれの持ち場で活躍できる、その前提条件を作ることができるかというのは、これはもう政治そのものであるし、公共政策としてしっかり取り組んでいかないといけない。2040年に向けて本当に日本の社会がこれから胸突き八丁を迎える。そういう分野だという思いが非常に強く、社会保障について取り組んでいきたいと考えました。
実際に厚労分野に携わることによって、ちょうどこども家庭庁をつくるタイミングで、こども基本法は議員立法だったんですけれども、提案者にならないかということで、議員になって最初の通常国会でそういう経験をさせていただきました。そこから一気に、関わっていく分野が単に医療だけではなくて、社会保障全体にぐっとひらいていった、そんな気がしています。
薬剤師さんに関しては印象深い思い出があります。当時、まだコロナ禍の真只中で、そんな中である薬剤師の先生のところにお伺いした時に、ラゲブリオの実物を見せていただいたんです。とても大きな錠剤でお年寄りがそのまま服用できるしろものではない。実際に防護服を着て、服薬指導に行って、ちゃんと飲んでいただけるまで見守っているとのことでした。そんな経験があり、当然、医療というのはチームでやるべきものでありますけれども、コロナ禍という国家的な危機の中で、それぞれの役割というものを果たしていかないといけないという実感が強まりました。薬剤師の先生が現にそういう形で仕事をされていて、それで命が救われる、さらに言うと救われるのだという安心感をみなさんに持っていただける、そういう仕事ぶりを具体的な形で見せてもらったことが私の中に記憶として強くあります。現在私は環境省の政務官であり、政府側の人間ではありますが、許される範囲において党の会議でも意見を申し述べています。
--勝目議員は伊吹文明議員の後継というイメージが強くあります。ご自身では、なぜご自分が後継指名されたとお感じですか。
勝目 なぜ私だったのか、それは分からないんですけれども、伊吹先生が地元の地方議員さんにおっしゃっていた言葉としては、「やっぱり京都から一人は霞ヶ関を道案内なく歩くことのできる人間が必要だ」という言い方をされていました。私は幸い、総務省だけではなく大使館であるとか、首相官邸、地方公共団体とか、横串で行政を見る仕事をたくさんさせていただいたこともあって、そういうところは一つあったのかなと思います。けれども私が政策面で伊吹先生から何か教えを受けたりとか、逆にこちらから伺ったりというのは一切ないんです。伊吹先生がおっしゃったのは、「とにかく政治家として独り立ちするための基盤を自分の力でつくれ」ということです。「政策というのはもちろん大事なんだけれども、紙の上で作るだけではなく実行力を持たなければいけない。その実行力を持つためには政治的な基盤が備わってないといけない。まず最初はそこを作ることに力を注がなければいけない。政調に出て政策を作った気になってたらあかんぞ」という話をされました。
--先生の選挙区の京都といいますと、今年の日本薬剤師会学術大会の開催地でもありますね。
勝目 京都府薬剤師会の河上英治会長とは、医薬品の問題を議論する中で、薬剤師さんからお声を聞くなど、コミュニケーションを取らせていただいています。当選後まもなくから薬剤師問題議員懇談会にも入らせていただいています。

勝目康氏
自民党衆議院議員 京都一区(2期)
昭和49年生まれ、51歳。東大法学部卒業後、総務省入省、自治財政局・消防庁理事官を務める。在フランス日本国大使館一等書記官、総理官邸 内閣官房副長官秘書官、京都府府民生活部長・総務部長、総務省地域振興室長を歴任。
令和3年第49回衆議院議員総選挙初当選。令和6年 第50回衆議院議員総選挙再選。 現在、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官。
薬剤師の役割・任務、教育も災害支援も「法の下にある」ことを実感/本田あきこ議員
--本田議員、お願いします。
本田 私は2019年に初当選し、その時に「あい・きぼう・これからの医療と薬剤師」という政治信条を掲げ出馬しました。出馬に至った経緯といいますのは、私自身が薬剤師として仕事をしている中で法の下で役割を担っているということを痛切に感じることが節々であったことです。平成16年の薬剤師法改正と学校教育法の改正によって薬学教育は4年制から6年制に変わりました。教育も実は法の下にあることを実感しました。
そして、熊本地震です。災害を経験し、命を守るのは政策だということを痛感しました。現場の声をしっかり政策に届けたいと思い国政を目指し、今、1期目として仕事をいたしております。
--熊本地震の支援では、本田議員が現地で誰よりも早く起床し活動されていたというエピソードをお聞きしたことがあります。昨年12月の国会質疑でも石破首相に中間年改定の見直しの必要性を訴えられていたのも印象的でした。現在は自民党女性局長として、ネットワークも広がっていると思います。ちなみに、女性局長指名の背景をうかがってもよいですか。
本田 女性局長は新人議員の登竜門とも言われています。前任で元・北海道知事であり同期でもある高橋はるみさんの推薦に基づいて参議院自民党幹部から打診がありました。女性局は青年局のように年齢制限がないので幅広い年齢層と、自ら政治に関わりたいという志のある党員の方もいたり、政策提言や地域貢献、女性の健康支援についてなど、多彩なテーマを議論しています。

本田あきこ氏
自民党参議院議員 比例代表全国区 (1期)
昭和46年生まれ、53歳。星薬科大学卒業後、医薬品卸や保険薬局勤務を経て、平成14年参議院議員公設秘書。平成28年熊本県薬剤師会勤務。平成29年日本薬剤師連盟副会長、熊本県薬剤師連盟 副会長、日本薬剤師会災害対策委員会委員。
令和元年第25回参議院議員選挙で初当選。政府では厚生労働政務官兼内閣府大臣政務官、文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた。党内では厚生労働部会副部会長を務めたほか、現在、女性局長。参議院文教科学委員会の与党筆頭理事。
中間年改定への疑義、党内で議論も国民から見えづらいことは課題/本田あきこ議員
--本日の座談会テーマである社会保障に関連し、本田議員は「医療・介護・福祉の現場を守る緊急要望」を発起した有志議員のお一人ですね。4月18日には関係団体や自民党国会議員が700名超集まった「医療・介護・福祉の現場を守る緊急集会」も開催されたほか、代表者が石破茂首相にも申し入れをしました。
本田 緊急集会においては300余名分の衆参国会議員の署名を集めました。医療、介護、福祉の現場を守るということにご賛同いただく衆参国会議員の先生方の署名活動を行ったわけですが、それに至った原因というのは、医療、介護、福祉というのは公定価格の下にあり、物価や人件費の高騰を価格に転嫁できないという状況にあることです。
令和6年度の報酬改定では賃上げ対応がなされましたが、それが現場では実感として届いておらず、かつ十分ではないという状況があります。人材が他業種へ流出し始めていることも問題です。2025年に団塊の世代の方たちが75歳以上を迎える中で、しっかりと支えていくという社会保障本来の仕組みを継続するためには、それらを担う職種の方たちがそこにいなければならない。働く方たちの手厚い支援がなければ充実した社会保障にならないですから、物価対策と賃上げ対応を訴えていかなければなりません。
物価高騰の影響がこれほどあるということは行政も政治も想定がなかったものだと思います。決議文の中でも「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安対応について見直す時期ではないかということも提起させていただきました。単に団体の声ということではなくて、今、医療・介護・福祉の職場に勤務している方は6人に1人いらっしゃいます。現役世代の手取りを増やすというような政策が野党でもありますけれども、そういったところに勤めている方も現役世代であるわけです。ですから署名活動は自民党が地域で暮らす人、支える人、両方守るんだということを訴えていることの表れでもあります。
--今後の見通しについてはどのように考えていますか。
本田 これだけの大きな声と署名を集めたので、ぜひ実現していきたいと思っています。
今の状況には不甲斐ない思いがあります。例えば薬価の中間年改定については、導入当初からわれわれ自民党の中には田畑先生をはじめ、問題意識を表明し強く意見を交わしてきました。しかし、それが実現できない中で、今回の予算に賛成していただくために3党合意がなされました。3党合意に掲げられていた政策は実現に近くなるのか、非現実的な内容も含まれている中にあって、今回の衆参の有志で集めた声をなんとか届け、実現に結びつけていきたいという強い思いがあります。野党は国会の委員会質疑という形で見解を示されますが、与党は党内での議論が中心になり、そのプロセスは見えづらいのかなと思います。しかし、自民党は総合力で対応していくということを発信していきたいと思います。
過去20年間と経済情勢が非常に変わってきていることを実態の数字や論理で説明/田畑裕明議員
--田畑議員は「緊急集会」では司会をされていましたが、いかがですか。
田畑 基本的に私は当事者ですから、傍観していません。やはりインフレ局面に入ってくる中で、過去20年間と経済情勢が非常に変わってきている。その中で今回の骨太方針や予算編成に入っていきます。しかも少数与党ということですから、非常に難しい方程式の中ですが、我々は働いている方々や国民に向けた政策づくり、また予算措置をしっかりやっていくということがまず大前提だと思っています。
しかしながらこれからの道のりは険しく、そしてどこかで妥協とか安心をしたら、目指す絵にならないという、とても強い危機感を持っています。具体的には財務省も財政審がスタートしたところで、本丸は安全保障、防衛関係と社会保障ということになるわけです。財務省は過去においては物価や経済情勢はデフレで停滞していたが医療費の給付はずっと伸ばしてきたというようなことを言っていますし、令和6年度・7年度について定昇分も含めると4%、3.5%はしっかり対応しているということなんですね。財政当局はその他の支援措置、補正も含めて対応しているので十分とは言わないまでもその中でやっていただきたいし、なおかつそれぞれの努力も含めて医療費の収入増というのもあるのではないかといったことを言っているわけで、それは相当ギャップがある話であります。
“目安対応”の問題でいえば、骨太方針2024では令和7・8・9年の3カ年がまた1つの期間として定められていて、歳出抑制の努力をしっかりやっていくということは政府文書です。この合意も含めて見直しをするということを我々は目指すわけですから、それに対応する論理的な流れ、そしてまた実態の数字、そうしたことをしっかり加味しながら社会情勢が変わっているよということ、これをまずどう説明をしていって財政当局や、国会議員の中でも財政再建を中心とした考えの方々も当然いらっしゃるわけですから、そうした方々の理解をどう得るのかということについて、相当汗をかいていかなければいけない。
また、社会保障費全体はブラックボックス化している面があります。消費税財源についても、見る側によって解釈が異なり、政治判断で物事が決められてきている部分が実はあります。そうした解釈も含めて全面的に見直しをするということに対抗するためには骨太方針も大事ですし、それ以降のいろんな議論について積み上げていく必要があるし、大きな声を束ねていく、当然1つは参議院選挙の結果というのも大変大事であります。我々も賛同していただく、またご支援をいただくこうした声をしっかり束ねるということも、両方が大事ということをまずお伝えしたいと思います。
--財政当局との折衝というのは、ある程度、見てきた景色ではありますが、今回、有権者の方にどう自民党の皆さんの考えを伝えていかれるのかが重要になっている面もあるかと思います。
田畑 われわれは国民政党ですから、もちろん社会保障分野で我々の考え方をしっかりお伝えすることも大事ですし、国家像ですとか、外交方針含めて、やはり懐の深い政党であるということをしっかり打ち出していかなければいけないというふうに思っています。
シンプルに言うと、勤労者の方の手取りを増やすというワードがありますよね。それは当然響くんだというふうに思いますが、その手取りを増やすために、減税ですとか給付ですとか、所得水準の税を変えるとかということについては、我々はやはり勤労することによってその評価を得てそして所得が上がる、賃金が上がるという姿を目指しています。それが本来、国の力を全体的に底上げしていく、伸ばしていくということなんだと思うんです。ただし、われわれがすべて正しくて国民の皆さんに理解をしていただきたいということではなく、当然、相手に届くような説明、政治家の力量が問われる部分であろうと思います。
一部を切り取った議論、全体を見なければ実は前提が崩れるおそれも/勝目康議員
--勝目議員は社会保障の問題をどのように見ていますか。
勝目 社会保障に関しては、おおざっぱな表現をすれば、社会保険料の負担の重さという入口の問題と、医療に従事される方々の人件費を含めた医療費という出口があり、入口をふさがれた状態で出口をどうするかという議論に陥りがちだと思います。ただ、そこでの国民負担は実は国民負担全体から見るとごく一部なんだということです。どういうことかというと、この間、先行して薬価の引き下げというのが加速度的に進んできました。薬価の中間年改定はその最たるものです。その結果、どうなっているかというと、ドラッグラグ・ロス問題であり、安定供給が損なわれている。必要な薬が手に入らないという状況に陥っているわけです。もちろん、その原因を薬価だけに問うのはどうかという議論はありますけれども、薬価がそこに大きく影響していることは間違いないと思うんです。
ということは、お金という目に見える国民負担を気にするがあまり、その結果として、もっと実物経済としての「モノが手に入らない」という意味での国民負担につながってしまっているということがあるのではないか、と思っています。
先ほど本田先生からお話のあった衆議院で予算を通すためではあったわけですが、これはまさに永田町の論理そのものだと私は言っています。社会保障費4兆円削減、社会保険料6万円引下げ、こういう話があったわけですけれども、これも現役世代の票を得んがためにこう言っておられるのだと思いますが、では、その結果、何が起きるのかというところまで議論がしっかりできているかというと、できていないと思います。
薬の場合は薬が手に入らないということで結果が出てきました。これが本体部分で言うと何が起きるかといえば、医療・介護の担い手不足というものにつながっていくわけですね。そうすると現役世代からすればその親世代を誰がケアするのか、今までその医療であったり介護であったり施設・事業所があり、病気になったら早い段階からケアしていただいていた、この体制で何が起きるかといえば、まさに現役世代そのものがケアラー化していくわけです。そうすると、もう手取り増やしますどころの騒ぎじゃないわけです。社会というのは、全体が繋がっているわけで、一部を切り取って、一部を下げて、その結果、見た目の手取りが増えるように見えたとしても、実は手取りを得られる仕事の前提が崩れてしまうというところまで及びかねない、そういう話なんだろうというふうに思っています。
一方で、やっぱり保険料の負担増加の問題はどうにかしないといけないので、ここは厳然とした我々に対して課せられている宿題だと思います。これは乱暴な議論でなはなく、皆保険制度のあり方そのものから、実は議論しないといけない話です。予算の賛成と引き換えに、永田町の論理、取引材料としてやるべき話では到底なく、もっと国民全体のコンセンサスを得るための政治全体の努力の中で解決しないといけない課題ではないかというふうに思っています。
手取りを増やすという政策も、減税とか給付とかというのは政府部門と民間部門の分配をどうしますかというだけの話で、全体が増えているわけではないわけなんですよね。まさに田畑先生がおっしゃる通りで、国富全体、国としての富をまず増やすというところからスタートしないと、右から左へお金を移しているだけでは成長しないですし、その間、外国は先進国も含めて成長しているわけですから、日本がどんどん置いていかれることに変わりはないわけです。短期的に少し懐が暖かくなったように見えたとしても、5年後どうなのか。経済政策があって、それを前提に社会保障の安定を組んでいかないといけないと思います。こういう議論をしっかりやらないといけないし、それを今、本当に意識してやろうとしてもいるのは自公政権だけだと思うんです。
削減ありきの議論で抜け落ちてはいけない医療安全の観点/本田あきこ議員
--今後の展望についてお願いします。
本田 私自身が問題意識を持っているのが、財源の出し入れのような議論になっていることです。どこを削減しようかというような議論の中で、抜け落ちているのが医療安全の観点です。安全確保への評価を疎かにした時に誰が困るのかといえば国民全員です。中でも薬剤師の役目は「当たり前」をつくることなので、ともすれば貢献度が見えにくいと感じています。処方箋の確認、患者さんに渡すお薬がきちんと合っているか、そして渡した後も副作用や服薬状況などをフォローする。そういった「当たり前」をつくることの評価をおろそかにすれば、一番困るのは患者さんや地域の方です。国家資格を持っている専門家にフルに活躍していただき、そういう人たちがいることを伝え評価することが今、やるべきことです。
薬剤師の中には政治に関心がない人もいます。医薬分業が定着し、今の仕事ができているから関係ない、ワークライフバランスの中でライフが重視、といった人もいるかもしれません。しかし、ワークがあるからこそライフの充実があります。我々のワークというのは、医薬分業をここまで来たところから進展させるか、停滞若しくは後退させるかは、今まさに生きている私たち薬剤師がつくっていくものです。薬や薬剤師に関してこれだけ大きな議論が今起きている中で、私たち薬剤師がどう政治に向き合うのかを見られている。それが次の参議院選挙で姿勢を示すことで想いを届ける原動力になると思います。一致結束で大きな声として示すことができれば、また違ったより良い景色があると信じています。
--薬剤師を生かす政策を訴えることもできますよね。
本田 それぞれの職能を尊重することが大前提です。タスクシフトというよりもタスクシェアですよね。例えば地域フォーミュラリであったり、リフィル処方箋や医療DX。こういったものを高めていくことが多職種協働による医療の質の向上につながると思います。そういうことを専門性を持つ関係者がやっていくことが大事ではないかなと思います。
医薬品の安定供給される、それを支える薬局薬剤師さんの働きがいを報酬上もしっかり担保していきたい/田畑裕明議員
--田畑議員からみて、今後の展望はいかがですか。
田畑 少し話がそれるようですが、今回、薬機法の改正、これも非常に大きなトピックです。衆議院の附帯決議にはリフィル処方箋についても、利用状況に関する実態調査を行うことやリフィル処方箋のさらなる利用促進に取り組むことについて決議されています。いろいろな効率化のメリットや患者さん側のメリットもあるわけだと思いますから、こういうことはきちんとやるべきだというふうに個人的にも思っています。それから、薬局の関係でいうと、地域における薬局の役割機能をさらに整理、明確化し、地域に必要な役割機能を持つ薬局に対し適切に診療報酬上の評価を行うことということも入れてあります。それもその通りだというふうに思います。全国津々浦々で医薬品が安定供給される、またそれを支える薬局・薬剤師さんという社会インフラをしっかり整えるということは政治の当然の役割だというふうに思います。そこで働く方が働きがい、生きがいやりがいを感じていただけることを報酬上もしっかり担保していきたいなというふうに思っています。
また、薬剤師さんの養成の話も決議しています。プライマリーケアのさらなる薬剤師への関与ということであったり、薬学教育を受けた専門性の高い薬剤師さんがさまざまな製薬の現場、臨床の現場も含めてですけれど、専門性を生かしていただけるような環境作りを進めることは大変大事だというふうに思っています。
--附帯決議の文言を読むと、野党が要望されていた内容も多かったように感じていました。
田畑 附帯決議はご存じの通り、自民、公明、立民、維新、国民の共同提案よるものです。しかし、理事会でしっかり協議をしており、その過程では当然、修文もしております。やはり与党として、現実的にできることという観点も含めて書き込んで決議したということです。衆議院で決議したことを、さらに参議院の専門性をもって肉付けをしていただく流れになります。より中身を充実をさせていくということですし、行政に対する政治、国民側からの約束をしっかり突きつけるということでありますので、地味かもしれませんが、大変大事なものです。
政策の話に関しては、大きな話と各論があるんですが、各論でいえば、総医療費をどう適正化できるか、これは当然、与党としてもチェックしていかなければいけません。なし崩し的に前例のまま右から左ということはやはり厳しいというふうに思います。その中で、リフィル処方箋の利用促進ということもあると思いますし、もうちょっと踏み込んで言うと、診療のいろんなガイドラインみたいなことを、やっぱり点検する必要があるのではないかなと思います。テクノロジーの進化、医学の進歩、そしてまた様々な医療機器の進展、もちろん現行の薬も含めて、なかなか新しいものが評価されないですとか、過去の診療ガイドラインがそのまま金科玉条の如くということについては、与党の我々としてもしっかり疑問を持ちながら、当然、現場の方々や実態との絡みということも配慮はしなければいけないと思いますが、そうしたことも含めた国民総医療費の“適正な”歳出の見直しは必要があります。しかし、何か数字がありきということではないと個人的には思っています。
そして、社会保障のフレームの“目安対応”については、やはり撤廃をするということをまず明確に我々は掲げていかなければいけない。しかし、財政当局はプライマリーバランスの黒字化ですとか、債務対GDP費の引き下げということを名目の中でギリギリ言ってくるわけでありますので、それに対抗するためには、まず危機感を共有する、具体的にはやっぱり数字ですよね。経営状況も含めてです。これまで医療機関の経営実態調査もいわゆる平均値をよく引用していたわけですが、今回は平均値ではなくて最頻値を見るという形が出てきました。すると、よりリアルな実態があぶりだされるわけですね。やっぱりそうしたところで働いていらっしゃる方々、また経営されている方々、最頻値ですから多くの皆さんの母集団だということになります。当然説得力のある数字ではないかなというふうに思います。そうした分野の方々にどう継続をしていただくかということが非常に大事です。加えて、今後、令和8年度予算以降も、我々はやっぱり成長していく社会を作っていくということですから、インフレ基調の世の中、金利のある社会ということになっていくわけです。診療報酬、薬価、障害報酬も含めて、物価・賃金に連動する、そうした報酬のあり方、仕組みということを構築する必要があると思っています。
今はなにか法定されたものではなく、まさに政治決断でいろんなことが決められてきているわけです。その都度、悲喜こもごもあるわけです。不公平感、不平等感を現場が抱かれるということはコミュニケーション上もよくないと思います。例えば物価・賃金に連動する、場合によっては消費税の問題もありますから物価・賃金以上に報酬をしっかり上げるという、そうしたことをこれまでの既存の思考回路や既存の枠組みのルールの延長線上で今回の予算編成に向かっていくということは現場が持ちません。それは自民党に対して多くの国民の皆さんの期待が失望に変わることだと思っています。
具体的に保険料に跳ねますよね、ということは非常にネガティブな投げかけをしてくるわけでありますけれど、保険者の果たす役割機能もしっかり点検をしなければいけませんし、保険料、イコール勤労世代の方々の所得にも響く話でありますから、保険料の見合いも含めながらこのフレームをどう見直していくかということが非常に難しい、どう理解や賛同を得ていくかということについて相当、我々は汗をかいていかなければいけないと思っています。
--今、話題になっているOTC類似薬の問題はいかがですか。個人的には「あれを保険からはずしたら」「これを保険からはずしたら」ではなくて、全体として医療の重症度で保険負担の“割合”を見直すぐらいの根本的な見直し議論があってもいいのではないかと思っています。
田畑 そうですね、どこをゴールにするかだと思いますけれど、今のお話だと、来年度予算の中では議論は煮詰まらないと思います。これも冷静に議論していくことが必要で、保険適用から除外するということも含めると、当然、自己負担が増える方々がたくさんいらっしゃるだろうと想像します。その考え方に基づくと副次的な副作用は何ですかということは、我々冷静に国民の皆さんに提示をしながら、OTC類似薬の関係、またスイッチ化の推進ですとか、何ができるのかを考えていかなければいけないと思っています。スイッチOTC化に関しても、我々は何も後ろ向きで、何もやって来ていなかったということではないということをちゃんと詳らかにしなければいけないとも思います。
供側給が大変だということだけでなく、患者さんにどういうことが起こるんだということを起点に/勝目康議員
--最後に、勝目議員、お願いします。
勝目 後期高齢者の負担の問題に関しても、改革の途上で、何もここが終わりという議論をしてきたわけではありません。われわれ与党も改革を進めてきている、しかし、ご負担が生じる方の実態を踏まえていくとなかなか一気には難しく、やはり調整ということは必要なんだと思います。政策当局者からすると、大ナタを振るうのは気持ちのよいことかもしれませんが、それはいったい社会にどういうその影響を及ぼすのかというところまで見ていかなければいけないんだろうと思います。結局は丁寧な議論を経ていなければ最終的には何もできないということだと思います。国民皆保険の中でどこまでを範囲にするのかというところの議論はいずれ避けられないのかもしれないですけれども、これを来年度予算までに結論を得るというのは到底無理だということは前提で申し上げますが、一定、国民のコンセンサスを得る中で社会保障の持続というものをどういう形でやるのかという議論は避けられないのではないかなというふうには思っています。ただその時にはちゃんとそのステークホルダーが関わり、患者サイドも、供給側の医療サイドも関わり、社会的合意を得る土壌というか枠組み、そういうものを作らないといけないのではないかと思います。
もう1つは、供給サイドの医療側として、ナラティブにもう少し気を配らなければいけないのではないかということは思っています。医療関係者の方々、その方たちはもちろん大変なんです、大変なんですけれども、供側給が大変なんですということで、需要側の患者さんに賛同を得ることは、僕はちょっと限界があるのではないかと思っているのです。そのシンパシーが広がっていくのかという目線を常に持っておいた方がいいのではないかと。やはり、患者さんにどういうことが起こるんだっていう、そこにナラティブの起点を置く必要があるのではないかなというところは思います。
--本日はお忙しいなか、ありがとうございました。