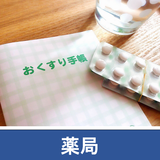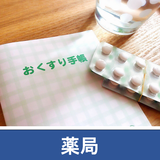要件に「無菌製剤処理の体制」
地域連携薬局の要件については、内容を見た薬局関係者から、すでにさまざまな意見が出ている。
まずは認定要件に対し「厳しい」といった声が聞かれる。そのほか、「高齢者が多くなっているので椅子は必須」「次回改定も見据えて在宅患者受け持ちに準備していく」「地域包括ケアシステムに資する研修は全国規模の企業・団体運営のものではなく地域主体のものが望ましい」「当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であることという規定は個店が意識されている」などの声がある。
こうした中、当メディアが注目した要件は、「無菌製剤処理を実施できる体制」だ。
なぜなら、現状、無菌製剤処理を実施できる薬局は極めて少なく、全国で届け出ている薬局は1862薬局しかない(平成29年4月1日時点)。約6万軒の保険薬局のうち、2000軒が無菌製剤の施設基準を満たしているとしても、その比率は約3%にしか達しないのだ。
これを単独で目指そうとすれば、地域連携薬局数は極めて少ないものとなるだろう。
厚労省も当然、それは分かっているため、付帯として「他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む」としている。
厚労省の真の狙いは、この要件に象徴される“地域の薬局同士”の連携強化ではないだろうか。
これまで、今回の要件にも記されているプライバシーに配慮した構造(間仕切り)や時間外対応、地域の医療機関や関連職種との連携などは調剤報酬上にも明記されてきた。しかしこれらの要件は、極論すれば、自薬局さえ努力すれば達成が可能であり、荒っぽい言い方をすれば、医療機関や多職種とは連携しても“隣の薬局の事情はお構いなし”でも成り立つのである。
これが、無菌調剤を実際にするかしないかは別として、「可能な体制」を満たすには、すでに無菌調剤体制を擁している薬局との連携が必要となる。このことにより、これまで希薄だった地域の“薬局同士の連携”が加速していくのではないだろうか。
薬局同士が地域で連携する必要性は在宅業務の拡充につながる。
特に“一人薬剤師”の状態が多いとされる個人薬局では、単独での在宅業務が困難な状況があり、それが在宅業務に踏み込む障害だと指摘されてきた。
厚労省では、地域の薬局同士が連携することで在宅訪問薬剤管理指導料算定を算定しやすくする「在宅協力薬局(旧サポート薬局)」の仕組みなどを整備してきたが、その利用状況は18%で、厚労省の思惑通りに進んでいない。
在宅医療を筆頭に、薬局同士もネットワークをつくり地域包括ケアに貢献しなければ、特定の薬局だけに重い負担がのしかかっていくことも考えられる。それはあるべき姿ではないだろう。今後は負担を地域で分散させていく工夫が重要になる。
「自薬局の単独活動」の評価指標から、「薬局同士の連携」も評価に加わっていく兆候が、今回の要件から読み解ける。
「他の薬局に在庫を提供できる体制」も
今回の要件の中には、「在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること」という項目もある。
まさに、いくら自薬局の努力によって地域包括ケアに貢献していようとも“隣の薬局”に目もくれない薬局は評価の対象外ということだろう。
“利他”の意識が、今以上に薬局に必要になってくるのではないだろうか。