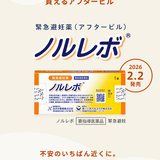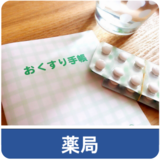提言の柱は2つ。「提言1:生活習慣病薬のスイッチOTC化の推進」。「提言2:生活者のヘルスリテラシー向上と、セルフケア・セルフメディケーション支援体制の整備」。
提言の内容は以下の通り。
■提言1:生活習慣病薬のスイッチ OTC 化の推進• 高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、糖尿病などの生活習慣病で、症状が安定し継続的に対象疾患で受診しており、⾧期間にわたり同一薬剤での治療を受けている患者に対し、医師の定期的な診察を前提に、同一成分・同一用量の OTC 医薬品を選択可能とする制度設計を進める。
• 生活習慣病領域の OTC 化推進には、日本版 CDTM(Collaborative Drug Therapy Management)を基盤とした医師・薬剤師連携体制の構築が適切である。すなわち、併発疾患のリスク評価やヘルスリテラシーレベル(疾患の理解、服薬アドヒアランスなど)を考慮した適正使用・管理プロトコールを策定し、医師、薬剤師、製薬業界、そして患者自身の4者連携による日本版 CDTM モデルを導入してはどうか。プロトコールには、医師による 6 か月から 1 年に一度程度の定期的な診察を最低限組み込んでいく。
• 保険者も含む、各医療ステークホルダー間での意見収集、調整して現実的な枠組みを提案していく。生活習慣病の予防や悪化防止などを目的とした生活習慣の改善プログラムなどの施策も枠組みの中に組み込んでいく。政府には制度構築に向け、分野毎の適正使用プロトコール策定が円滑に進むための各ステークホルダー間協議の場作りなどの仕組み作りと、それを実行するために必要な薬局での服薬支援・医師との連携および医師による指導・支援体制に対するインセンティブの創設を求めたい。
• 高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、糖尿病などは、相互に関連性が高く併発することが多く、また、生活習慣の改善プログラムなど、予防、悪化防止施策も共通しており症状が安定していれば、併発している患者も視野に入れるべきである。また、並行して検査医療機器、検査薬(穿刺血での複数検査項目のマルチ検査機器・検査薬の開発も含む)の OTC 化も促進し、患者自身が体調をモニタリングし管理するための基盤整備も進める。
• この取り組みは受診時間を十分確保できない、近くに適切な医療機関がないなどの理由により治療の継続を断念させないために有用な選択肢となり得る。
■提言2:生活者のヘルスリテラシー向上と、セルフケア・セルフメディケーション支援体制の整備
• 提案1だけでなく、セルフケア・セルフメディケーションを促進するためには、生活者のヘルスリテラシー向上が必須である。これは単に経済的な理由のみでセルフメディケーションを促進しないためにも必要な基盤となる。ヘルスリテラシーは健康に関する情報を「入手・理解・評価・活用」するための認知的・社会的スキルで、正しい情報理解に基づき生活者自身が主体的に判断することも重要な要素である。確立された医学情報の提供と自主性の醸成がヘルスリテラシー向上につながる。
• 情報提供体制:ネット上で健康情報が氾濫しているが、信頼性が低いもの、専門性が高いものが多く、OTC 医薬品の利用等を包含し、かつ、生活者が感じる「症状」から「対処」に導く総合的な情報提供はなされていない。生活者がわかりやすく判断しやすい症状別の対処方法をまとめた情報サイトの構築などの作成を提案する。生活者自身で、症状から類推できるレッドフラッグを見逃さず、OTCの活用でいいのか、それとも医療機関を受診すべきなのか、自らで極力対処できるようなフローを構築する。確立された医療情報に基づき、わかりやすいものである必要がある。関連学会、行政、企業等と連携し、標準化された生活者のためのプライマリケアの情報源をめざす。この情報は、Web サイトでの提供のほか、アプリ、書籍等での展開も視野に入れる。
• 啓発活動:継続して教育現場での医薬品適正使用の教育を推し進める。また、疾患の予防や悪化防止につながる健康情報も合わせて提供する。従来の健康教育では、情報伝達に偏重し、社会的・経済的背景を無視したアプローチで、行動変容を促すには限界がある。行動科学の理論に基づく啓発素材や単に医学的な情報だけでなく医療環境、リソースの逼迫の現状、将来への課題、なども積極的に生活者に提供し、セルフケア・セルフメディケーションの重要性の理解を深めていくとともに、自己の健康管理に対するモチベーションが高まるよう促していく。
• 支援体制:生活者のヘルスリテラシーを補完、支援するための体制も重要である。医師、薬剤師だけでなく医薬品登録販売者を含む地域医療の一部として相談体制の構築・強化を行う。特に薬剤師の臨床推論に基づく判断支援ガイドの策定をすすめ、セルフケア・セルフメディケーション・医療連携の窓口となり、生活者の疾患の自己管理支援を行いやすくする。デジタルツールを活用した医療者・生活者ネットワーキング体制も視野に入れる。
分科会では、医療の中にどのように OTC 医薬品を位置づけるのか、また、位置づけるためには、何が課題で、何を変革すべきか、広く、深く議論する必要性を強く感じ、提言に至っております。2040 年問題は日々深刻度を増しており、これから体制を作り上げていくことを踏まえますと、速やかに議論をスタートすべき時期にきていると考えるとしている。

【ジェネリック学会OTC分科会】生活習慣病薬のスイッチOTC化の推進で提言書公表
【2025.10.13配信】日本ジェネリック・バイオシミラー学会のOTC医薬品分科会(分科会⾧・武藤正樹氏)はこのほど、活習慣病薬のスイッチOTC化の推進で提言書を公表した。10月11日に盛岡市で開催された「日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第19回学術総会」「OTC医薬品分科会」のシンポジウムの場で示したもの。シンポジウムは日本OTC医薬品協会当の共催。
関連する投稿
【緊急避妊薬OTC】アプリ「ルナルナ」と協力で服薬サポート/第一三共ヘルスケア
【2026.01.14配信】⽇本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を販売開始する第一三共ヘルスケアは1月14日、ウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』と協⼒し服薬前から服薬後までをサポートすると公表した。同剤の発売は2月2日。製品の詳しい情報や購⼊・服⽤の流れ、服⽤前セルフチェック ページなどを掲載したブランドサイト(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_norlevo/)も同日、公開した。
【緊急避妊薬のスイッチOTC】承認取得/あすか製薬、販売元は第一三共HC
【2025.10.20配信】あすか製薬ホールディングスは10月20日、子会社のあすか製薬が緊急避妊薬「ノルレボ」の製造販売承認を取得したと公表した。承認取得を受け、第一三共ヘルスケアが同品の販売元として、発売に向けた情報提供体制の整備を進めるという。
【2025.06.02配信】エーザイは6月2日、国内 OTC 医薬品として初めて製造販売承認を取得したプロトンポンプ阻害薬(PPI)である「パリエットS」を発売した。
【日本薬剤師会】緊急避妊薬の調査事業を報告/「世の中の流れはスイッチ化と理解」
【2025.05.22配信】日本薬剤師会(日薬)は5月22日に定例会見を開催した。その中で緊急避妊薬の薬局販売にかかる調査事業について報告した。
【2025.05.15配信】あすか製薬は5月15日、 緊急避妊薬のスイッチ OTC について、製造販売承認申請を行ったと公表した。
最新の投稿
【緊急避妊薬OTC】アプリ「ルナルナ」と協力で服薬サポート/第一三共ヘルスケア
【2026.01.14配信】⽇本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を販売開始する第一三共ヘルスケアは1月14日、ウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』と協⼒し服薬前から服薬後までをサポートすると公表した。同剤の発売は2月2日。製品の詳しい情報や購⼊・服⽤の流れ、服⽤前セルフチェック ページなどを掲載したブランドサイト(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_norlevo/)も同日、公開した。
【東京都薬剤師会】“小規模な薬局を大規模へ”は「許しがたい」/髙橋会長
【2026.01.09配信】東京都薬剤師会(都薬)は1月9日に定例会見を開いた。その中で髙橋正夫会長は調剤報酬改定の議論に触れ、小規模な薬局を大規模へといった方向については「許しがたいという感覚を持っている」と憤りを示した。
【中医協】診療側意見、「かかりつけ薬剤師・薬局に対する評価」要望
【2025.12.26配信】厚生労働省は12月26日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開いた。令和8年度診療報酬改定への各号意見が表明された。
【中医協】支払側意見、調剤基本料1除外を要望/600 回超かつ集中率 85%超、特に都市部薬局で
【2025.12.26配信】厚生労働省は12月26日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開いた。令和8年度診療報酬改定への各号意見が表明された。
【令和8年度診療報酬改定】本体+3.09%、令和8年度及び令和9年度の2年度平均として
【2025.12.24配信】12月24日の予算大臣折衝を踏まえて、令和8年度の診療報酬改定が決定した。令和8年度及び令和9年度の2年度平均として、本体を+3.09%とする。令和8年度+2.41%、令和9年度 +3.77%とする。