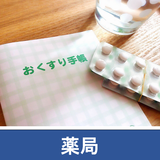WGではカルディオインテリジェンス社などが要望をプレゼンし、家庭で得られるデータを基にリスクを判定し、病名を表示することが可能になっている状況を説明。
その上で、安全性の確保や表示根拠のエビデンスがある場合に、表示は規制上、どのような問題があるのか等について質問や要望を行った。医師の確定診断を前提としつつ、どのような条件であれば表示が可能なのかなどの質問も行われた。事業者が開発にあたっての予見可能性を求めたもの。
これに対して厚労省は、「一般論としては病名を示してリスクに関する情報提供を医療機器が行うことは薬事承認の範囲内で可能」と回答。「これらの情報提供を行う製品が、専ら一般の人が購入し使用する医療機器に該当するかどうかは、当該製品が使用者に提供する情報の臨床的意義が確立しているか、使用者自らが結果を解釈し、受診の要否の判断を含めて適切な行動に繋げられるか等の観点から、個別に判断することになる。また、提供される情報の妥当性については、当該情報の裏付けとなるエビデンスに基づき評価される」とした。
今後の厚労省の対応としては、「このような製品が使用者に提供する情報の臨床的意義等について、関連学会等の専門家との協議が必要」とした。さらに、「一般の人が購入し使用する医療機器の研究開発の動向・進捗の把握が必要」とした。
留意すべき事項として厚労省は次の3つを挙げた。
(1) 健常者を含めた当該医療機器の使用者が、適切な受診機会を逃す可能性を一つのリスクと捉え、そのリスク低 減策が必要であること。特に、対象とする疾患の特性を踏まえ、家庭用医療機器としてのリスク・ベネフィット等につ いて検討が必要であること。
(2) 当該医療機器の使用者が医療機関を受診した場合に、医療機関側で適切に対応するために、当該医療機器の 性能、機能等の情報について、使用者だけでなく医療機関側へも提供が必要になること。
(3) 疾病の確定診断は、医師が行うものであること
その上で、具体的な対応策として、(1)使用者への情報提供(添付文書等による注意喚起)や、(2)医療関係者への情報提供(関係学会・医会と調整の上で、 情報提供)、(3)安全性情報の収集・追加の安全対策の実施(受診遅延や健康被害等の情報収集)、(4)その他の留意点(収集された情報のセキュリティ対策)ーーなどを挙げたという。
委員からの主な意見として、次のようなものが出たという。
・情報提供情報収集に関して、ベンチャー企業が開発するという実態も踏まえて、健康被害が起きてないという情報の収集は過度の負担なので、具体的にどういう情報収集が必要なのかどうなのかということを明確化すべきである。
・学会との協議については、利益相反の防止などが必ずしも徹底されてないような事例もある中で、いかにその透明性を向上させていくかどうかというところが課題になるのではないか
・日本の企業においては、グレーはクロと判断してしまうような傾向もあるので、産業振興の観点から行政が情報発信していくということが重要
厚労省からは、「疾患領域の分野横断的に可能な部分については考え方をまとめていきたい」との発言があったという。

【規制改革推進会議WG】家庭用医療機器において兆候を検出した疾病名の表示について議論
【2022.04.18配信】内閣府は4月18日、規制改革推進会議「医療・介護・感染症対策ワーキンググループ(WG)」を開催した。この中で議題1として「家庭用医療機器において兆候を検出した疾病名の表示について」が議論された。厚労省は「可能な部分については整理したい」との考えを示したという。
関連する投稿
【規制改革WG】事前処方・調剤の質疑への回答公表/在宅医療における円滑な薬物治療の提供で
【2025.05.01配信】規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ(第5回)」が5月1日、開催された。その中で令和7年3月14日に開催された「第2回健康・医療・介護 WG」に関する委員・専門委員からの追加質疑・意見に対する厚生労働省の回答を公表した。
【規制改革推進会議WG】訪看ステーションへの薬剤配置、輸液以外も再検討を/日本訪問看護財団
【2025.03.14配信】規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ」が3月14日に開かれた。
【規制改革推進会議WG】提案「調剤前に薬局で登録医師の確認が必要な医薬品の確認方法の統一」
【2025.03.06配信】3月6日に規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ」が開催された。その中で、規制改革ホットラインの提案事項、およびそれに対する令和6年10月18日から令和6年12月16日までの関係省庁の回答、加えてWGとしての処理方針が報告された。
【規制改革】薬局の処方箋40枚規定、「再検討」を厚労省に要望
【2024.09.30配信】内閣府規制改革推進会議「第1回 健康・医療・介護ワーキング・グループ」が9月30日に開かれた。この中で、規制改革ホットライン処理方針 (令和6年3月16日から令和6年7月19日までの回答)が報告され、「薬局に係る40枚規制」について 厚労省に再検討を要請するとした。厚労省サイドは「検討を予定」と回答しつつも、「慎重に検討する必要がある」としている。
【規制改革推進会議】規制緩和求めた「住田町」 / “町唯一の”薬局「夜間休日対応、連携で可能」
【2024.05.08配信】4月26日に開かれた内閣府の規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ」(WG) では、「在宅医療における円滑な薬物治療の提供について」が議題の1つとなり、岩手県気仙郡住田町の町長から訪問看護ステーションへの薬剤ストックの提案がされた。同町で唯一である薬局が本紙取材に応えた。
最新の投稿
【大木ヘルスケアHD】 ADTANK社と業務提携/セールスプロモーションで協業
【2026.02.26配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:松井秀正氏)は2月19日、セールスプロモーションを手掛けるADTANK株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役 CEO:菅野健一氏)と業務提携契約を締結したと公表した。なお、今回の業務提携に先立ち、大木ヘルスケアHDはADTANK による第三者割当増資を引き受け、出資している。
【大木ヘルスケアHD】“濫用防止薬”、市場にはマイナス/リテラシー向上貢献に意欲
【2026.02.26配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアHDは2月26日に会見を開いた。「2026OHKI春夏用カテゴリー提案商談会」を2月25日 (水)~2月26日 (木)まで開催しており、会期中に会見を行ったもの。
【大木ヘルスケアHD】SBI アラプロモと業務提携/「5-ALA」の市場拡大へ向けて
【2026.02.26配信】大木ヘルスケアホールディングス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:松井秀正氏)は2月24日、健康食品等の製造・販売・OEM・原料供給等を行う SBI アラプロモ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:竹崎泰史氏)と業務提携を行い、5-アミノレブリン酸リン酸塩(以下、「5-ALA」)を活用したヘルスケア市場の拡大に向けた戦略的協業を開始することと発表した。
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。