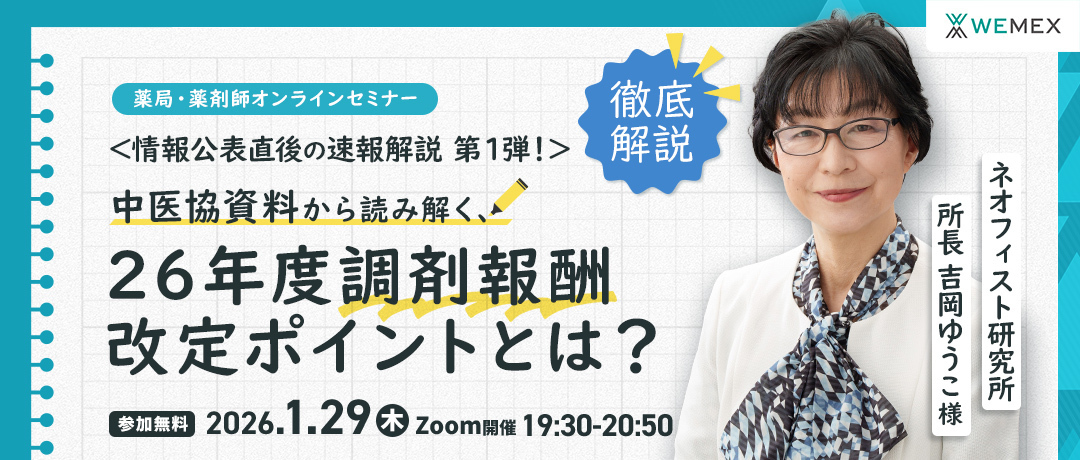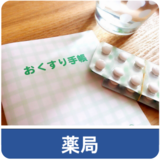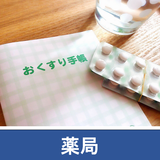東京都薬剤師会は「後発医薬品調剤体制加算に関する調査」を行い、概要を10月に公表していた。
供給不足の理由だけでなく患者や医療機関からの要望によって変更できにくい後発医薬品について調査し、東京都後発医薬品安心使用促進協議会等での議論に用いることを目的としているという。
ここ3年間の後発医薬品の調剤率推移の項目では、3年前の令和元年8月では80%台が35%だったものが、2年前の令和2年8月時点では使用率80%台の比率は48%まで上昇。一方で令和3年8月時点では使用率80%台は49%で、大きく変化していない状況がうかがえる。
「自局で特に変更できにくい頻度の高い医薬品名」については、内服薬と外用薬に分けて聞いている。
内服薬ではエディロールがトップで回答数は148。次いで2位デパス(回答数119)、3位マイスリー(同112)、4位ロキソニン(100)、5位アレロック(80)、6位ハルシオン(80)、7位メインテート(69)、8位オノン(51)、9位エルデカルシトール(47)、10位レンドルミン(42)、11位ビソプロロールフマル酸塩(41)、12位サンバルタ(39)、13位ノルバスク(38)、14位アムロジン(36)、15位ユベラ(34)、16位アルファカルシドール(33)、17位デパケン(30)、18位タケプロン(29)、18位ムコダイン(29)、20位ワンアルファ(25)、21位ザイザル(22)、21位ソラナックス(22)、23位オロパタジン(21)、24位アダラート(20)。
回答した薬局数が20を超えるのは前述の24位まで。以降、25位〜51位までは回答薬局数10以上20未満、52位〜113位までは回答薬局数4以上10未満、114位〜264位までは回答薬局数が1〜3。
これらの変更し難い医薬品の「一番の理由」では「後発薬が入手できない」が38%を占めるものの、「患者希望」が41%と高い比率だった。「医師の指示」も16%あった。
外用薬では「患者希望」によって変更し難い比率はさらに高く、「自局で特に変更できにくい医薬品の一番の理由」では、「患者希望」が62%を占めた。次いで「医師の指示」21%、「後発薬が入手できない」は6%だった。
外用薬の「特に変更できにくい医薬品名」では、1位がヒルドイド(回答薬局数669)、2位がモーラス(同551)、3位ロキソニンテープ(289)、4位アンテベート(84)、5位ホクナリンテープ(57)、6位ヒアレイン(49)、7位リンデロン(46)、8位プロトピック(25)、9位キサラタン(24)、9位シムビコート(24)、11位ボルタレン(23)などだった。
調査では、さらに「自局で取り扱う医療用医薬品を総合的に精査して、『後発医薬品調剤体制加算』が1段昇格する医薬品のうち最上位となる品目」を聞いている。
1位ヒルドイド(回答薬局数200)、2位モーラス(同105)、3位アムロジピン(90)、4位ロキソニン(75)、5位エディロール(42)、5位レバミピド(42)、7位カルボシステイン(35)などだった。
永田会長「患者満足度やアドヒアランスの観点を」
東京都薬剤師会会長の永田泰造氏は、外用薬では使用感などによって患者希望で変更し難いとの回答が多かったことを指摘。「薬局業務を行う中で外用薬については使用感などによって変えて欲しくないという希望をお聞きしているが、それが調査でも回答として表れた」(永田氏)。
その上で、製剤技術の違う製品について後発医薬品のカテゴリーからはずすべきではないかとの考えを表明した。「60%の患者さんがノーと言っている以上は、製剤的に違う外用薬は後発医薬品というカテゴリーとはまた違う考え方をしなくてはいけないのではないか。上から押し付ける使用促進ではなく患者満足度やアドヒアランスの観点から後発医薬品からはずしましょうというのが望ましいのではないか」と述べた。さらに後発医薬品の昨今の不祥事を受けて「製剤技術があったとしてもうまく活用されていない。そういったところに政府は目を向けなければいけないと思う。そういう意見が言えるのは中医協では(日本薬剤師会常務理事の)有澤委員しかいないと思うのでぜひ頑張っていただきたい」と述べた。