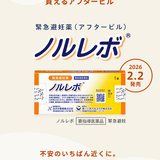厚労省は昨年12月24日に中間とりまとめの案を議論していた。
議論の詳細は以下の当メディア記事を参照いただきたい。
https://www.dgs-on-line.com/articles/620
記事にも記載している通り、日本医師会常任理事の長島公之氏から「医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等」に関して、「自覚症状がないものに使用する医薬品については、スイッチ OTC 化すべきではないとの意見もあったと記載してほしい」との要望があった。これに座長の笠貫 宏氏(早稲田大学特命教授 医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問)が、意見としての記載は了承する意向を示していた。
こうした議論の結果、「中間とりまとめ」に、慎重意見が併記された格好だ。
また、「スイッチOTC化の適切性は個別の成分毎に議論されるものであるが」という文言が追加された。この文言のあとには、もともとあった「どのような薬効群の医薬品がスイッチ OTC 化の対象となるのか、その具体的な条件については、各ステークホルダーの連携等の更なる環境の整備の状況も踏まえつつ、個別の成分の議論等を通じて、今後も議論が進められる必要がある」との文章が続く。
意見としての記載であるため、上記の考え方が最終的に否定されたわけではないといえる。基本的には個別の成分の議論となるため、薬食審での議論が展開されることになりそうだ。
上記の変更点が、前回の「中間とりまとめ案」から「中間とりまとめ」までの主な変更点だ。
***************
改めて「中間とりまとめ」の意義を考察してみたい。
まず重要な点は、「医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等」のスイッチの扉が閉ざされなかった点である。
これは表現を変えると慢性的な症状と受け止めることができ、産業界が生活習慣に関連する症状を想定していると考えられる。
このカテゴリーのスイッチにあたって焦点となるのが「自覚症状」の有無である。
例えば、日本チェーンドラッグストア協会がスイッチ化を優先的に要望しているもののうち、片頭痛薬「イミグラン」やアレルギー性結膜炎薬「パタノール」、吐き気改善薬「ナウゼリン」、胃潰瘍薬であるPPI「オメプラゾン」「オメプラール」などは自覚症状のあるものといえるのではないだろうか。一方、食後過血糖改善薬「ベイスン」などは、どのように自覚症状を定義するかは難しい面もあるように思える。
また、こうした成分が議論される前提として示されているのが、薬剤師等の知識習得やセルフチェックシート・お薬手帳の活用、医師と薬剤師等の情報共有という位置づけとなる。
スイッチOTC促進は製薬企業だけで進められるものではなく、販売を担う薬局・ドラッグストアの“本気度”も問われるだろう。
慢性的な症状のスイッチ化が正しいのか、重症化をもたらすのではないかとの議論は常につきまとう。しかし、現状でも未受診者、受診離脱者は一定数いると考えられ、こうした層に薬局やドラッグストアからもアプローチができる手段が増えるととらえれば社会的意義は大きいのではないだろうか。
医師か、薬剤師か、の議論ではなく、一定の条件の下で、生活者がアクセスしやすい環境整備が理想的だ。そのためには、要指導薬固定条件でのスイッチや、販売条件を逸脱した店舗は一定の期間の販売停止など、厳正な条件を設けることも一案ではないだろうか。特に医療リソースの限られる地域では、こうしたスイッチによって生活者のQOL改善に貢献したいとの意欲を持つ薬局・ドラッグストアは少なくない。一部の不適切販売によって、全体の機会が奪われるのは社会にとって好ましいことなのかどうか。
少子高齢化の進むわが国で、スイッチの健全な在り方はどのようにあるべきか。前例にとらわれない新しい制度の枠組みも期待したい。
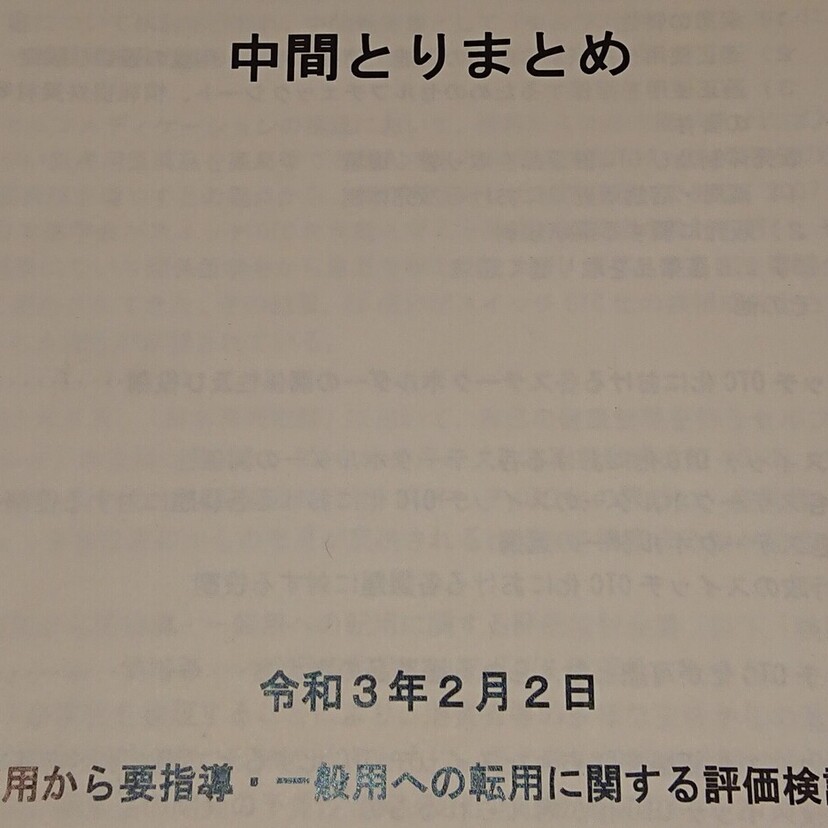
【スイッチ検討会議中間とりまとめ】「自覚症状のないスイッチ」への慎重意見併記
【2021.02.10配信】厚生労働省は、「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の「中間とりまとめを」公表した。焦点であった「医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等」に関しては、「自覚症状がないものに使用する医薬品については、スイッチ OTC 化すべきではないとの意見もあった」との慎重意見が併記となった。
関連する投稿
【緊急避妊薬OTC】アプリ「ルナルナ」と協力で服薬サポート/第一三共ヘルスケア
【2026.01.14配信】⽇本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を販売開始する第一三共ヘルスケアは1月14日、ウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』と協⼒し服薬前から服薬後までをサポートすると公表した。同剤の発売は2月2日。製品の詳しい情報や購⼊・服⽤の流れ、服⽤前セルフチェック ページなどを掲載したブランドサイト(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_norlevo/)も同日、公開した。
日本初のOTC緊急避妊薬「ノルレボ」新発売/第一三共ヘルスケア
【2025.12.18配信】 第一三共ヘルスケア株式会社(本社:東京都中央区、社長:内田高広氏)は12月18日、日本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を2026年2月2日(月)に発売すると公表した。価格(メーカー希望小売価格)は1錠 6800円(税込み 7480円)。
【緊急避妊薬のスイッチOTC】承認取得/あすか製薬、販売元は第一三共HC
【2025.10.20配信】あすか製薬ホールディングスは10月20日、子会社のあすか製薬が緊急避妊薬「ノルレボ」の製造販売承認を取得したと公表した。承認取得を受け、第一三共ヘルスケアが同品の販売元として、発売に向けた情報提供体制の整備を進めるという。
【ジェネリック学会OTC分科会】生活習慣病薬のスイッチOTC化の推進で提言書公表
【2025.10.13配信】日本ジェネリック・バイオシミラー学会のOTC医薬品分科会(分科会⾧・武藤正樹氏)はこのほど、活習慣病薬のスイッチOTC化の推進で提言書を公表した。10月11日に盛岡市で開催された「日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第19回学術総会」「OTC医薬品分科会」のシンポジウムの場で示したもの。シンポジウムは日本OTC医薬品協会当の共催。
【2025.06.02配信】エーザイは6月2日、国内 OTC 医薬品として初めて製造販売承認を取得したプロトンポンプ阻害薬(PPI)である「パリエットS」を発売した。
最新の投稿
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【コミュニティファーマシー協会】ドイツ薬局視察旅行の参加者を募集
【2026.02.22配信】 日本コミュニティファーマシー協会はドイツの薬局を視察する旅行参加者を募集する。 旅行期間は2026年6月8日(月)〜6月13日(土)まで4泊6日。申し込み締切は、2026年3月5日(木)。
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。