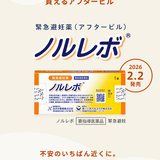緊避妊薬とPPIはパブコメの意見を考慮し再議論も
今回の検討会では、事務局が前回の中間とりまとめ案から変更になった箇所を説明。それに対し、日本医師会・常任理事の長島 公之氏が数多くの意見を出し、それに座長(早稲田大学特命教授 医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問・笠貫 宏氏)や事務局が応答するような形になった。
まず検討会では、事務局が今回の中間とりまとめ案に関して、前回提示の内容から変更した点を紹介した。
前回、座長から「パブリックコメントが検討会に与えた影響」に関して、「これまでの議論」の総括として加えるべきではないかとの指摘があったことから、以下の文言が追加された。
“これまでのパブリックコメントを総括すると、多くの候補治療薬については、検討会議の評価結果案に対して、意見なしも含め賛成する意見が寄せられた。また、スイッチ OTC 化が可とされた候補治療薬の中には、検討会議の結論として、パブリックコメントを踏まえて検討された効能・効果が採用されている。一方、パブリックコメントで検討会議の評価結果案に対して反対意見が多く寄せられたものとして、緊急避妊薬及び胃酸分泌抑制薬があげられる。これらについ ても、検討会議の評価結果は、現時点においてスイッチ OTC 化は認められないものの、将来的なスイッチ OTC 化の議論を妨げるものではなく、パブリックコメントで提案された解決策等も含めて検討会議の結論としている。このように、検討会議では、パブリックコメントがスイッチ OTC 化の意思決定に国民の意見を反映させる役割を一定程度果たしてきたといえる。”
環境整えば否とされた成分も再議論。医師との連携で
「各ステークホルダーのスイッチ OTC 化における各課題に対する役割について」の項では、以下の文言を追加した。 “各ステークホルダーがそれぞれの課題を解決することにより、これまでの検討会議において、販売体制やスイッチ OTC 化した際に受け入れる環境が整っていないことを理由に否とされたものについても、課題とされた点について議論を進めることが可能となると考える。”
“また、各課題を解決する上で、薬剤師と医師の連携が重要なこともとりあげられた。連携については、薬剤師と医師の連携だけではなく、それ以外の各ステークホルダーとの連携、横断的な連携も重要であり、具体的にどのような連携が有用で実施することが可能か議論を進めていく必要がある。”
ステークホルダーの関係性の図については、内容の変更ではないが、使用者を中央にする形で三者が周りを囲む図にした。
「各ステークホルダーの連携について」を追記。「医師との連携重要」
「各ステークホルダーの連携について」は、以下の文言を追記した。
“OTC 医薬品の適正販売、適正使用の確保及び取り巻く環境の改善を進めていくためには、各ステークホルダーがそれぞれの役割を果たすだけでなく、各ステークホルダーが連携して取り組んでいくことが重要である。使用者を中心として、ステークホルダー横断的に連携が行われることが望まれるものとして、薬局等と医療機関等との連携体制の構築、情報共有があげられている。
“特に医師と薬剤師の連携は、検討会議において重要性が指摘されている。薬局ビジョンにおいては、「かかりつけ薬剤師・薬局は、主治医との連携、患者に対する丁寧なインタビュー、患者に発行されたお薬手帳の内容の把握等を通じて、当該患者がかかっている全ての医療機関を把握し、要指導医薬品等を含めた服薬情報を一元的・継続的に把握することが不可欠である」とされており、医療用医薬品と同様、OTC 医薬品でも直接又は使用者を通じた連携による情報共有が重要と指摘されている。”
“薬局等と医療機関等との連携体制については、受診勧奨等を行う上での近隣地区の病院とのあらかじめの連携、また、開局時間外や夜間・休日等の相談体制の確保を行うための地区薬剤師会や近隣薬局等の連携が想定される。”
“使用者の適正使用を促進していく上での連携や情報共有については、使用者の適正使用を促進していく上で、どのような方法(ICT 等を利用した一元的な管理、お薬手帳の活用等)でどのような情報(服薬履歴、受診履歴、臨床検査値等)を共有すべきか議論がある。”
「検査値情報が必須のものはスイッチすべきでない」意見表記
上記「連携」の続きとして、以下の文言も追記されている。
“共有する情報については、特に臨床検査値について議論が行われた。臨床検査値共有は、患者が希望する場合において現在でも薬局と医療機関の間で行われており、セルフメディケーション推進の観点から必須と考えるとの意見がある一方、連携や情報共有はスイッチ OTC 化に限った話ではなく、検査情報がないと販売できないものは、そもそもスイッチ OTC 化すべきではないとの意見もあった。”
“いずれの意見においても、情報共有を行うためには、使用者が望む情報のみがプライバシーを確保の上共有される必要があるとされており、情報共有のあり方、各ステークホルダーの連携やかかわり方等について、どのような場で議論していくかも含め、今後議論が進められる必要がある。”
リスク区分の移行の仕方に関して議論を
「規制当局の役割」の項では、制度検討の箇所で以下のように文章が変更になった。
「なお、インターネット販売について問題があると指摘されたが、インターネット販売に伴う安全確保策、制度の検討等については、別途議論を深める必要がある。」は前回も記載があったが、以下の文章が追加になった。
“また、併せて要指導医薬品から一般用医薬品への移行の仕方等の制度の検討についても、別途議論する必要がある。”
スイッチの要件、「一定期間内の診断情報で適正に使用できるもの」追加
「スイッチ OTC 化が可能と考えられる医薬品の考え方」の項では、「②使用する際に使用者自身が症状から判断することが可能であり、使用者自身が適正に購入し短期間使用できる医薬品であること」という表現は前回もあったが、その項に続く文章が以下に変更になった。
“または、使用者のみでは自己判断が難しい症状であるものの、一定期間内の診断情報、服薬指導等といった医師、薬剤師による一定の関与により、使用者が適正に購入し使用できる医薬品であること。” ここで特に追加となったのは、「一定期間内の診断情報、服薬指導等といった」の文言だ。
上記②を満たしたものの中で、スイッチが可能と考えられるものについては、すでに承認されたものと、今後、スイッチが考えられるものを分けて記載とした。
「新たにスイッチOTC化が考えられるもの」として、以下の文言を記載した。
“医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等”。
“前記については、各ステークホルダーの連携等の更なる環境の整備の状況も踏まえつつ、どのような薬効群の医薬品がスイッチ OTC 化の対象となるのか、その具体的な条件については、個別の成分の議論等を通じて、今後も議論が進められる必要がある。”
「環境整備」を追加
さらに、スイッチ化を進めるためには環境整備が強く求められているという項目を追加。
“薬剤師(または登録販売者)が消費者に対して適切な情報提供ができるための知識習得の促進”
“薬剤師による適正販売が確保されるよう、セルフチェックシート等を用いた確認の徹底及び記録の管理”
“お薬手帳等の活用による医療用医薬品と OTC 医薬品の情報の一元的・継続的な把握”
“医師、薬剤師等、各ステークホルダーの情報共有等を介した連携による適正使用、適正販売の促進”
検討会での「パブコメ」は継続。検討会議に承認情報をフィードバック
「今後の検討会議の進め方について」の項では、以下を追記した。
“課題等の解決策を検討する上で、幅広いステークホルダーの意見を踏まえることが重要であることから、従前のように検討会議の意見についてパブリックコメントを行った上で再度議論する仕組みを維持する”
“また、中間とりまとめであげられた課題について、内容に応じて、検討会議で継続的な議論を行う。”
“検討会議で検討を行った成分について、その承認状況等を適宜検討会議にフィードバックを行う。”
医師会・長島氏「セルフチェックシートの評価」追記要望
続いて質疑・意見陳述に入った。
日本医師会・常任理事の長島 公之氏が意見を複数出した。主な項目は、セルフチェックシートとお薬手帳の価値、「医師の管理下のスイッチ」だ。
まず、「これまでの議論の経緯の中にセルフチェックシートの評価を入れる」ことを要望した。
「セルフチェックシートが規制を強めるようなものという批判もあったが、それは全く逆でセルフチェックシートによって安全性が担保できることで一般用に転用してよいと、むしろ転用を進めるための有用なものであるという記載があった方がいいと思う」(長島氏)とした。
「疾患の判断」とある表現については、「使用の判断」と変更することを求めた。具体的には「症状のみから疾患の判断が困難な場合であっても」といった表記に関し、「使用の判断が困難」が適切とした。
「消費者自身」という表現についても、「使用者自身」の表現が適切とした。
「ステークホルダーの役割」に関しては、「基本は薬機法の国民の責任の表記にある」とした。「薬機法では、国民の役割として、医薬品等を適正に使用するとともに、有効性・安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないとされており」の表現を上位に持ってきて、「それを実現するために各ステークホルダーがこれこれをすべきという構成にした方がよい」と指摘した。
お薬手帳の重要性も指摘。「薬局、医療機関だけでなく、使用者本人も含めた三者が同じ情報を共有するという意味で、お薬手帳は非常に重要だ。例えば、薬剤師は必ずお薬手帳をかかりつけ医に指導することは重要。医薬品名だけではどんなものかを探すのは大変なので、医薬品の情報が追記されていると使用者も分かりやすいし、医師もその情報である程度の判断ができる」とした。
規制当局の役割については、「規制当局だけでなく、教育の面では文部科学省、薬局の経営という面では経済産業省も関係してくるので、規制当局を中心とする行政全体で役割を果たすということが必要ではないか」とした。
医師会・長島氏「スイッチ要件に安全性を第一に」
続いて長島氏は、スイッチの要件に関連して、「安全性というのは第一に重要なので、それは記載した方がよい。成分として安全性が高いと入れるべき」とした。
「個々の成分で例えば薬事の審査、対象となる病態や状況、あるいは副反応も同じ薬効でも違うということがあるので、単純に同じ薬効分類だからいいということではなく個別性があるところについてはきちんと検討する必要があるという観点は記載すべきだ」とした。
新たにスイッチ化が考えられるとして掲げられた「医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等」に関しては、「“状態とは自分で判断できる状態なのかどうか、例えば検査結果、あるいは自分で判断してよいものなのかどうか、対処方法が確定するとはどういう意味なのかというところでかなり状況・薬物によって違うので、これは申請が上がってきたら一つ一つ丁寧に議論すべき。考え方で整理するのは重要だが、一つ一つの成分には個別性もあるため、丁寧に議論し、建設的な結果につながるように議論することが重要だと思っている」とした。
座長は、長島氏の指摘について一つ一つ議論するとした。
まず、セルフチェックシートに関して座長は、「あまりにも厳しい内容になると、使用者も書きにくいし薬剤師も評価しにくいと言いう規制を強める、必要で大事なということは書いてもらわないといけない」と指摘。
長島氏は「安心・安全のための有効なツールであるということを記載していただければ」と要望した。
事務局は「セルフチェックシートは重要と理解しているので、重要性を表現する文言を追加したりすることで対応したい」と回答した。
これに関連し、日本薬剤師会 常務理事の岩月進氏は、「セルフチェックシートのセルフとはだれのセルフかというと薬剤師ではなく、症状を訴えている方自らが自分のことを考えて、コミュニケーションが取れるためのものだと理解している。重要ではあるが、まずは患者さんがご理解いただくためのものなので、専門家から言われた通りに回答するのではなく、ご自身が考えてチェックすることで適正使用につながるものと認識している。薬剤師が関与して回答を誘導したりしてはいけないということは確認をしておいた方がよいと思う」と発言した。
座長は「セルチェックシートの重要性は構成委員が理解していることだと思う」と話した。
産経新聞社論説委員の佐藤 好美氏は「長島委員の言葉に感銘を受けた。セルフチェックシートが阻害するものではなく、これをツールにすることでOTC化を進めるのだというところ、その方向性を描いていただければいいと思う」と話した。
座長は「セルフメディケーションを推進するためにセルフチェックシートが有効なツールであると記載することでよいのではないか」とした。
お薬手帳の重要性については、項目として独立させ、記載することになった。
規制当局の役割に関しては、「行政」という表現にすることになった。
長島氏の「個別の議論が必要」との指摘について事務局は、「実際にスイッチ化する時は、実際は個別の議論になるので中間とりまとめとして整理はするが薬食審では当然、個別の議論になるとは思う。表現は検討したい」とした。
長島氏は「それに対する意見として、きちんと自分で自覚症状で判断できるもの以外に対してはすべきではないという意見があったことは記載してほしい」と求めた。
これに対し座長は、「私も両論併記でよいと話してきた」と応答。
事務局も「こうした議論があったということは記載したい。具体的な条件などについては今後、議論することになると思う。ご意見は書いたうえで、各論は引き続きの議論が必要としたい」と話した。
佐藤氏は三者で同じ情報を共有することが大切という意見に共感します。医師の役割のところにもお薬手帳を記載したらどうか」とした。
事務局は「記載すべきだと思いますので記載いたします」とした。
検討会議はどういう成分がスイッチ化できるかを整理
国民生活センター理事の宗林さおり氏は「使用者と国民という表現が混在している。どんな人から申請が出てくるかのところでも個人という表現が出てくるが、このあたりを意識して書き分ける必要がある。使用者で統一してはどうか」とした。
事務局は、「統一させていただくように検討したいと思います。ただ、薬機法上、国民という表現がありますので、できる限り使用者としながら、かっこ書きで国民とするなどしたい」とした。
座長は「ほかに意見はないか」と求めた。
構成員は「セルフチェックシートに関して、使用者がチェックして薬剤師が確認すると書かれているが、確認の上で安全性に問題があった時の対応はどうなるのか。受診勧奨するのか」と質問を出した。
事務局は「現実としては受診勧奨などの対応は起きていると理解している」とした。
日薬の岩月氏は、「セルフチェックシートは患者さんとコミュニケーションを取った上で、あてはまらない場合は販売しないということになっている。それでも症状を訴える方がいたら、OTC薬の範疇ではないことをお伝えし、受診勧奨をするということになる」と説明した。
構成委員からは「仮に副作用が出た場合、有害事象が出た場合はPMDAに報告するのでしょうか、医師が報告するのでしょうか。また、その時点で販売を」と質問が出た。
事務局は「患者自ら報告する制度、薬剤師、医師からの報告も制度がある」と説明した。
長島氏は「副作用が出た時にここに報告すればいいということや、副作用救済制度などが使用者にしっかり伝わっているのかどうかは重要だが、いかがか」と質問した。
事務局は「国民の認知度などを調査し、電車広告、政府広報なども通して認知度向上に努めている。とりまとめの環境整備の項に記載したい」と説明した。
長島氏は「まさにOTC化を推進するための環境整備として積極的に進めてほしい」とした。
宗林氏は「重篤な副作用に関する情報に関して、処方箋調剤を待っている間に見られるような掲示をするなどお願いしたい」とした。
また宗林氏は「この検討会議を通さず、薬食審に直接申請するという道もできるのか」と質問した。
事務局は「検討会議は予見性を高めるという意味で、どういう成分がスイッチ化できるかを整理している会議体になる。そこで整理されたものがそれに従って開発がなされる、申請がなされるというルートだということ」と回答した。
また現状について事務局は、「これまでの運用としては、検討会議の当初の議論の中でスイッチ化されるものはすべて検討会議で議論するという確認があったため、PMDAに直接相談があった際は検討会議に出すよう要望をしてきた。今後に関しては規制改革推進会議の関係もあり、直接申請することを可能とすべきだという議論があるということ」と付け加えた。
岩月氏は宗林氏の重篤な副作用の認知の問題に関連して、「販売制度が変わっても中身は同じなので、医療用でも一般用でも同じような注意喚起をすることが必要と理解している。販売の形態が変わるだけであるので、重篤な副作用に関しても、何かあればご連絡をくださいとしております」とした。
構成委員からは、「使用者が情報提供するとあるが、使用者が薬剤師のフォローアップのための情報提供もするのだということが図の中で記載されていると分かりやすいと思う」という意見が出た。
なお、同日の検討会議の後段では、今後の検討会議の在り方について議論された。
*******************
前回から今回の開催までに議論された主要なポイントの一つが、「新たにスイッチOTC化が考えられるもの」として掲げられた“医師の管理下での処方で長期間状態が安定しており、対処方法が確定していて自己による服薬管理が可能な医薬品等”(以下、「医師の管理下」と表現)であることは、事務局の変更点の説明でも明らかだ。
にもかかわらず、議論の中で座長も、日薬・岩月氏も正面からそのテーマに触れようとはしなかった。
医師会の長島氏が「医師の管理下での処方で長期間状態が安定しているという、“状態”とは自分で判断できる状態なのかどうか、例えば検査結果、あるいは自分で判断してよいものなのかどうか、対処方法が確定するとはどういう意味なのか」と述べたことは、皮肉にも、議論を視聴していた多くの人の疑問を代弁したといえる。
つまり、それだけ、このテーマに関して、議論が尽くされていないということだ。
事務局は、同カテゴリーを記載だけして、具体的な条件は今後、引き続き議論するという姿勢を示した。検討会議はどういう成分がスイッチ化できるかを整理するだけでその整理に基づいて申請がなされるという説明もされている。今後、同カテゴリーの具体的な申請が薬食審にされる可能性もあるだろう。
同カテゴリーが急浮上したのには、産業界が申請を念頭においている具体的な成分があるはずだ。しかし、その具体像を議論すればするほど、この検討会議の新たな範疇と乖離してくることを懸念したことが考えられる。すなわち、今後は個別的な成分の議論は、薬食審に譲るということだ。
規制改革推進会議は、この検討会議で個別成分の議論、可否を行うことは薬機法に照らし合わせても不適切であると指摘してきた。
今後は薬食審でどのような成分が、どのように審議されていくのか、注意深くみていきたい。スイッチOTCのカテゴリーが拡大すること自体は、国民の選択肢を増やす意味で歓迎すべきことだ。ただ、これまでも議論の過程であまりにも医師の関与を強めたことで、実際に生活者の手に届きにくいスイッチOTCが誕生してしまう懸念は持たれてきた。医師と薬剤師の連携度合いと、生活者のアクセシビリティのバランスはとてもさじ加減が難しいところだろう。
新たに広がるスイッチOTCの領域に期待したい。検討会議では具体的なスイッチ候補成分を推し量ることはできないが、今後、スイッチが具体的に議論されてくる個別成分に関しては、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が要望書としてまとめている優先5成分が参考になるだろう。
JACDSは、吐き気改善薬「ナウゼリン」のほか、片頭痛治療薬「イミグラン」、胃潰瘍薬であるPPI「オメプラゾン」「オメプラール」、食後過血糖改善剤「ベイスン」、アレルギー性結膜炎薬「パタノール」を優先成分に挙げていた。
これに、今回の検討会議でも確認された緊急避妊薬の再議論などが加わるだろう。
これらは検討会議ではなく、薬食審での議論となる可能性がある。
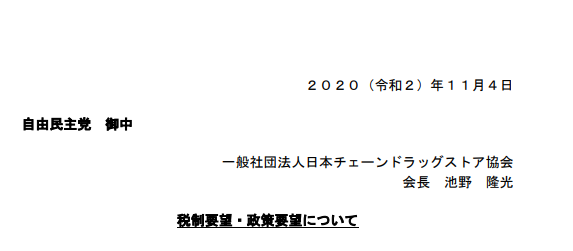
【ドラッグストア協会がスイッチOTC化要望】吐き気改善薬「ナウゼリン」や片頭痛薬「イミグラン」のほか胃潰瘍薬のPPI、食後過血糖改善剤
https://www.dgs-on-line.com/articles/492日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は医療用医薬品からOTC医薬品への転用(スイッチOTC)の拡大を求めている。11月4日に開かれた自民党の「予算・税制等に関する政策懇談会」では、厳選した5成分の早期スイッチを要望した。吐き気改善薬「ナウゼリン」のほか、片頭痛治療薬「イミグラン」、胃潰瘍薬であるPPI「オメプラゾン」「オメプラール」、食後過血糖改善剤「ベイスン」、アレルギー性結膜炎薬「パタノール」だ。JACDSはOTC医薬品業界とも意見調整済み。政府、厚生労働省にもスイッチOTC推進の機運が高まる中、これまでにないスピード感の発売に期待がかかる。生活習慣病関連薬も挙げられており、発売となれば市場へのインパクトも大きい。