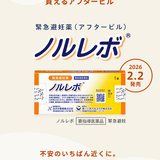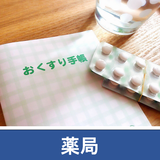8月22日に厚労省が「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業一式」に関して一般入札を公告していた。
これを受け、日本薬剤師会では入札する意向を表明した。主任研究員は日本薬剤師会の常務理事も務める帝京平成大学薬学部長の亀井美和子氏とする予定。
日本薬剤師会会長の山本信夫氏は、競争入札であるため日薬が考えている調査事業内容詳細については明らかにできないと断った上で、「社会的にも大きな議論になっている。都道府県薬剤師会と協力して実施体制をとれるような整備を進めたい」と述べた。日本医師会、日本産婦人科医会とも連携体制をとり、安全に進めたいとの考え。
山本会長は「使う方のことを考えて対応したい」とするとともに、「緊急避妊薬にだけ限ったことではないが、適正に販売されなければいけないと思っている。そういった意味ではしっかりと対応したい」と述べた。「いろいろな意味で耳目を集めている。使い方を間違えた時に及ぼす影響は大きい」として、受託した場合の責任の大きさへの認識をにじませた。
具体的な内容は事業受託が決定し次第、報告したい考え。
同調査事業は緊急避妊薬のスイッチOTC化を議論している「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」でも提案、了承されていた。検討会では「地域の一部薬局における試験的運用」を提案し、その手法として、一定の要件を満たす特定の薬局に限定し、試行的に女性へ緊急避妊薬(処方箋医薬品)の販売を行うことを通じて、適正販売が確保できるか、代替手段(チェックリスト、リーフレット等の活用)でも問題ないか等を調査解析するモデル的調査研究を委託研究として実施する方法が考えられるとしていた。
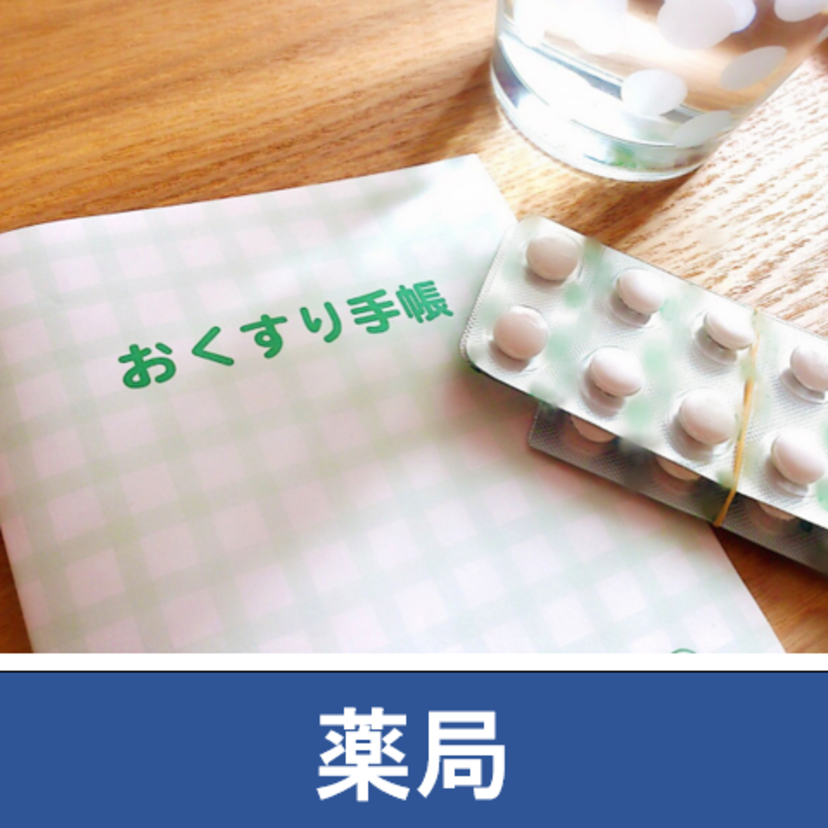
【緊急避妊薬の薬局販売】日本薬剤師会が調査事業に入札表明
【2023.08.23配信】日本薬剤師会は8月23日に開いた定例会見で、緊急避妊薬の薬局販売に関する調査事業に入札する意向を表明した。
関連する投稿
【緊急避妊OTC薬】取扱店検索システム提供/第一三共ヘルスケア
【2026.02.08配信】第一三共ヘルスケアは2月3日、緊急避妊薬「ノルレボ」の販売店検索システムを公開した。最寄りの取扱店舗を位置情報から検索できるほか、駅名・住所からも検索可能。
【緊急避妊薬OTC】全国5000超の薬局等が販売へ/1月19日時点リスト、厚労省
【2026.01.19配信】厚生労働省は1月19日時点での緊急避妊薬OTC(要指導医薬品)の販売が可能な薬局等の一覧を公表した。全国で5000超の薬局・店舗販売業の店舗が登録した。
【緊急避妊薬OTC】アプリ「ルナルナ」と協力で服薬サポート/第一三共ヘルスケア
【2026.01.14配信】⽇本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を販売開始する第一三共ヘルスケアは1月14日、ウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』と協⼒し服薬前から服薬後までをサポートすると公表した。同剤の発売は2月2日。製品の詳しい情報や購⼊・服⽤の流れ、服⽤前セルフチェック ページなどを掲載したブランドサイト(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_norlevo/)も同日、公開した。
【日本薬剤師会】会員1671人減少、10万人切る/組織強化委員の報告書は年明け完成見込み
【2025.12.23配信】日本薬剤師会は12月23日に定例会見を開き、日本薬剤師会の全国会員数調査報告について報告した。
日本初のOTC緊急避妊薬「ノルレボ」新発売/第一三共ヘルスケア
【2025.12.18配信】 第一三共ヘルスケア株式会社(本社:東京都中央区、社長:内田高広氏)は12月18日、日本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」(要指導医薬品)を2026年2月2日(月)に発売すると公表した。価格(メーカー希望小売価格)は1錠 6800円(税込み 7480円)。
最新の投稿
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【コミュニティファーマシー協会】ドイツ薬局視察旅行の参加者を募集
【2026.02.22配信】 日本コミュニティファーマシー協会はドイツの薬局を視察する旅行参加者を募集する。 旅行期間は2026年6月8日(月)〜6月13日(土)まで4泊6日。申し込み締切は、2026年3月5日(木)。
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。