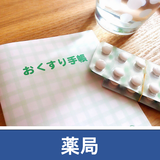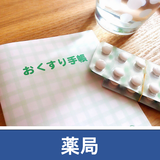「空気も“タダ”ではない時代がくる」
5月14日に、奈良県立医科大学(微生物感染症学 矢野寿一教授、感染症センター 笠原敬センター長)とMBTコンソーシアム(感染症部会会員企業:クオールホールディングス、三友商事、タムラテコ、丸三製薬バイオテック)の研究グループが、世界で初めてオゾンガス曝露による新型コロナウイルスの不活化を確認して注目を集めた。
その後も、クオールHDでは同社のプロジェクトチームが、日本オゾン協会が認定する「オゾン安全管理士」の資格を取得し、安心・安全を前提に、年間 1 万台の販売を目指す方針を示すなど、精力的な動きをみせている。
このオゾン発生器を製造しているのが大阪府東大阪市に本社のあるタムラテコだ。2003年に設立された同社は、創立からオゾンを活用したテクノロジーを手掛けてきたベンチャー企業。同社社長の田村耕三氏は、「水が“タダ”ではなくなったように、安全な空気もいずれタダではなくなる」と予想する。現在、オゾン発生器を活用しているのは救急車両や医療機関、人の集まる施設が中心だが、「いずれ家庭の中まで入っていくのではないか」と指摘。その過程にあっては、オゾンの知識を正しく生活者に伝えることのできる薬局の介入が望ましい選択肢の一つとの考えも示した。
低濃度のオゾンでの効果実証
クオールHDの研究結果に続いて、8月26日には藤田医科大学(愛知県豊明市)の村田貴之教授(ウイルス・寄生虫学)が人体に安全な低濃度オゾンガスで新型コロナウイルスを不活性化できることを確認し、研究発表を行った。実験に使われたのはタムラテコの機器だ。
この研究が既報の実験と違うのは、既報の実験は1.0〜6.0ppmという高濃度のオゾンガスを使用しているのに対し、0.1ppmという低濃度オゾンの検証をしたこと。有人でのレギュレーションが0.1ppmであることから、既報の研究結果に対し、「1.0ppmでは人体への毒性はどうなのか」という声や、「0.1ppmでの効果はどうなのか」という疑問の声があった。
今回は低濃度(0.05または0.1ppm)のオゾンガスでも新型コロナウイルスに対して除染効果を確認した。
オゾンガスは多くの病原体を不活化する効果があることが知られているが、その効果は、「濃度(ppm、Concentration)×時間(Time)」の「CT値」に相関する。先の奈良県立医科大学の実験ではCT値60(1ppmで60分)と330(6ppmで55分)において効果を測った。藤田医科大学の実験では、湿度80%でCT値60(0.1ppm で10時間後)で4.6%までウイルスの感染性が低減。CT値24(0.1ppm で4時間後)でも13%まで低減していた。
日本産業衛生学会は、作業環境基準としてのオゾン許容濃度を0.1ppm(労働者が1日8時間、週40時間浴びた場合の平均曝露濃度)と勧告しているため、今回の結果は有人が可能な濃度でも効果があることを実証したといえる。
ちなみに、オゾンの運用として消防庁や総務省はCT値60で運用している。消防庁では救急車両の消毒などに用いられている。厚生労働省で医療機器として認可されている同社の機器のCT値は330だ。
「オゾンのメリット・デメリット理解が前提」
この結果を受け、これまで救急車両や医療機関、人の集まる施設が中心だった導入先が、家庭まで広がる可能性は大きくなってきた。
同社も一般家庭への導入には肯定的だ。
ただ、スピード感を持った拡大には二つの壁がある。
1つは同社が一般家庭にまで一気に機器を導入するような企業規模では、現状はないこと。
同社の納入先はこれまで、警察や消防、自衛隊など、官公庁が6割を超えていた。いわば、「特定の場に特殊な機器を販売するベンチャー企業」であったわけだ。年商も前期は18億と、決して大企業ではない。それが、今回の新型コロナウイルス感染症の発生により、病院、飲食店も含めて需要が爆発的に伸びた。既存の納入先でもアルコール不足などを背景に、同社のオゾン発生器を求めるニーズが大きくなった。
増産が需要に追い付かないのが現状だ。需要増は10倍や20倍ではなく、製品によっては3桁レベルで急増しているという。新型コロナウイルス感染症は機器のパーツの入手にも影響を及ぼしている。
「2月に中国からパーツが入らなくなった。4月は東南アジア、8月現在はアメリカからの供給が回復してない」(田村氏)。
もう1つの課題は、オゾンは濃度によって人体に危険を伴うものだということ。田村氏は「オゾンのメリット・デメリットの正しい知識の普及という土台がなければ、家庭への普及拡大は難しい」と語る。
「病原体に効果のあるオゾンが、どんな高濃度でも人体に影響がないと考えるのは、率直に言って都合のよい考え。メリットとデメリットを知った上で使うことが大前提だ」(田村氏)と率直に語る。そのため、例えば、ネット通販で一般消費者に直接販売を一気に拡大していくことには消極的である。

タムラテコ社長の田村耕三氏
“説明のできる”薬局の役割に期待
では、前述の2つの課題に対し、同社はどのように取り組んでいくのか。
1つ目の生産増強に関しては、自社の製造設備の拡充は着々と進んでおり、年内には月に5000台の供給を目指す。
パーツの獲得に関しては、これまでに取っていなかったメーカー・商社のセカンドソースを獲得し、リスクヘッジできる体制を図る。
これによって、「来年には1カ月1万台、年間12万台の供給を目指したい」(田村氏)とする。
余談にはなるが、同社には「70億円を先払いで」という海外商社からのオファーも寄せられているという。しかし、同社ではメンテナンスや品質の問題から、海外への販売は断っているという。
2つ目の課題の知識普及に関しては、同社ではさらなる研究発表を手掛けていく予定。これまでも同社がアカデミアと手掛けてきた研究発表は18あるが、今後、さらに拡充していく。現在も東海大学との研究が進行中という。
「ネガティブな結果に関しても、しっかり出していき、ネガティブな情報とポジティブな情報のバランスを取っていくことが重要」(田村氏)
さらに、同社では薬局、薬剤師の“しっかりと説明のできる”という特徴に普及への期待を示す。
「ネットで“安いから”“オゾンの発生濃度が高いから”“あの病院でも導入しているのだから良いものだろう”などど、クリックして購入いただく製品ではない。例えば、研修会などを通して、メリットとデメリットを説明いただけることを前提とすることが現時点では最も適切な手法だと考えている。研修会等を通じて取り扱いを熟知した人を介した形で、販売していく。『誰がどこで使っても安全』というところまでオゾン発生器のテクノロジー自体も追い付いていない。コストと量産の問題もある」(田村氏)
さらに、薬局には次のように期待を示す。
「薬局の可能性を非常に感じている。かかりつけ薬剤師さんの役割が多岐にわたってくると思っている。さらに病院での治療だけでなく、在宅医療が増え、在宅療養に関わる家族の方の環境整備もより重要になってくるのではないか」(田村氏)
緒に就いたばかりの「空間の感染予防策」というテーマ
具体的な製品としては濃度の変更をするタイプの「BTシリーズ」のほか、小型の「デュオ」「リオン」「ループ」などがある。
「BTシリーズ」は医療系でも使われている機種と同型のため、より専門的な知識が求められる。小型器では、クローゼットに入れて衣服の消臭などに用いられてきた。
感染予防という観点での使用シーンを考えると、医師や看護師、薬剤師、ヘルパーなど、複数の人を家に招き入れなければならない在宅療養の現場では、往診後などにオゾン発生器を一定時間に限定して使用するといった利用にニーズがあるのではないか。
また、小型器では、外出から家に帰った際に、外で着用・使用していた衣類・バッグなどをクローゼットに入れ、オゾン発生器を一定時間利用するという利用法などがあるだろう。
いずれにせよ、オゾンは有人での高濃度や密閉空間での長時間利用は適さない。また、低濃度であれば効果が下がる。家庭での利用は、一定時間、無人状態で利用し、そのあと、換気をするなどの工夫が必要になるだろう。
「どの空間であればどのぐらいの濃度分布になって、どれぐらい以上の状態で使う必要があるのかをご理解いただくことが必要」(田村氏)だ。
田村氏は今後、使用の目安を業界団体などで作っていき、周知していく必要もあるとの考えだ。一般生活者に理解のしやすい情報サイト構築も一案としてある。
オゾンに関しては、懐疑的な立場をとる薬剤師も多いのではないだろうか。
しかし、「空間の感染予防策」というテーマは、まさに緒に就いたばかりともいえる。二酸化塩素製品も含めて、今後、薬局や薬剤師が効果実証研究に主体的に参加していく方法もあるだろう。
そもそも、感染予防策に万全はない。マスクや手洗いも感染予防を万全にするものではなく、「リスクを下げる手法をいくつも取り入れることで感染の可能性を下げていく」という考え方が基本にある。空間のウイルス量を減らす面では換気という手法が一つの手法でもあり、感染者が触ったかもしれないテーブルやカウンターのこまめな消毒作業もその一つだ。ただし、感染者が触った可能性のある箇所を一定時間ごとに消毒するのは非常に労力がかかるため、医療機関では無人・高濃度でのオゾン消毒が用いられているわけだ。
在宅療養中やクローゼット利用では、オゾン発生器の家庭利用も一つの手段になっていく可能性はあるだろう。
オゾン発生器には、機械的に産生されることから、原材料がいらず、今回のようなパンデミックによる需要急増時に対応しやすいという側面もある。
「空間の感染予防策」というテーマに薬局、薬剤師はどのように関わっていくのか。業界横断的な議論の場も求められているといえる。

救急車両など官公庁を中心に導入されてきたBTシリーズ

特に安全性に配慮した家庭用シリーズもラインアップしている