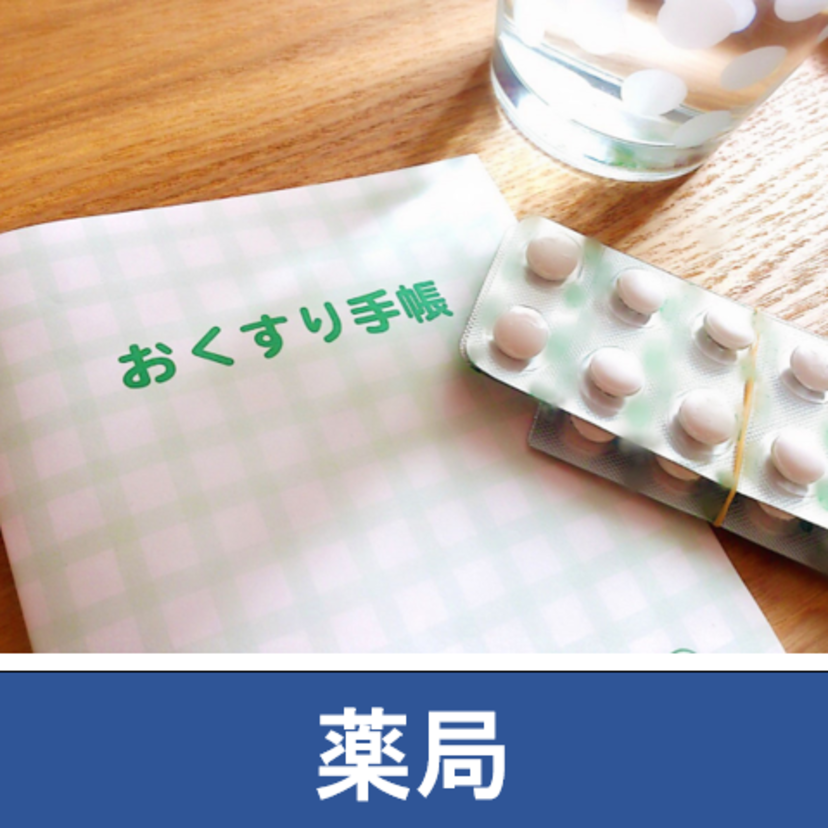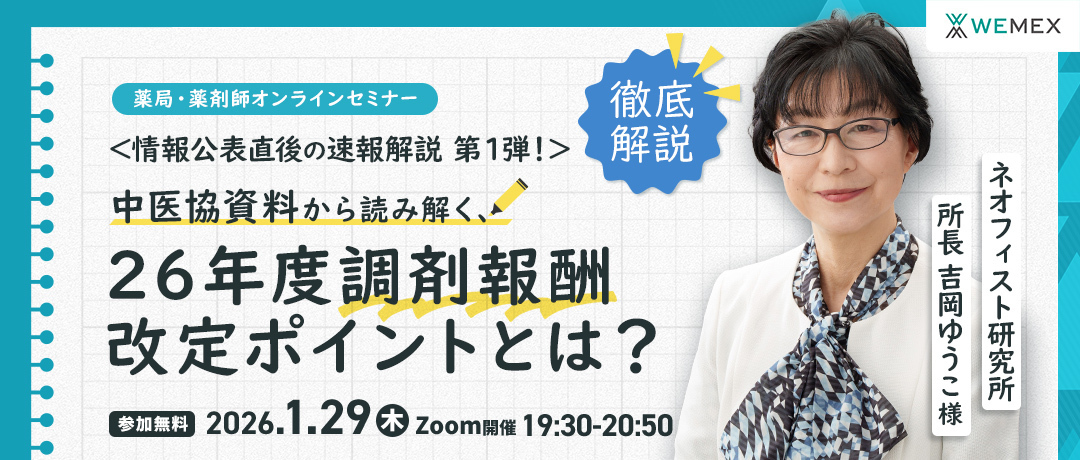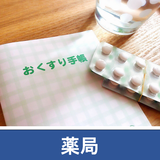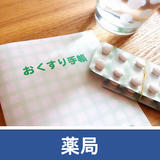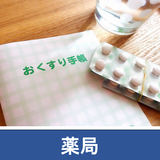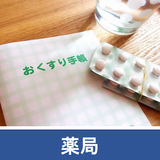昨今、カスタマーハラスメント(カスハラ:顧客等からの著しい迷惑行為)は、深刻な社会問題となっている。一方、薬剤師法第 21条においては、「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」と規定されており、薬剤師にはいわゆる「応需義務」が課されている。日薬としては、今回の調査結果を踏まえ、医療提供体制の変化や薬剤師の働き方改革といった観点から必要な検討を進めていきたい考え。
また、厚生労働省との協議をはじめとする関係機関との連携のもと、適切な対応を講じていくとしている。
調査では、薬局業務においてカスタマーハラスメント行為が発生し、調剤の対応が困難だった事例を聞いている。調査対象は、日本薬剤師会会員。調査対象期間は、令和6年3月1日~アンケート回答日までの約1年間。回答期間は令和7年2月26日(水)~3月16日(日)まで。回答数は1566件。
カスハラの状況では、カスハラに該当する行動をはたらいた者は、男性が1118件(71.4%)、年齢は70代が429件(27.4%)、60代が364件(23.2%)、50代が314件(20.1%)であり、中高年男性によるハラスメントが特に多かった。
カスハラの行動としては、大声、暴言、脅迫的言動が最も多く 974件(62.2%)、続いて、過剰、不当な要求が657件(42.0%)、不当なクレーム(調剤や販売等)が495件(31.6%)、長時間の拘束が437件(27.9%)、人格否定・屈辱的言動436件(27.8%)であった。
現場からの主な要望としては、調剤拒否の明確化と法整備が多かった。
「カスハラを正当な拒否理由として明文化してほしい」「拒否可能な具体的な事例(例:暴言、支払拒否、業務妨害等)を示してほしい」「法律や制度の見直し(薬剤師法第 21条、応需義務の例外規定等)も視野に検討してほしい」などの声があった。
また、周知・啓発の強化を求める声も多かった。「カスハラ行為に関する啓発ポスターや掲示物の作成と活用」「薬局も医療提供施設であるという認識の社会的啓発」「 厚生労働省をはじめとした関係機関との、事例の共有や対策に向けた全国的な連携の強化」など。
現場支援と実務的対応策として、カスハラ事例集や対応マニュアルの整備などを求める声もあった。
今後の対応としては、応需義務の範囲の明確化を求める考え。薬剤師は、薬剤師法第 21条により、「正当な理由」がなければ調剤を拒否できないとされているが、医師は厚労省医政局長通知により診療を拒否することができる事例が示されている。一方、薬剤師は、それがなく、結果として、暴言・威圧・金銭不払いなどへの対応に苦慮しているとの問題がある。
日薬としては、今回の調査により、カスハラの対応によって他の患者への影響や、従事者への精神的負荷が深刻化していることが明らかとなったことに加え、さらに薬局業務におけるカスハラの問題は、対人業務の範囲にとどまらず、薬局従事者の人権や安全の確保はもとより、地域の医療提供体制の維持、さらには地域社会との連携にも深く関わる、極めて重大な課題であるとし、薬剤師法第21条の法的な性質を踏まえ、どのような場合に調剤の求めに応じないことが正当化されるか否かについて整理し明確化するなど、早急に現場の実態を踏まえた実効性のある対応をすることが必要であるとの見解を示している。