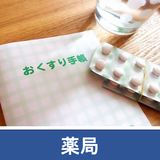「議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について)」では、「地域の状況に応じた在宅医療における薬剤提供体制に係る課題への対応」について、3段階で区分け。
(1)地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化
(2)個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応
(3)上記(1)及び(2)によっても困難な事態が生じた場合の対応
ーーである。
(1)の「地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化」では、在宅医療における医療提供体制は地域包括ケアシステムの考え方に基づき、それぞれの専門家がサービス担当者会議等で議論を行い、連携協力し、患者に専門サービスを提供することが、地域住民の最も大きな利益となるとの考えを示した上で、「行政を含めた関係者による協議により、地域の実情を踏まえた対応を検討、実施することが必要」などとし、具体的には、都道府県等のレベルで、地域における在宅患者への薬剤提供体制の実態を把握し、円滑な薬剤提供に必要な体制構築に係る課題の抽出を行い、行政、医師会や薬剤師会等の関係団体を含む有識者等の協議等により、医療計画と連動しながら、必要な方策を検討する方向を示した。
また、各地域(在宅医療の圏域や市町村単位を想定)では、都道府県等のレベルの協議結果を踏まえて、必要な薬剤提供体制やその構築・強化の方策、連携のための具体的な情報共有等について、行政、地域医師会や地域薬剤師会等を含めた関係者で協議し、体制の強化を図ることが考えられるとしている。
「在宅医療における薬剤提供体制の構築・強化のための方策(例)」としては以下を挙げた。
・地域の在宅医療における薬剤提供体制の実態の継続的な把握
・個別患者への対応で薬剤提供に課題が生じた場合の地域レベルでの対応方法をあらかじめ決定・周知
・地域における在宅医療等に関する協議等への薬局薬剤師の参加
・地域薬剤師会による在宅対応薬局の一覧(会員、非会員薬局問わず、対応可能なサービスの内容や連絡先に係る情報を含む)の公表
・薬局間連携体制の構築(医薬品の融通、輪番体制の構築等)
・地域薬剤師会による薬剤提供に係る課題に関する相談窓口の設置・公表、地域の関係者への周知
・多職種で共有すべき情報や共有方法を整理し、あらかじめ地域の関係者で共有
・多職種を対象とした研修会等の実施(行政も積極的に関与することが望ましい)
(2)の「個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応」については(1)を推進している場合であっても、地域によってはその構築・強化の過程において、個別の在宅患者への対応において薬剤提供が円滑にできないような事
態が生じてしまうことはあり得るとして設定。
そのような事態が生じた場合は、まずは個別の患者の状況を踏まえ、当該患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等によりサービス担当者会議等で協議して、関係者の連携等による対応を検討することが求められるとの考えを示した上で、調整の結果、医師が薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を指示しないことになった場合(薬局は外来調剤としての対応となる)でも、あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配置することや、緊急に必要となった場合に備えて薬剤の配送に対応するための体制を関係者間で取り決めておく必要があるとし、薬局が他の薬局と連携して対応する場合は、薬局薬剤師同士で必要な情報(在宅患者の状況や多職種の関わりの状況等)を共有しておくことが重要であるとした。
「個別の在宅患者への対応方法(例)」としては以下を挙げた。
・地域薬剤師会への情報提供・相談
・あらかじめ休日や夜間に急な対応が必要になった場合の連絡方法・対応方法を協議しておく
・(通常対応している薬局が対応できない場合)臨時的な対応が可能な薬局との連携体制の確保
・あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配置すること
・患者宅にある一般用医薬品の活用11
(3)の「上記(1)及び(2)によっても困難な事態が生じた場合の対応」については、(1)及び(2)によってほとんどの場合は薬剤提供体制を構築できるものと考えられるとした上で、しかしながら、地域によっては緊急時における薬局による臨時の処方に対応するための体制の構築・強化に時間を要することや、過疎化の進展に伴い広域での体制構築が必要になることも想定され、個別の患者の状態、状況によっては、患者宅にあらかじめ処方、調剤された薬剤を配置しておくことや一般用医薬品により臨時的に対応することが困難な場合もあると考えられるため、設定。
このような場合においては、まずは医師による診断と投薬等の対応ができないかを改めて検討した上で、当該患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等の協議により、以下の対応の実施を検討することも考えられるとした。
・ 医師の診療により、在宅療養中の患者の急な状態の変化時に投薬又は医薬品の使用を伴う処置が必要となった場合において、当該医薬品を円滑に入手することができないことが想定されることから、事前に訪問看護ステーションに当該医薬品を準備しておく。
・ 上記の「急な状態の変化」とは、在宅療養を継続する程度の状態の変化であって、医師ではなく訪問看護師であっても明確に判断できるような変化に限る。
・ 実際に医師の診療により医薬品が必要となり、他に当該医薬品を円滑に入手する手段がない場合は、訪問看護師が、当該医師の指示に基づき、事前に訪問看護ステーションに準備しておいた当該医薬品について、使用前に当該医師又は薬剤師に確認した後に、患者に投薬または当該医薬品の使用を伴う処置を行う。
ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではなく、体制が構築・強化されるまでの臨時的な対応である。在宅患者が安全な在宅医療を受けられるようにするため、また、地域の医療資源を有効に活用するためにも、そのような事態が可能な限り発生しないよう、事前に対処することが重要であり、速やかに、改善策について検討することが必要であるともした。
また、実施に当たっては、あらかじめ、行政や地域の関係団体等に当該対応を実施することを報告の上、実施状況についても定期的に共有するべきであるとした。
行政においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に対する薬剤提供体制の構築に活用すべきであるとし、医薬品の卸売販売業者による医薬品の販売先について、自らの判断で医薬品の処方・調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として販売先に含まれていないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売することは既に認められている。それに加え、上記の臨時的な対応は、輸液(体液維持剤)を対象として検討することが考えられるとした。
訪問看護ステーション内で保管する医薬品については、訪問看護ステーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションの責任・負担において保管・管理を実施する。
厚生労働省においては、上記の臨時的な対応が現行法令に基づき適切に実施されるよう、訪問看護ステーションにおける医薬品の保管方法や留意事項(輸液投与に必要な留置針や点滴ルート等の入手方法を含む)、行政や地域の関係団体等への報告方法、報告事項等について必要なことを示す方針。
併せて、各種法令、医療保険上の対応について整理し、明確化することも必要としている。
当該対応が適切に実施されるよう、都道府県等の薬事担当部局に加え、医療・介護等の関係部局にも周知し、理解いただくことも重要とした。
そのほか、とりまとめでは、「今後さらに検討が必要と考えられる事項」も記載している。
■厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001469948.pdf

【厚労省_薬局検討会】「議論のとりまとめ」公表/在宅医療における薬剤提供で
【2025.03.31配信】厚生労働省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」は3月31日、「これまでの議論のまとめ」 を公表した。「在宅医療における薬剤提供のあり方について」に関するものとなっている。 同検討会は2024年9月にも「地域における薬局・薬剤師のあり方に関するテーマで議論のとりまとめを公表している。今回は、同検討会でのとりまとめ第2弾となり、「在宅医療における薬剤提供のあり方について」に関するものとなっている。
関連する投稿
【規制改革WG】事前処方・調剤の質疑への回答公表/在宅医療における円滑な薬物治療の提供で
【2025.05.01配信】規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ(第5回)」が5月1日、開催された。その中で令和7年3月14日に開催された「第2回健康・医療・介護 WG」に関する委員・専門委員からの追加質疑・意見に対する厚生労働省の回答を公表した。
【地域における医薬品提供】岩手県薬剤師会の視点/畑澤博巳会長に聞く「“リスト化”は次のステップへの基盤づくり」
【2025.03.24配信】在宅領域など、地域への医薬品提供に課題があるのではないかとの指摘が社会から挙がっている。こうした中、地域薬剤師会や都道府県薬剤師会では地域ごとの薬局の体制について「リスト化」し地域に向けて公表している。進行する取り組みに各地の薬剤師会はどのように考えているのか。岩手県薬剤師会会長の畑澤博巳氏に聞いた。
【規制改革推進会議WG】訪看ステーションへの薬剤配置、輸液以外も再検討を/日本訪問看護財団
【2025.03.14配信】規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ」が3月14日に開かれた。
【厚労省_中医協】訪問看護への「指導要領」改定/不適切な請求事案受け
【2025.03.12配信】厚生労働省は3月12日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、訪問看護ステーションの指導要領の改定を了承した。昨今の不適切な請求事案の報道を受けた対応。
【専門医療機関連携薬局】「HIV」「小児(疾病)」追加を検討へ/厚労省検討会
【2024.12.16配信】厚生労働省は、認定薬局の1つである「専門医療機関連携薬局」について、現行の「がん」に加え、「HIV」、「小児(疾病)」について検討することとし、関係者へのヒアリングを実施していく方針を示した。「第11回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」で示したもの。
最新の投稿
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。
【答申】調剤管理料「2区分」化では「7日以下」では増点の結果
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤管理料(内服薬)では、「長期処方」(28日分以上)以外は10点となる。長期処方は60点。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤基本料「1」と「3ーハ」で2点増点する。
【日本保険薬局協会】門前薬局“減算”、「到底受け入れられない」/三木田会長
【2026.02.12配信】日本保険薬局協会は2月12日に定例会見を開いた。この中で会長の三木田慎也氏は、次期調剤報酬改定の項目、いわゆる“短冊”について触れ、「門前薬局等立地依存減算」について「到底、受け入れらない」と強調した。「患者さんの動向、患者の志向、いわゆるマーケットインの発想が調剤報酬をつくる側に全く意識されていない結果」と述べた。