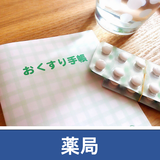厚労省は現在、市販薬の販売方法見直しを含めた薬機法改正を予定している。
1月10日には、厚生科学審議会「医薬品医療機器制度部会」の報告書を公表。今月24日にも招集されるとみられる通常国会に薬機法改正案を提出する予定だ。
厚労省は制度部会に入る前の検討会で濫用のおそれのある医薬品に関しては、「顧客の手の届かない場所」での陳列などが必要としたとりまとめを行っており、これにより専門家の関与を担保しようとの意向をみせていた。こうした方針が制度部会での「報告書」では「手の届かない場所」への陳列以外に「継続的な専門家の配置」を選択肢に加えた。この提案はドラッグストア業界から出てきたものであり、ドラッグストア業界の意向を反映したという指摘は、はずれたものではない。
しかし、「継続的な専門家の配置」はあくまで選択肢であり、当初から目指した「専門家の関与」を担保するとの目的を変えたものではない。
今回の濫用のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化は、いうまでもなく、昨今の市販薬の過量服用(いわゆるオーバードーズ)の社会問題化を受けての対応である。過量服薬は背景として孤立の問題などが含まれていると指摘されており、一面的な方策で解決するものではない。そのため、地域に根差した薬局や店舗販売業は、販売に際するルール遵守だけでなく、地域住民の状況により、地域の必要な機関につなげることが求められる。これは、地域のネットワークがなければできないことだ。
また、地域包括ケアの必要性が高まる中、最近、地域を“頭越し”したオンライン診療についての問題点が指摘されることも出てきた。肥満症治療薬をオンライン診療で処方された患者が体調不良になった際、その対応にあたるのは地域の医療リソースになることの問題点の指摘だ。同じことは市販薬にもいえる。医薬品はベネフィットと表裏一体でリスクを持っているものであり、地域ぐるみの啓発やネットワークが欠かせない。無論、医薬品のこうした特性は何も最近の変化ではないが、生産年齢人口の急速な減少の中、地域のリソースは細ってきていることは事実だ。こうした中で、もしかしたら向けられる“目”が減っているかもしれない若者に誰が注意を配るのか。これは、1つとして地域の薬局や店舗販売業であってもいいはずだ。
同様に「とりまとめ」から「報告書」の過程で、変わった事項の1つが購入者の「記録」と「保管」だ。 報告書では購入者の氏名・年齢などの機微な個人情報については確認はするものの、記録し保管することの義務化までは見送った。ネット事業者からは自らのデジタルの優位性を訴え、リアル店舗の施策が手ぬるく優遇されているとの指摘も聞こえてくる。ただ、ネット事業者といえども、他社の記録を共有しているわけではなく、ネット事業者が記録を保管したとしても、手のひらのスマホの中で別の事業者から購入できる現状では「買い回り」に対して実効性はどこまであるのだろうかという疑問がある。もしもマイナンバーカード活用で買い回り防止効果を担保するのであれば、OTC医薬品の購入履歴、少なくとも濫用のおそれのある医薬品の購入履歴情報を他社間でも共有できるような仕組み構築が必要となる。現状ではマイナンバーカードは保険診療情報や健診情報しか蓄積されない。「マイナンバーカードを活用すればネット販売でも濫用防止ができる」といえる状況は現在はない。
ドラッグストア業界にしろ、ネット事業者にしろ、「現状の販売が毀損される」というビジネス起点の主張の応酬のように映る。濫用のおそれのある医薬品は、荒っぽい表現をすれば“稼ぎ頭”である総合感冒薬が多く含まれるからだ。求められるのは濫用にはからずも陥ってしまうような若者をどう減らすかであり、専門家の活用を含めた“人”というリソースを使おうという視点は理にかなっているのではないか。ネット事業者にも、リアルタイムのオンライン通話で“対話”を求めるとした見直し案も“人”の活用という根本は同じだ。
オンライン、IT、DXは活用すべきツールである。しかし、地域の“人”が生かされ生きるために活用すべきではないか。地域のかかりつけ薬局がこれまで以上に「時には薬局で相談」「時にはオンラインでも販売」と便利なツールをそれぞれ地域住民、購入者に提供していくことも選択肢になるのではないか。ネットモールでの出店社もかかりつけ薬局という出店社が増える可能性もゼロではないのではないか。もっといえば、ネット事業者の医薬品購入情報も、いざという時にはかかりつけ薬局と連携して地域住民を守っていくという概念もほしい。
手段と目的を取り違えず、生産年齢人口急減という我が国の現状下の「地方創生」のあり方を含めた大局観で、今後の国会審議が進むことを期待したい。
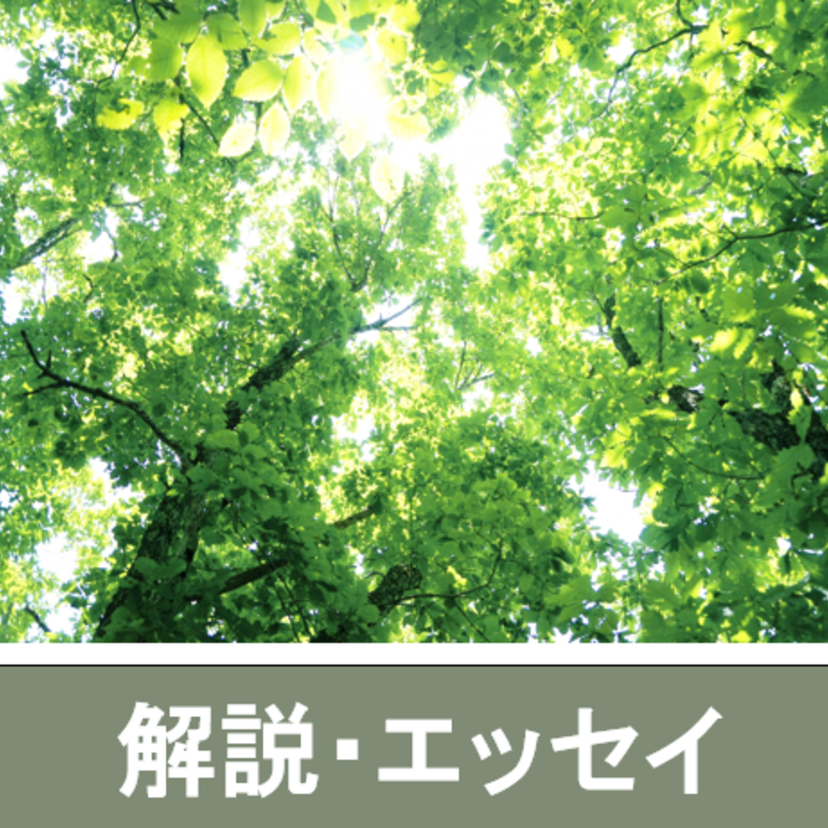
【社説】市販薬の濫用防止策こそ「地方創生」だ
【2025.01.15配信】市販薬の濫用対策の見直しをめぐって、ドラッグストア業界やネット事業者関係者からの“経営視点”での議論の応酬が目に付く。その根底には現状のビジネスの継続に支障となるとの思惑がのぞく。しかし、濫用問題は孤立の問題や相談先の確保、もっと言えば人的なリソースなど、地域でどう若者など守るべき人を守っていくのか、という点に収斂される。地域の持続性をどう確保するのかという、すなわち、石破茂首相が就任以来、掲げてきた「地方創生」にも関わる問題だ。
関連する投稿
【厚労省_令和6年度医薬品販売制度実態把握調査】“濫用薬”販売方法で改善みられる
【2025.08.26配信】厚生労働省は8月22日、「令和6年度医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表した。同調査は、薬局・店舗販売業の許可を得た店舗が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調べたもの。令和6年度の調査は、前年度に引き続き一般用医薬品のインターネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めた調査を実施した。
【2025.05.16配信】一般社団法人新経済連盟(所在地:東京都港区、代表理事:三木谷浩史氏)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」が5月15日付けで成立したことを受け、代表理事のコメントを発表した。新経済連盟はこれまでも濫用のおそれのある医薬品の販売規制について、「市販薬のネット販売にビデオ通話を義務付ける厚生労働省の案の撤回」を求めており、今後の下位法令等が規定においても引き続き要望活動を展開する構え。
【“濫用薬”】デキストロメトルファン、「直ちに指定を」/嶋根研究班
【2025.04.15配信】国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所は、「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究(2024年)」の報告書をホームページに掲載した。
【市販薬の乱用】中学生にも/過去1年間の経験率は1.8%、55人に1人/嶋根研究班
【2025.04.15配信】国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所は、「飲酒・喫煙・薬物乱用についての全国中学生意識・実態調査(2024年)」の報告書をホームページに掲載した。
【衆議院_改正薬機法審議】濱地雅一議員、調剤基本料について「大規模な調剤薬局等について点数を下げていくようなこと、やめていただきたい」
【2025.04.07配信】今改正薬機法における初となる国会審議が4月4日、衆議院厚生労働委員会で行われた。この中で濱地雅一議員(公明党)が質疑に立った。
最新の投稿
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【コミュニティファーマシー協会】ドイツ薬局視察旅行の参加者を募集
【2026.02.22配信】 日本コミュニティファーマシー協会はドイツの薬局を視察する旅行参加者を募集する。 旅行期間は2026年6月8日(月)〜6月13日(土)まで4泊6日。申し込み締切は、2026年3月5日(木)。
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。