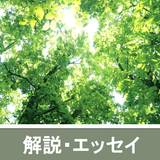報告書では濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る見解案をまとめている。
そこでは、デキストロメトルファンとジフェンヒドラミンについて、直ちに「監用等のおそれのある医薬品」として指定すべきであるとした。数多くの市販薬症例、意図的摂取による中毒情報の報告があり、乱用に伴う健康被害を文献上でも確認できた。
また、カフェインについては、何らかの販売規制が必要とした。依存症としての症例報告は限られているが、意図的摂取による中毒情報の報告や、心竜図異常の出現などが報告されている。ただし、カフェインを含有する市販薬の製品数は膨大であり、他の成分と同様に一律に「濫用等のおそれのある医薬品」として指定するのは現実的ではないとの見解も表明。乱用される製品は一部に偏っていることから、当該製品を製造・販売している製薬会社に注意喚起や乱用防止策を求めることは必要とした。
加えて、アリルインプロピルアセチル尿素については、今後、基礎研究を通じて、同成分の依存性などの健康影響を評価していく追加試験が必要となるとした。同成分は国際的に医薬品として使われておらず、乱用に伴う健康影響に関する情報が乏しいものの、国内の依存症専門医療機関からは一定数の症例が報告されているとした。すでに「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されているプロモバレリル尿素も含めて、医薬品として承認の妥当性についても検討していくことが必要としている。
この調査は令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金事業。研究代表者は、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部の嶋根卓也氏。
「濫用等のおそれのある医薬品」の指定成分の範囲の見直しを検討することは喫緊の課題であるとして、同研究では、依存症専門医療機関等における市販薬の乱用・依存の実態を把握するとともに、各成分の依存性や乱用につながる精神作用性などに関する情報を収集・整理し、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲に関する見解案の作成を目的とした。