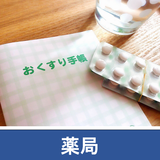調査期間は2023年10月24日から2024年3月15日まで。病院の敷地内薬局として、220薬局の回答を得た。
主な結果概要は以下の通り(結果の実績値については、回答時点の直近3か月における1か月当たりの平均値に基づく)。
「病院敷地内薬局の体制」については、処方箋応需枚数は平均2,744枚/月(薬局平均※:1,661枚)、1日当たりの平均勤務薬剤師数は5.7人(薬局平均 :2.7人)であった。
「高度な薬学管理機能について」は、医療用医薬品の備蓄品目数の平均は1,667品目(薬局平均:1,150品目)であった。
病院敷地内薬局の半数以上が、がんや在宅医療の分野に注力していた。
病院敷地内薬局における認定薬局等の割合は、健康サポート薬局が8.2%(薬局平均:5.1%) 、地域連携薬局が35.5% (薬局平均:6.8%) 、専門医療機関連携薬局が12.3%(薬局平均:0.33%)であった。専門医療機関連携薬局は約1割が病院敷地内薬局であった。
「かかりつけ機能・地域との連携体制について」は、病院敷地内薬局の90%以上が自薬局単独で夜間・休日に調剤や相談に対応する体制を整備しており、半数以上の薬局において、月に1回以上時間外等加算の算定実績があった。
在宅患者への対応実績がある病院敷地内薬局は85%であり、1か月当たりの算定実績は平均43.2回、うち80%の病院敷地内薬局では在宅関連の加算の算定実績があった。
病院敷地内薬局の51.8%に無菌調剤の対応実績があり、他局との共同利用に対応している薬局が15%あった。
病院敷地内薬局の84.1%に麻薬の調剤実績があり、その平均は32.5回/月であった。
病院敷地内薬局の31.4%が地域ケア会議、 50.9%がサービス担当者会議へ参加していた。
「敷地内医療機関との連携体制について」は、敷地内薬局において平均51.7施設の処方箋を受け取っていたが、処方箋集中率は93.1%と高かった。
敷地内薬局において、医療機関の求めで医療機関に情報提供した実績は平均65.5回/月、うち、敷地内の医療機関からの求めによるものは13.0回/月であった。
敷地内薬局の34.1%が地域の他薬局も含めて同一敷地の医療機関とプロトコールに基づく問い合わせの簡素化に関する協議を行っており、敷地内薬局のみで協議している場合も含めると、敷地内薬局の50.4%が、同一敷地内の医療機関と協議していた。
「薬局の開設について」は、回答のあった敷地内薬局のうち、同一敷地内の病院の開設者としては、「医療法人」が最も多かった。
公募型プロポーザルが「あった」と回答したのは78薬局あり、「なかった」と回答したのは59薬局、無回答は83薬局であった。
「あった」と回答した薬局における公募要件の内容については、「県内での薬局の運営実績があること」が最も多かった。
こうした調査結果のまとめとして、事務局は、いわゆる病院敷地内薬局には24時間対応や麻薬の調剤対応など地域に貢献するような業務が実施されているものもあり、また、敷地内の医療機関のみならず、地域の医療機関・薬局との連携がなされている場合もあったと記述。
その上で、すべての敷地内薬局において上記のような対応がなされているものではないが、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」とりまとめにも記載されているとおり、門前薬局など敷地内薬局以外の薬局も同じ状況であると考えられることから、立地によらず機能を発揮していくことが重要であるとの考え方を否定するものでもないと考えられるとした。
また、一方で、検討会の「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)」では、「「患者のための薬局ビジョン」に示された方向性については、引き続き推進していくことが重要である一方で、薬局を取り巻く環境にも変化が生じていることから、本とりまとめやこれまでの厚生労働省の有識者検討会等の結論も踏まえつつ、今後の薬局の目指すべき姿やそこに向かうための方策等について、引き続き検討していくべきである」としており、必要に応じ、敷地内薬局も含め、今後の地域における薬局のあり方について、引き続き検討することとするーーと総括している。