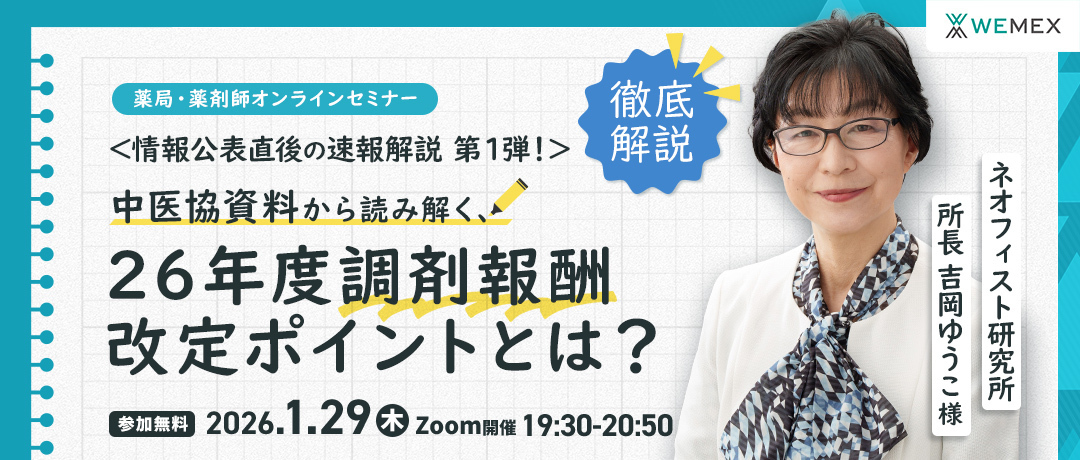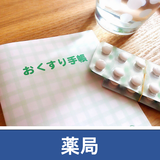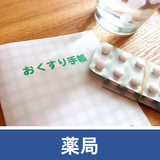注目されてきた薬価の中間年改定については以下のように記載した。
イ)薬価改定
薬剤使用量の増加や新規医薬品の保険収載により、薬剤費総額は年2%程度増加している。高齢化の進展に伴い、更なる薬剤費の増加が見込まれる中、市場実勢価格を薬価に適切に反映させるため、毎年薬価改定を着実に実施していかなければならない。
近年の薬価制度改革は、革新的な先発品(新薬)と、特許期間が切れ、後発医薬品が収載されている長期収載品との間で薬価上の評価等に関するメリハリ付けをより一層進展させており、こうした制度の下で薬価改定を実施することは、製薬企業にとって、革新的な新薬を創出するインセンティブにつながる一方、長期収載品に依存したような経営の在り方の見直しを促すことにもつながる。
同時に、貴重な医療保険財源をメリハリのある形で配分することにより、現役世代を含む国民の負担軽減につながり、医療保険制度の持続可能性確保にも資することになる。
a)薬価改定の経緯
薬価改定は、基本的には、市場で決定される実勢価格に応じて既存医薬品の価格を引き下げる仕組みとなっているため、「改定率」としては例年マイナスとなるが、薬剤使用量の増加や新規医薬品の保険収載により、医療保険財政で支えられている薬剤費総額自体は一貫して拡大傾向にあることに加えて、今後の高齢化の進展に伴い、更なる薬剤費の増加も見込まれる状況である。
b)対象品目の考え方
これまでの「診療報酬改定のない年の薬価改定」では、平均乖離率に基づく機械的な計算で改定対象品目を限定してきた。しかしながら、新薬創出等加算がある中では、実質的な改定対象は長期収載品等に限られることを踏まえれば、乖離率に基づき改定対象品目を限定することについては、国民負担軽減等の観点からも、長期収載品依存からの脱却等の観点からも、政策的合理性が乏しいと考えられる。
令和7年度(2025 年度)薬価改定については、原則全ての医薬品を対象にして、市場実勢価格に合わせた改定を実施すべきである。仮に、一定の品目を除外するとしても、安定供給確保に資する医薬品や真に革新的な医薬品など、政策的対応の合理性があるものに限定すべきである。
c)適用ルール
直近の「診療報酬改定のない年の薬価改定」である令和5年度(2023年度)改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特例的な対応を行う一方で、新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルール等については適用されず、また、追加承認項目等の加算などほかの多くのルールについても適用しないこととされた。
毎年薬価改定が行われる中で、このように2年に1度しか適用されないルールがあるのは合理的な説明が困難である。例えば、「新薬創出等加算の累積額控除」や「長期収載品の薬価改定」などについては、革新性を失った医薬品の評価を適切に見直すルールであり、現役世代を含む国民負担軽減の観点や、収載のタイミングによる不公平の解消の観点から、令和7年度(2025 年度)改定では、既収載品の算定ルールについて、全て適用すべきである。
d)調整幅の在り方
我が国の薬価制度は、現状、「薬価」と薬局・医療機関が医薬品を購入する際に実際に支払う「納入価」との間の乖離、すなわち薬価差益の解消を図ることを基本としつつ、流通コスト等を勘案して「調整幅」の乖離を認めている。調整幅(2%)については、平成 12 年(2000 年)以来見直しが行われていないが、その後の流通市場の変化等を踏まえ、現役世代の保険料負担軽減を含め、国民皆保険制度の持続可能性を確保する観点から、その制度趣旨に遡って、価格や薬剤の種類によらず調整幅を一律に2%としていることの妥当性をはじめ、その在り方の見直しを検討すべき時期に来ていると考えられる。