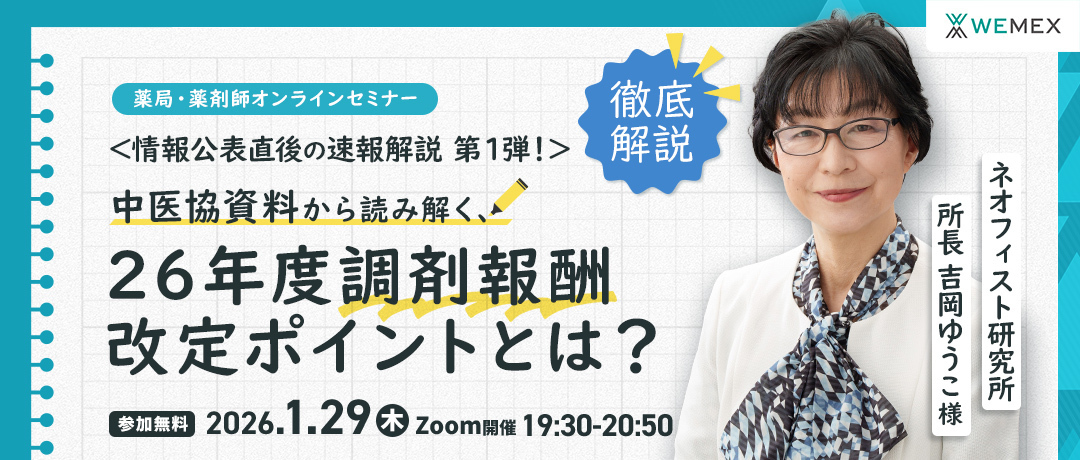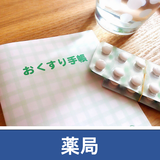地域連携薬局は名称見直しも/健康サポート薬局は法制化
とりまとめでは、まず「地域における薬局の役割・機能」を整理。医療資源が限られている中、すべての機能を個々の薬局が持つことは困難である場合もあるとして、少なくとも薬局間の連携等により地域・拠点で確保すべきものはどのようなものであるか、議論してきたもの。
地域・拠点で確保すべき機能について列挙した上で、特に、夜間・休日対応や在宅対応については、連携が重要としている。行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した上で必要な体制を構築することが重要であるともした。
その上で、地域連携薬局については、在宅対応の実施に加え地域の薬局が対応できない場合にそれらの薬局と連携して対応することなども明記し、地域連携薬局がこれらの機能を担い、地域において求められる役割を果たすことができるよう、制度(要件、名称等)についても見直す必要があるとした。
加えて、健康サポート薬局については、機能や取組について、その質を確保していくための仕組み(認定制度など)を法令に規定することが必要であるとした。
とりまとめ全文
とりまとめ全文は以下の通り(各注釈を除く)。
■これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)
○地域における薬局・薬剤師のあり方
⚫ 薬局・薬剤師については、平成 27 年に厚生労働省が作成した「患者のための薬局ビジョン」において、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の推進、対物中心の業務から対人中心の業務へのシフトを図り、対人業務の強化や医療機関等との地域連携等を基本的な考えとして示し、その実現を目指し様々な施策が推進されてきた。
⚫ このような取組の中、健康サポート薬局(平成 28 年4月)や認定薬局(令和3年8月)など、患者が自身に適した機能を有する薬局を主体的に選択できるよう、一定の機能を有する薬局について表示又は名称を使用できる制度が導入されている。
⚫ しかしながら、健康サポート薬局や認定薬局についてはあまり認知されておらず、利用者にどのようなメリットがあるのか不明確であり、また、薬局側に名称を使用(表示)できる以外のインセンティブがなく、十分に活用されていない状況にあると考えられる。
⚫ 特に、健康サポート薬局、地域連携薬局については、在宅対応を含むかかりつけ薬剤師・薬局としての機能を持つことを基準の一部とされているなど共通している部分もあり、地域の中での位置付けや違いがわかりにくいとの指摘もなされている。
⚫ 地域において求められる薬剤師サービスは、医薬品の供給拠点、在宅対応、夜間・休日の対応、健康サポート(セルフケア・セルフメディケーションの啓発・推進を含む)、新興感染症・災害等の有事対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生等、多岐に渡っており、これらの機能を薬局がどのように担うのか検討が必要である。
⚫ これらの薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難であり、地域全体で効果的・効率的に必要な薬剤師サービスを提供していく観点から、個々の薬局がかかりつけ薬剤師・薬局としての役割を果たす前提で、地域の薬局が連携して対応する仕組みを構築することが重要であると指摘されている。
⚫ このような状況を踏まえ、本検討会では、地域における薬局の役割・機能のあり方を整理し、健康サポート薬局、認定薬局について、患者等が利用する、又は医療関係者が連携する薬局を選定する際に有用となる制度となるよう、その機能や地域における役割・位置付けを改めて整理・明確化するための検討を行った。
○地域における薬局の役割・機能
⚫ 薬剤師法第1条では、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と規定されている。
⚫ 薬局については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)第2条第 12 号において、「「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。
⚫ また、医療法において、薬局は病院や診療所と同様「医療提供施設」とされ、地域医療における法律上の責務が課されており、地域医療を担う一員としての役割を果たすことが求められている。
⚫ さらに薬局には、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する役割も求められている。
⚫ このため、薬局は薬剤師がその任務を十分に遂行できるよう、地域の公共的な施設として必要な役割を果たすことが求められる。
⚫ 具体的には、薬局は、地域の医療・健康における公共的な活動方針を理解の上、地域において、当該薬局の薬剤師の専門性を発揮すること等により、以下に示す役割を果たすことが求められている。
・ 医療関係者等との連携による地域の住民の薬物治療(外来・在宅医療)の提供
・ 医薬品の適正使用の推進など公衆衛生の向上・増進
・ 薬剤師の資質向上2
・ セルフケア・セルフメディケーションの啓発・推進など、地域住民の健康維持・増進の取組等の支援 等
⚫ さらに近年では新型コロナウイルス感染症時の自宅・宿泊療養者の健康観察の協力や震災時の医薬品提供に係る対応等、有事への対応を行うなど、地域における公衆衛生の維持・向上のための取組も求められている。
⚫ 以上の役割を果たすため、薬局においては、調剤・服薬指導及びフォローアップ等の外来患者への対応に係る機能や訪問薬剤管理指導等の在宅患者への対応に係る機能といった医療提供機能、OTC 医薬品等の販売や健康相談など、未病の方を含む地域住民に向けた対応に係る健康サポート機能を持つことが求められており、薬局薬剤師はこれらに適切に対応する必要がある。
⚫ 一方で、医療資源が限られている中、これらのすべての機能を個々の薬局が持つことは困難である場合もあり、効果的・効率的な体制の構築も必要な場合もあると考えられ、地域での医療資源を有効に活用する観点から、薬局間の連携等により地域・拠点で必要な機能を確保していくことも必要である。
⚫ 本検討会では、まず、薬局に必要な機能のうち、個々の薬局に必要なもの、本来は個々の薬局で持っていることが望ましいが、少なくとも薬局間の連携等により地域・拠点で確保すべきものはどのようなものであるか、議論を行った。
⚫ 個々の薬局に必要な機能は、迅速な対応や地域の状況に応じた対応を行う観点から、どの薬局を利用した場合でも利用者にサービスとして提供されるべきものであり、具体的には、
・ 外来患者への調剤・服薬指導等
・ 在宅対応(他の薬局との連携、関係機関との連絡調整を含む)4
・ 入院・退院・在宅の移行において円滑に薬剤提供ができるよう医療機関(歯科医療機関を含む。以下同じ)・他の薬局等と連携すること
・ 地域住民への OTC 医薬品等に関する相談対応・販売、受診勧奨等が求められる。
⚫ 地域・拠点で確保すべき機能について、①未病の方を含む地域住民を対象としたもの、②主に外来患者を対象としたもの、③主に在宅患者を対象としたもの、④外来、在宅患者を対象としたもの、⑤その他に分類すると、以下のとおりである。
① 未病の方を含む地域住民を対象としたもの
・ 健康・介護相談等(関係機関との連携)
② 主に外来患者を対象としたもの
・ 夜間・休日対応
③ 主に在宅患者を対象としたもの
・ 在宅対応(臨時の訪問対応、ターミナルケアを受ける患者への対応)8
④ 外来、在宅患者を対象としたもの
・ 無菌製剤処理
・ 医療用麻薬調剤
・ 高度薬学管理
⑤ その他、地域全体を対象とした
・ 災害・新興感染症発生時の対応・支援
⚫ これらの機能については、地域における拠点となる薬局による対応を含む薬局間連携による対応や医療機関等の関係機関と必要な情報の共有を含めた連携体制の構築など、その機能ごとに地域の状況に応じた体制を構築することが考えられ、地域の実情に応じ、計画性をもって、実効性のある体制を構築していく必要がある。
⚫ その他、薬剤師の資質(薬学的能力、臨床能力、医療倫理等)の向上のための薬剤師の教育・研修等の取組については、個々の薬局の機能としても、地域・拠点で確保すべき機能としても必要である。
⚫ 特に、夜間・休日対応や在宅対応については、個々の薬局で対応するとしても、輪番体制への参加協力や対応可能な薬局との連携、医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等との連携、患者や医薬品等に係る情報の共有が必要であり、協力、連携、情報共有のもと、地域において必要な体制を確保することが重要である。こうした連携に際し、薬局薬剤師は、日々の業務や多職種を対象とした勉強会への参加等を通じ、医師、看護師等をはじめ、これらの機関の関係者と積極的に関係を構築しておくことが求められる。
⚫ 地域ごとに薬局の状況は大きく異なっていると考えられることから、地域・拠点で確保すべき機能について、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した上で必要な体制を構築することが重要である。特に、夜間・休日対応や在宅対応などの機能については、今後、地域における医療計画等を踏まえ、薬局を含む関係機関が連携して地域の実情に応じた体制構築を進めていく必要がある。また、構築した体制については適宜見直すとともに、地域の住民、関係者に必要な情報を公表する等により、共有していくべきである。
⚫ 厚生労働省は、地域における必要な体制の構築の推進に向け、課題を整理し、対応を検討するなど、必要な対応を実施すべきである。その際、薬局・薬剤師を取り巻く環境は時代とともに変化していくことから、時代の変化や状況を踏まえて、適宜見直すことも重要である。
⚫ なお、検討会においては、構成員から、個々の薬局に必要な機能について、最低限必要な機能に絞ったほうがよいという意見があった一方、個々の薬局で求められる役割を果たすことができないこともあるかもしれないが、地域の実態に応じ求められる役割を検討して必要な体制を構築すべきものであり、まずは広く捉えるべきという意見もあった。
○地域連携薬局の役割・機能
⚫ 地域連携薬局は、入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応する薬局であり、地域の中で、医療機関、他の薬局と連携し、夜間・休日対応や在宅対応を実施することが求められている。
⚫ 上述のとおり、在宅対応や夜間・休日等の対応については、地域において、行政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した上で、輪番制や薬局間連携により対応する体制を確実に構築する必要があるため、地域の中でこれらの機能を担う薬局が必要である。このような薬局の確保を推進し、また、地域において対応可能な薬局を明確にするため、地域において、夜間・休日対応や在宅対応を実施するなど、これらの機能を担う薬局として地域連携薬局を位置付けるべきである。
⚫ 具体的には、地域連携薬局は、個々の薬局に必要な機能に加え、以下の機能を有する必要があると考える。
・ 在宅対応の実施に加え、地域の薬局が対応できない場合に、それらの薬局と連携して対応(臨時対応含む。)すること
・ 医療用の麻薬調剤の対応
・ ターミナルケアを受ける患者の対応10や無菌製剤処理
・ 医療機関等との情報共有
⚫ これらの機能のうち、ターミナルケアを受ける患者の対応や無菌製剤処理については、すべての地域連携薬局に必須とする機能ではないが、地域の実状を踏まえ必要な体制を確保することが重要であり、地域においてはターミナルケアを受ける患者の対応や無菌製剤処理の機能を有する地域連携薬局が確保されることが望まれる。
⚫ 地域連携薬局に求められる機能については、薬局間だけではなく地域の医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等と連携することが前提となるため、地域連携薬局の薬剤師はこれらの関係機関の関係者と日頃から関係構築に努めることが重要である。
⚫ また、地域連携薬局に求められる機能については、地域全体で体制を構築する必要があるものであり、地域連携薬局にすべてを任せるのではなく、地域の実状に対応するための体制の構築に当たっては地域連携薬局以外の薬局も積極的に協力することが求められる。
⚫ さらに、地域連携薬局がこれらの機能を担い、地域において求められる役割を果たすことができるよう、制度(要件、名称等)についても見直す必要がある。
○健康サポート薬局の役割・機能
⚫ 健康サポート機能については、「患者のための薬局ビジョン」において、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する機能であり、患者等のニーズに応じて強化・充実すべき機能のひとつであるとされている。特に健康サポート薬局では、かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的な機能に加え、健康サポート機能の発揮が期待されていることが示されている。
⚫ 「患者のための薬局ビジョン」においては、健康サポート薬局では、以下のような取組を積極的に実施することとされている。
・ 地域住民による主体的な健康維持・増進を積極的に支援するため、医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行う
・ 健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介する
・ 地域の薬局の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援等を実施する
⚫ このように健康サポート薬局は、個々の薬局に必要な機能(かかりつけ薬局としての機能を含む。)※を前提に、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する機能を有する薬局であり、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携して、セルフケア・セルフメディケーションに係る相談対応や健康サポート薬局研修修了薬剤師による学校薬剤師の活動・支援などを含め、地域住民の健康の維持・増進に関する課題を発掘し、関係機関等と連携しながら創意工夫して当該課題の解決に導くなど、地域住民の相談役のひとつとしての役割を果たすことが期待されている。
※ 「地域における薬局の役割・機能について」、「個々の薬局に求められる機能」については、「○地域における薬局の役割・機能(2 ページ」において示されている役割、機能を参照。
⚫ しかしながら、健康サポート薬局については、地域住民にとって利用するメリットが不明確で、十分に認知されておらず、十分に活用されていない状況にあると考えられる。このため、求められる役割と必要な機能を改めて明確化し、その上で利用するメリットについて周知を図っていくことが必要である。
⚫ 健康サポート薬局の機能を明確化するに当たり、例えば、以下のようなことについて、明示していくことが考えられる。
・ 「関係機関や多職種との連携による健康・介護相談対応」、「介護用品、特別用途食品の販売」、「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」、「セルフケア
・セルフメディケーションの啓発・推進」に対応するに当たっては、処方箋のない方も含め、地域住民の健康の保持増進等に関する相談を幅広く受け入れ、自治体等と連携しながら必要な機関につなげられる機能が必要となること
・ 上記対応については、薬局だけで解決できないものも含まれると考えられることから、地域の自治体を含む関係機関と連携しながら、適切な機関につないでいくことが求められること
⚫ また、健康サポート薬局がその機能を発揮し、求められる役割を果たすためには、例えば、当該薬局は以下のような対応を実施することが必要である。
・ 「健康・介護相談対応等」について、地域の行政や地域包括支援センター、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等の関係機関、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体と連携して対応すること
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」について、積極的に地域の行政や薬局、関係機関と連携すること
⚫ これらの対応について、健康サポート薬局が提供するサービスとして、一般の薬局が提供する以上に高度なものを提供する場合は、その質や安全の確保に努めるべきであり、受診勧奨も含め適切に実施できるよう適切な連携体制を構築する必要がある。
⚫ 現行の健康サポート薬局については、薬局開設者による届出によって、その表示を可能とする制度であり、健康サポートに関する取組状況等の基準を満たしているかどうかについて薬局開設者が適合していることを明らかにする書類を提出し、基準を満たしていることが形式上確認されれば健康サポート薬局と表示することが可能となるものである。
⚫ このため、健康サポート薬局の機能や健康サポートに関する取組について、その質を確保していくための仕組み(認定制度など)を法令に規定することが必要である。
⚫ 厚生労働省や都道府県等の行政機関は、健康サポート薬局の役割・機能を明示し、住民、関係機関、関係団体等に周知・広報を図ることが必要である。加えて、健康サポート薬局がこれまで以上に市区町村等による健康増進・介護予防関連事業等への参画を推進していくことや、地域における健康相談対応等を幅広く実施し、行政と連携しながら必要な機関につなげられる薬局であることについて、さらに周知等を図ることが必要である。
⚫ また、行政機関による対応だけで地域住民へ効果的に周知することは困難であり、健康サポート薬局自ら、及び地域の薬剤師会等と連携を取りながら、積極的に情報を発信していくべきである。
⚫ 健康サポート薬局の役割・機能の周知・広報においては、地域の住民を対象とする場合と医療関係者、関係機関を対象とする場合を分ける等、より効果的に実施できるよう必要な対応を検討すべきである。
⚫ 健康サポート薬局の役割・機能の見える化を図ること、利用するメリットを具体的に示すことなど、住民、患者、関係機関等にとってわかりやすく、実効性のある制度となるよう、必要な対応を実施するべきである。
⚫ 併せて、健康サポート薬局について、地域住民が必要な機能を有する薬局を主体的に選択できるよう、名称独占について法令上明確化することが必要である。
⚫ その他、検討会では、健康サポート薬局について、以下のような意見があった。
・ 健康サポート薬局について、通常の薬局との差異が明確ではない
・ 健康サポート薬局及び地域連携薬局の要件の整理は必要である
・ 健康サポート薬局の要件を見直す際には、在宅対応など地域連携薬局が中心的に担う機能については緩和してもよいのではないかといった意見があった一方で、地域住民にとって高度な機能を有した薬局があることはよいことであり、現在の健康サポート薬局の基準を緩和せずに残してもよいのではないかとの意見があり、要件についてはさらなる検討が必要である。
・ 薬局機能情報提供制度により薬局の情報を公表しているシステム(医療情報ネット)において、健康サポート薬局や地域連携薬局を上位の項目として検索、表示できるようにしてはどうか
・ 健康サポートの取組は、健康サポート薬局以外の薬局でも薬剤師が目指すべき方向性であると考えられるため、関係団体として、薬局として将来的にどのような姿を目指すべきか示すことが必要ではないか
・ 健康サポート機能について、行政に示されて実施するのではなく、関係団体や薬局自らが明確に示していくべきではないか・ 地域の行政が健康サポート薬局を利活用するために、地域行政等が健康サポート薬局の機能をしっかり理解することが重要であり、都道府県や市町村の健康関係部局や地域の関係機関、関係団体に対して健康サポート薬局の制度の周知を図るべきではないか
・ インセンティブがないことは課題であり、国民のためにも制度として成り立つようにする必要があるのではないか
⚫ 厚生労働省、日本薬剤師会等の関係団体においては、これらの意見も踏まえ、引き続き必要な対応について検討していくべきである。
⚫ なお、制度の見直し後、健康サポート薬局の行う取組の実施状況や活用状況等を踏まえ、地域において求められている役割を果たしているのか等について検証を行い、必要に応じ制度を見直すことも必要である。
○おわりに
⚫ 本検討会では、地域における薬局の役割・機能について整理した上で、それを踏まえて地域連携薬局、健康サポート薬局の役割・機能のあり方について主に議論を行い、以上のとおりとりまとめを行った。
⚫ 冒頭でも記載したとおり、厚生労働省では、「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の推進、対物中心の業務から対人中心の業務へのシフトを図り、対人業務の強化や医療機関等との地域連携等を推進するための施策を実施してきたところである。
⚫ 「患者のための薬局ビジョン」に示された方向性については、引き続き推進していくことが重要である一方で、薬局を取り巻く環境にも変化が生じていることから、本とりまとめやこれまでの厚生労働省の有識者検討会等の結論も踏まえつつ、今後の薬局の目指すべき姿やそこに向かうための方策等について、引き続き検討していくべきである。