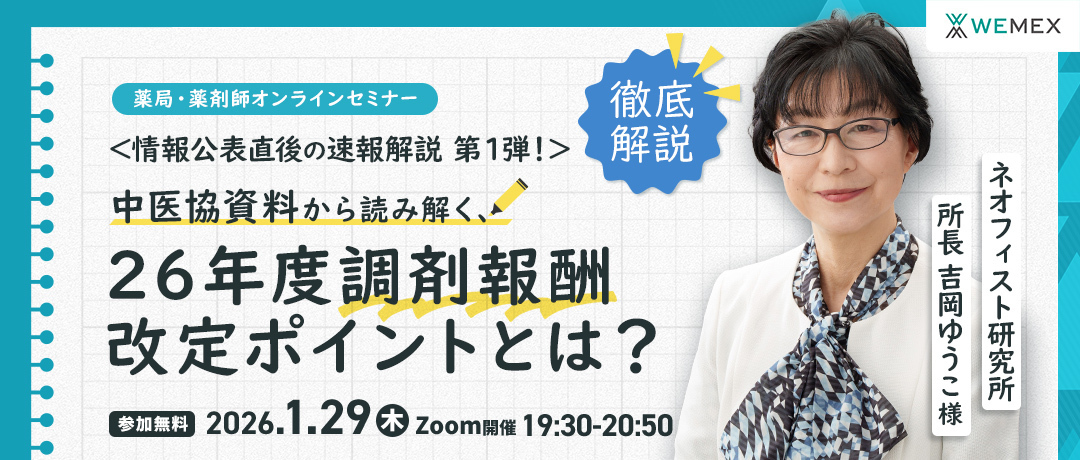党内での信頼の積み重ねに尽力し声を届ける
――今回の医薬品販売制度検討会の議論やとりまとめをどのように受け止めていますか。
神谷 今回の1年あまりの議論で、関わられてきた方は大変なご苦労だったと思います。まずは関係された皆様に敬意を表したいと思います。私は自民党の「厚生労働部会 薬事に関する小委員会」の事務局長を務めていますが、この中の議論も非常に有意義であったと感じています。事務局長としても嬉しく思っています。
今回、とりまとめに向けていろいろな議論がされていましたが、特に現場の方々からは「どうなっていくのか」、非常に心配、というお声、高い関心をお寄せいただきました。私は今回、いろいろなところにお邪魔した際には、できる限り、現状、それからご心配について具体的にお聞きするようにしていました。
――まずは、ご指摘の“経緯”についてですが、医薬品という専門的な領域に関して、厚労省、薬剤師という専門職の中で議論がある一方で、規制改革会議というどちらかというと経済原理を基本とするような会議体からのお声が強くなっているように感じています。
神谷 二軸構造になっているというご指摘の中で、重要なのは政治であると私も思いますし、そのことを、ぜひ薬剤師会の会員の皆様にもご理解をいただけるといいなと思います。政治の持っているやるべきことの1つに、横串を刺していくということがあります。厚労という分野があり、一方で経済発展という考えがあった時に、しっかり横串を刺していくということは政治が担える仕事だと思っています。例えばオンラインというものであれば、安全性を担保した上でどう行っていくのか、合意形成が必要になります。民主主義とは何かといえば、ご高承の通り、合意形成でありますから、業界団体があり、経済や社会的な状況があり、そこの合意形成にしっかり政治が関わっていくことが重要だと思います。医薬品とはどのようなものなのか、しっかり知っている国会議員をその場に送り出すということは非常に重要なことであると改めて思っています。
例えば、小委員会の中でも要指導薬について3年経ったら自動的に一般用医薬品に移行することについては懸念の声が非常に多く聞かれたところです。それぞれ国民を代表する議員の方からそういう声が出たことはしっかり受け止める必要がありますし、今回の検討会議論においても重要な決定になったのではないかと思っています。
それぞれの地域でお話ししていただいていることが、こうした小委員会の場でも意見となっているものだと思います。
――小委員会でのお話が検討会議論の方向の後押しにもなっているのですね。一方で、要指導薬が増えるのではないかという経済理論からの懸念も出ていますが。
神谷 小委員会などの意見が大きな後押しになると思いますし、逆にそれがないと、対立する意見が出た時に反論する材料もなくなってしまうと思います。
地域の薬剤師の方々が国会議員の方々と話し合いをして、自分たちの思いを理解してもらう機会を増やしていくことは重要ですし、政治と薬剤師、また薬業界との関係はとても重要なんだということを理解してもらえるように、私たちも活動していくことが重要なんだと思います。
――一方、薬剤師の声を政治の中枢に届けるためには、神谷先生ご自身のネットワーク、人脈を育てていただくことが重要なのかなと思っています。
神谷 いろいろな声を届けていくために、それは当然、一人ではできないことです。信頼をつくっていくことはとても大事だと思っています。党内での仕事をしっかり果たすことであったり、国会質問でも与党議員としてその法案にどう向き合っていくという視点を持つのか、ということで信頼を重ねていきたいと思っています。
例えば私は自民党の青年局の仕事も力を入れてやっていますが、その場でできた人間関係はやはり大事です。国会議員に薬剤師という専門職により関心を持っていただくことにつながると思っています。
――具体的なとりまとめの内容についてです。特にいわゆる零売については規制強化の方向ではないかとの反発の声が大きかったように思えます。
神谷 薬剤師の皆さんから戸惑いの声があったことは私も承知しています。大事なのは、まずは現状がどうなのかという分析、そしてそれが今後どうなっていくのかという未来の展望だと思うのです。1つ目の現状については、私は実際に現場にいた人間として、今回の「やむを得ない場合」以外については、OTC医薬品で対応できるケースが多かったと思っています。実際に現場の方々にいろいろな聞き取りをしている中でも、将来的な不安感の方が大きいようにも感じました。今回、零売そのものが否定されたわけではないというところは重要で、その上でわれわれの中で「やむを得ない」場合はどのようなものが該当するのか、共有していくことが大事になってくるだろうと思っています。もしそれが医療提供体制の中でできない、ということがあるのであれば、医薬品提供体制をその地域でどうしていくのか、併せて考えていく必要があるだろうと思います。それが2つ目の将来の展望だと思います。そのことをこれから議論していく必要が出てくるのではないだろうかと思っています。
――いわゆる零売という1つの事項だけをみるのではなく、地域での医薬品提供体制をどうしていくかという議論につながっていくわけですね。
神谷 地域包括ケアの中で描かれているように、地域によって医療提供体制であったり、医療を必要とする人たちは、これから大きく異なってくるんだろうと思っています。そうすると医薬品の提供体制もだいぶ変わってきます。それに対応する環境をどう考えるかが重要になってくるんだろうなと思います。例えばドラッグストアの場合、出店の難しい地域もあるでしょう。そういう場合は、個別の薬局でどうOTC医薬品を対応していくのかということもありますし、その時にオンラインというものをどう使っていくのかという議論も、地域によってだいぶ異なってくるのだろうと思います。都道府県もそこは想定していくだろうと思いますが、さらには地域の薬剤師会や関係者が集まってどう取り組んでいくのか考えていくことになるのだろうと思っています。
今回の検討会の議論は医薬品販売に専門家が関わるということを、かなり強く押し出していると思っています。そこは今回の肝ではないかと私は思っています。
そもそも薬剤師とは何かを考えると、薬剤師法の第1条は「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」としています。“健康を確保する”ではなくて、“健康な生活を確保する”、生活が関わってくるわけです。一般用医薬品はまさに生活の中にあるものです。普段の健康から、生活習慣、食事習慣はどうなのか、場合によっては家族はどうなのか、生活を含めてお聞きして、じゃあそれに対してはこの一般用医薬品にはこのような効果が期待され、補助的なもので良い場合は健康食品もあることを紹介していって、健康に貢献していくということになるので、地域で支える仕組みには一般用医薬品を活用してそこに薬剤師が生活の中に入っていくということがこれまで以上に重要になってくるといえると思います。
私が薬局現場に立つ中で「薬剤師さんから買うと効く気がするんだよね」と言われたことがあります。意外に思いつつも、思い返してみると、そうだなと思うところもあります。例えば、ご自身の顔を見たことがありますか? 鏡で見ることは多くても鏡の中は左右反対です。声もそうです。自分で頭に反響して聞いている声と、実際に録音で聞く声も違うと思います。つまり、自分のことは知っているようで分かっていないことも多いのです。これと同じことがOTC薬にも言えるのではないでしょうか。ご自身でOTC薬を買うとあまり的確でないこともあっても、薬剤師という専門家が客観的にみてこの症状ならこのOTC薬がいいのではないかとアドバイスした場合、フィットすることが多いのです。こういった経験を私自身、たくさん経験し、感謝されたことがあります。
このように登録販売者も含めて、専門家が介入することによってOTC薬の期待値というのはますます高まっていくと思いますし、薬剤師も生活の中に入っていく、そのことによって医薬品市場全体が盛り上がることを期待したいと思います。
――さきほど神谷議員からは、ドラッグストアという言葉も出ましたが、今後、どのように地域の薬局とドラッグストアは協力体制をとっていくことができるでしょうか。
神谷 これから考えていくべきことですね。それぞれの強い分野や得意なことというのは、それぞれが協力して補完し合うことがこれからの超高齢社会かつ人口減の中では必要になってくると思います。何を柱にやっていくかというと、まさに地域への貢献ですし、一般用医薬品を含めた医薬品の提供体制だと思います。今回の改正で期待したいところが、専門家が関与することで一般用医薬品もよく効くよねということになってくると、かなり一般用医薬品への期待も国民からも変わってくるのではないでしょうか。それは業界全体の発展につながるものです。
要指導薬が3年経てば自動的に一般用医薬品になるという仕組みについての見直しに関しても、スイッチOTCの促進になり、ドラッグストアの中でも薬剤師さんが相談販売したり、扱わない場合は要指導薬については地域の薬局と連携しようなどといった補完し合える関係にもつながるのではないでしょうか。
――個別的なことになりますが、デジタルを活用した医薬品販売における受け渡し店舗の店舗数上限撤廃や同一都道府県に限らないことなどの論点はまだ火種を残していると思いますが、どうしたら合意できると思いますか。
神谷 難しい問題ではありますが、1つ言えるのは、新しいスキームを回そうとしていることではありますから、実績を見た上で、規制について議論すべきではあると思います。
――オンラインの活用についても、こと医薬品の販売はその地域の中で議論すべきであると思うのです。受け渡し店舗で渡した医薬品でもしも救急的な対応が必要になった場合でも、その対応を担うのは結局、地域の連携の中だと思うからです。
神谷 実はオンラインを活用した例で、糖尿病治療薬をダイエット目的で購入したという方が地域外でやりとりした場合、健康被害が出ても地域では対応しづらいという事例があることを最近、お聞きしました。実際に事象としてそういったことが起きているので、デジタルの活用についてもしっかりと議論していくことが必要だと思っています。
――わかりました。ありがとうございます。