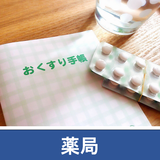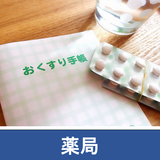事務局は「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売にかかる追加の論点について」との資料を示し、処方箋に基づく販売を基本とすること、リスクの低い医療用医薬品の販売については法令上、例外的に「やむを得ない場合」に薬局での販売を認めることとしてはどうか、とした。
その場合の販売が認められる「やむを得ない場合」については、「①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合」と、「②一般用医薬品で代用できない、もしくは、代用可能と考えられる一般用医薬品が容易に入手できない場合(例えば、当該薬局及び近隣の薬局等において在庫がない等)」の両方を満たすことを条件とする方針を示した。
また、その上で、販売に当たっては、かかりつけ薬局での販売とすることなどの要件を示した。要件としては、かかりつけ薬局の利用が難しい場合等の例外的な場合を除くとしつつも、かかりつけ薬局が販売することを示した。
加えて、「一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時には休診日等でいけない、かかりつけの医療機関に受診するまでの間に必要な分。最大数日分等)に限り販売すること」や、「適正な販売のために購入者の氏名等及び販売の状況を記録、受診している医療機関に報告すること」を要件とする案を示した。
これに対し、認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長の山口育子氏は、事務局案に近い意見を表明。処方されているものの、紛失したなど不測の事態で患者の手元にない場合に認める方向を支持。また、処方されていることが確認できる薬局でしか売れないという形が望ましいのではないかとした。「よほど薬局として関係性を持っていないと」とし、「薬局の在り方が問われる」と述べた。
日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、事務局案に「違和感はない」とした上で、事務局案で示した2つの条件を満たすことは重要との考えを示した。一方、その条件を満たした場合の販売にあたった要件については、「さまざまなケースが生じる」として、多彩な事例の抽出を求める意向を示した。
日本医師会常任理事の宮川 政昭氏は、「やむを得ない場合」に関して、「レアなケースはほとんどない」とし、前提条件の1と2は守られるべき、との考えを示した。例外についても、「医療機関と薬局が整合性を高めていただければ解消できる」との基本的な考えを示した。これまでの通知が守られてこなかったことについては、「法令に近い、当然尊重すべきものなのに当該薬剤師が無視していることになる」と指摘した。
東京都福祉保健局健康安全部薬務課長の中島真弓氏は、 監視指導の立場から法令に位置付けてほしいとの考えを示した。また、かかりつけ薬局で販売するようにするとの事項については、「もし要件を設定するならかかりつけ薬局の定義と確認方法を明確にし、判断がばらつかないようにする必要がある」とした。
森・濱田松本法律事務所の末岡 晶子氏は、事務局案に「基本的に賛成」としつつ、かかりつけ薬局での販売とすることについては、「再考いただければ」とした。理由として、これまで実際に販売してきた事業者が販売が不可能になることについては、営業の自由の関連からも慎重さが必要との意見を示した。「法律的には禁止されていなかったことに禁止事項をつくることになるので、営業の自由の制限になる。今まで、もしかしたらゆがんだ形だったかもしれないが、営業はできていたので、事業者が満たせない要件を課すのは躊躇を感じる」と述べた。
【編集部より】
ドラビズもPR記事をお手伝いさせていただいた、調剤売上データの収集・集計・分析業務を自動化し、店舗・本部スタッフ・マネージャー・オーナーの負担を軽減する新しい薬局経営見える化ツールの「digicareアナリティクス」は、8月15日〜8月25日までオンラインセミナー(45分間)を開催します。digicareアナリティクスの導入方法やユーザーで主に使われている具体的な活用方法など、普段の薬局経営分析にとっても参考になる内容になっています。ぜひご参加ください。
参加申し込みは下記URL、もしくはバナー広告から。
https://digicare.jp/seminar/dgsonline/?utm_source=dgs-on-line&utm_medium=banner&utm_campaign=seminar202308