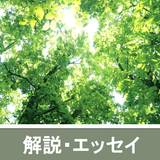濫用等のおそれのある医薬品については、特に若年層において社会問題となっている。そのため今回の検討会でも何らかの制度見直しを行う方向となっている。
事務局が示した論点は以下の通り。
■濫用等のおそれのある医薬品
オンライン服薬指導(画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信)を用いた販売方法とすることについて、どのように考えるか。
○ 身分証による本人確認、販売時の情報提供や確認の実施記録を課すことについて、どのように考えるか。
○ 小包装(例えば二、三日分)のみ販売可とする制度とすることについて、どのように考えるか。
○ 長期的にはマイナンバーカード等による購入情報の一元管理を前提とした規制を導入することについて、どのように考えるか。
こうした論点のうち、オンライン服薬指導による販売については賛成の声が多く出た。
より気軽に買えるネット販売よりも、処方箋薬の調剤においても用いられているオンライン服薬指導を用いることで本人確認などが確実になるとの見方も示された。
日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「複数の店舗で買い周りができること、購入しやすさ、容易なアクセス、それから確実な本人確認の点から見直しが必要だ。具体的にはネット販売ではなく店舗での販売を基本とした上で、画像情報を伴うオンライン形式による販売方法に限定すべきだ」と述べた。加えて、規制強化だけでなく顔の見える関係性によって専門家による啓発機能を発揮し、濫用防止機能を発揮したいとした。「適切な販売方法と啓発の両輪で進めていくべきだ」とした。最小個数の販売、頻回・複数の購入、小包装、表示などへの工夫も必要とした。将来的な課題としてはマイナンバーカードの活用による防止策も考えられるとした。
また、小包装については認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOMLや日本医師会の委員から規制すべきとの意見が出た。
認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長の山口 育子氏は、「濫用のおそれのある医薬品は特定できている。ネット販売はまずだめということにする必要があるのではないか。ネット販売のチェックは形式的。致死量に致る包装が販売されているのは危険極まりない。家族での購入もあるようだが、それは家族での使用を伝えた上で、2、3日分を複数個、販売すればよい。23日分のかぜ薬は規制をかける必要があるのではないか。小包装での販売に進むべきだと思う」と述べた。
日本医師会常任理事の宮川政昭氏も、「山口氏と同じ意見だ。一元管理は長期的な視点もあるが、短期的には数量、小包装に対応すべき。ワンパッケージに(致死量が)入っていることはあってはならない。3、4日服用して症状が変わらなければと書いてある。それならば12回分が適切だよとするしかない」とした。
この日の会議では「現在販売されている製品で1箱で中毒量・致死量になる製品パッケージ調査」の結果として、該当する64製品のうち、一例として具体的な商品名と包装容量も提示された。
ただ、小包装に関しては日本OTC医薬品協会からは利便性を損なうリスクもあるとの意見が示された。
日本 OTC 医薬品協会事業活動戦略会議座長・薬制委員長の山本雅俊氏は、コロナ禍においても備蓄の存在意義は大きかったとし、小さい包装のみとすることは生活者の利便性が損なわれるとの意見を表明した。

【医薬品販売制度検討会】市販薬の濫用問題、オンライン服薬指導による販売が俎上に
【2023.06.13配信】厚生労働省は6月12日、「第5回医薬品の販売制度に関する検討会」を開催。この日は「濫用等のおそれのある医薬品」についても議題になった。事務局は「オンライン服薬指導を用いた販売方法とすることについて、どのように考えるか」と論点を提示。委員から賛成の声が多くあがった。ネット販売がメールなどのやりとりであるのに対して、オンライン服薬指導による販売は画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信を想定しており、より本人確認などで実効性があるとみられる。
関連する投稿
【厚労省_令和6年度医薬品販売制度実態把握調査】“濫用薬”販売方法で改善みられる
【2025.08.26配信】厚生労働省は8月22日、「令和6年度医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表した。同調査は、薬局・店舗販売業の許可を得た店舗が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調べたもの。令和6年度の調査は、前年度に引き続き一般用医薬品のインターネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めた調査を実施した。
【“濫用薬”】デキストロメトルファン、「直ちに指定を」/嶋根研究班
【2025.04.15配信】国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所は、「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究(2024年)」の報告書をホームページに掲載した。
【市販薬の乱用】中学生にも/過去1年間の経験率は1.8%、55人に1人/嶋根研究班
【2025.04.15配信】国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所は、「飲酒・喫煙・薬物乱用についての全国中学生意識・実態調査(2024年)」の報告書をホームページに掲載した。
【東京都】“濫用薬”ネット販売でルール遵守の形骸化例を確認/監視事業で
【2025.01.28配信】東京都薬事審議会が1月28日に開かれ、薬事監視指導に関連する事業内容について報告があった。
【2025.01.15配信】市販薬の濫用対策の見直しをめぐって、ドラッグストア業界やネット事業者関係者からの“経営視点”での議論の応酬が目に付く。その根底には現状のビジネスの継続に支障となるとの思惑がのぞく。しかし、濫用問題は孤立の問題や相談先の確保、もっと言えば人的なリソースなど、地域でどう若者など守るべき人を守っていくのか、という点に収斂される。地域の持続性をどう確保するのかという、すなわち、石破茂首相が就任以来、掲げてきた「地方創生」にも関わる問題だ。
最新の投稿
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。
【答申】調剤管理料「2区分」化では「7日以下」では増点の結果
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤管理料(内服薬)では、「長期処方」(28日分以上)以外は10点となる。長期処方は60点。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤基本料「1」と「3ーハ」で2点増点する。
【日本保険薬局協会】門前薬局“減算”、「到底受け入れられない」/三木田会長
【2026.02.12配信】日本保険薬局協会は2月12日に定例会見を開いた。この中で会長の三木田慎也氏は、次期調剤報酬改定の項目、いわゆる“短冊”について触れ、「門前薬局等立地依存減算」について「到底、受け入れらない」と強調した。「患者さんの動向、患者の志向、いわゆるマーケットインの発想が調剤報酬をつくる側に全く意識されていない結果」と述べた。