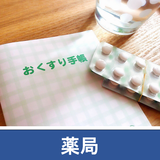同検討会では、医薬品の販売区分及び販売方法やデジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方が議論される。
デジタル技術の進展を踏まえ、薬剤師等による遠隔での情報提供の可能性などを議論するほか、一般用医薬品による救急搬送事例の増加を踏まえ、濫用等のおそれのある一般用医薬品の販売のあり方も議題とする。
こうした議題に対し、落合弁護士はデジタル臨調で、「デジタル原則」を踏まえた「アナログ規制に関する点検・見直し」が手掛けられていることを説明。デジタル臨調では、2022年12月開催の会議で、法令約1万条項全ての見直し方針及び見直しに向けた工程表が確定したと報告されている。今回の検討会の開催の目的の1つに、2022年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」での「患者のための医薬品アクセスの円滑化」の議論があるが、落合氏は「規制改革推進会議の書面・対面規制の見直しも、デジタル原則とオーバーラップするもの」とし、「それを踏まえて議論をしていただけるといいと思う」と述べた。
デジタル原則とは、現行の規制や法令がデジタル時代に則しているかを判断する適合性についてデジタル臨調が5原則を規定しているもの。
落合氏はデジタル原則に基づく見直しの中で特に、常駐・専任規制が見直しされるとし、「必要な部分については国会でも改正法案が提出されるということになっている」と説明した。
一方、医薬品においては有効性・安全性の確保は重要だとして、「場合によっては強化、新しくつくることも必要だと思っている」と指摘した上で、「ただ、その際もオンラインにだけ厳しくするということではなく、リスクに対応しようということであれば対面・オンラインを問わず両方を適切に整理するべき」と指摘。「対面と差別するということは行わないように整理していただくことは重要」と述べた。
スイッチOTCやタスクシェアについては進める要望をした。
スイッチOTCについては、「規制改革推進会議でも例年、スイッチOTCの話にも取り組んでいる。必要な範囲について、枠組みの整備を議論していただけるといいのではないか」と述べた。
タスクシェアについては、「過疎地域などにおいては医師だけでは地域医療を維持できないという声もいろいろなところからあがっているところ。薬剤師の業務の拡充、専門家としての役割も重要だ」と指摘した。

【厚労省_医薬品販売制度検討会】落合弁護士「デジタル原則とオーバーラップするもの」
【2023.02.22配信】厚生労働省は2月22日、「第1回医薬品の販売制度に関する検討会」を開いた。この中で、弁護士の落合孝文氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)は、自身が作業部会の委員を務めるデジタル庁デジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)での「デジタル原則」の議論にも触れ、医薬品の販売制度も「オーバーラップするもの」だとの見方を示した。
関連する投稿
【楽天三木谷氏】“濫用薬”の規制方向「撤回を」/デジタル社会構想会議で表明
【2024.04.24配信】デジタル庁は4月24日、第 9 回デジタル社会構想会議を開いた。この中で三木谷浩史氏(楽天グループ株式会社/一般社団法人新経済連盟)は厚労省の進める“濫用薬”の規制方向を撤回するよう意見した。
【医薬品販売制度】神谷政幸参議院議員に聞く/強まる規制改革の声、「横串を刺すのが政治の仕事」
【2024.02.22配信】「医薬品医療機器制度部会」にステージを移した医薬品販売制度改正。これまでと今後の展望について、自民党の「厚生労働部会 薬事に関する小委員会」の事務局長として議論の行方にも関わってきた参議院議員の神谷政幸氏にインタビューした。
【規制改革会議議事録】佐藤WG座長「成分の規制の必要も」/“濫用薬”の販売制度問題で
【2024.01.24配信】内閣府規制改革推進会議は、1月24日までに令和5年12月26日開催の会議議事録を公開した。その中で「健康・医療・介護ワーキング・グループ」(WG)の佐藤主光座長は濫用のおそれのある医薬品成分の規制などについて指摘している。
【2024.01.17配信】日本の厚労省検討会で議論の進展は少なかった“共用薬”問題。保険など複合的な問題がからむため、粘り強く、かつ包括的な議論が今後求められそうだ。「OTC薬を医師が処方するのはやはり非現実的なのか」と思ってしまいそうだが、ドイツにはすでに医師がOTC薬を処方する制度がある。そこで本紙では、今後の議論の少なからずの参考になるよう、ドイツの薬局開設者であるアッセンハイマー慶子氏に取材した。
【医薬品販売制度検討会とりまとめ議論】“濫用薬”、20歳での区別に日薬が最後まで反論
【2023.12.18配信】厚生労働省は12月18日に「第11回医薬品の販売制度に関する検討会」を開いた。この中で「濫用等のおそれのある医薬品」を対面・もしくはオンライン(画像)を用いた販売とする方向で議論をされてきたが、事務局は「20 歳以上の者が小容量の製品1個のみ購入しようとする場合」については、ネット販売を認める案を提示した。
最新の投稿
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。
【答申】調剤管理料「2区分」化では「7日以下」では増点の結果
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤管理料(内服薬)では、「長期処方」(28日分以上)以外は10点となる。長期処方は60点。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤基本料「1」と「3ーハ」で2点増点する。
【日本保険薬局協会】門前薬局“減算”、「到底受け入れられない」/三木田会長
【2026.02.12配信】日本保険薬局協会は2月12日に定例会見を開いた。この中で会長の三木田慎也氏は、次期調剤報酬改定の項目、いわゆる“短冊”について触れ、「門前薬局等立地依存減算」について「到底、受け入れらない」と強調した。「患者さんの動向、患者の志向、いわゆるマーケットインの発想が調剤報酬をつくる側に全く意識されていない結果」と述べた。