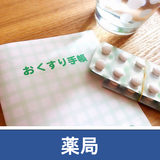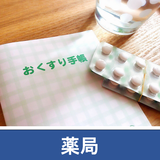「物販+オンライン服薬指導」は差別化にもなりそう
「SOKUYAKU」の足下の状況をみると、導入先は2022年7月時点で医療機関で2702軒、薬局で4017軒、ユーザー数も約60万人に増えてきた。保険診療での活用が多いため、市中の医薬分業率同様に過半がオンライン服薬指導の利用になっているという。
その「SOKUYAKU」が現在、サービス機能拡充として開発に注力しているのが、“ついで買い”のサービスだ。オンライン服薬指導を受ける患者の中にはそのほかのOTC医薬品や日用品もついでに買いたいというニーズがあり、そのニーズに「SOKUYAKU」が応えるもの。もともと処方薬は配達員がドラッグストアや薬局にピックアップに行っているため、その際に一緒に同梱して他のものを届けるようにする。利用者からすれば、医薬品の宅配でかかっているお届け料で欲しい商品の買い物まで済ませられる。「SOKUYAKU」についてはツルハやその他ドラッグストアも導入をリリースしているが、さらに導入企業が増加する見込み。新型コロナウイルス第7波以降、利用者数が急激に増加しているという。“ついで買い”は、宅配までを網羅している同サービスだからこそ追加できるサービスであり、今後、優位性を発揮していくことになりそうだ。
なお、オンライン診療では遠方のクリニックを受診する場合でも、早く医薬品を入手したい場合は、利用者自宅の近くの薬局である必要があるため、利用者の居住地近くの薬局がオンライン服薬指導で利用されることになる。NB商品が多くECサービスの差別化が難しいという指摘もあるドラッグストア業界だが、オンライン服薬指導の利用がECの追い風になる可能性もある。ドラッグストア業界では“Uber Eatsのような配達サービスも広がっているが、「SOKUYAKU」もそういったサービスの中の差別化できるものとして普及することを狙っている。
改めて、「SOKUYAKU」の概要を紹介する。「薬局でオンライン服薬指導関連サービスを導入しても患者からの予約が入らない」、という声が少なくない中で、「SOKUYAKU」が拡充しているのは利用者の拡大。自社で俳優の大沢たかお氏を起用したテレビCMを放映するなど、ユーザー獲得に注力し、そのことでアプリが実際に利用されるシーンを増やしている。医療機関は普段の運用と並行しての利用となるため、予約時間が近づくとリマインドの連絡を行い、実際にオンライン診療等が完遂するまでをフォローアップしている点も特筆できる。予約の完結率は95%という。医療機関や薬局の導入費用や利用料は無料で、患者から1診察あたり165円(およびオンライン服薬指導1回165円)という利用料を課金するという仕組みも他にはないものだ。医薬品の宅配までにかかる時間も最短で1時間と圧縮に成功。これはもともと診療予約の時点でオンライン服薬指導や宅配までを予約していることでバリューチェーンが分断するロスタイムが生じないためだ。料金も施設が決めるのではなく一律とすることで利用者にとって分かりやすくなった。当日宅配の場合はバイク便で550円、翌日配送の場合は440円、日本全国、当日の16時までに服薬指導を受けていれば翌日中には届くような配送体制になっている。また、新たに店舗での受け取り昨日を追加。その場合は予約した薬局へ、オンライン服薬指導実施後に患者が受け取りに行くことで送料が0円にすることが可能。
基本的な「SOKUYAKU」の利用方法は日時、エリア、診療科目から診療予約。続いて、オンライン服薬指導を行う薬局を予約する。薬局は患者の住所の近くから上位表示されるほか、かかりつけ薬局の登録も可能になっている。予約した診療時間になると、アプリから入室でき、診療を開始。同様にオンライン服薬指導も受ける。薬の配達状況の確認も可能だ。
将来的に地域の薬局の連携には活用できないのか?
「SOKUYAKU」のようなオンラインシステムでは、地域の薬局同士の連携はできないのか、という疑問がわく。この点に関して同社社長の中村篤弘氏は、すでにオンライン診療の中でも往診が必要な場合において、地域での連携があることを例に挙げ、薬局でも同様のことが起こってくる可能性はあるのではないかと指摘する。
具体的には、同社では大阪で自治体と協力してオンライン診療に協力しているが、自治体から相談があるのが「往診もできないか」というものだという。オンライン診療をしたものの、「この患者さんに関しては往診が望ましい」というケースの場合だ。その場合、オンラインでは一定の距離があってもよいが、往診となると地域の診療所に依頼が必要になる。初診のオンライン診療をする診療所と、往診ができる診療所をつなぐ必要性が出てくる。そのため同社では往診のできる診療所の登録数増加も力を注いでいきたい考えを示している。これは薬局の場合でも、「宅配」であれば受けていた薬局と、「薬剤師によるお届け」ができる薬局をつなぐ、ある意味で棲み分けも出てくる可能性を示していると指摘できる。薬局という施設に固定化されている薬剤師というリソースも、システムによって流動的にマッチングできることにつながるのかもしれない。
中村社長は「コロナ禍で閉める個人の診療所もあった。腕のある医師と良い経営はまた別な部分もある。そういう中で貴重な医療従事者という資源を最大限に役割発揮していただくということは非常に重要ではないか」と指摘する。
中には「SOKUYAKU」を上手に活用し、過重な負担を抱えずに高収益を上げている医師も登場しているという。
また、自治体の強い要請から「SOKUYAKU」を導入しているケースも増えてきているという。自治体では土日・祝日・年末年始にどう地域で対応するかという点で問題意識が大きいという。実は同社在籍の医師も活用しながらそれを補完する仕組みを構築しており、かつ導入費用が無料ということもあり、自治体から評価される場合があるという。その場合は自治体が主催で説明会を開き、導入医療機関を募る形をとっているという。
過疎を挙げるまでもなく、感染症蔓延を筆頭に医療の提供体制をどう補完するかに自治体の関心は思う以上に強まっているようだ。それに非接触や利便性を求める利用者のニーズもあいまって、「オンライン診療・服薬指導」の形も広がってきている。
なお、同社サービスにはニーズに応じてカスタマイズ後の提供もあり、自社サービスのように使用できるものでは、「薬局1店舗月額1000円」のサービスなどもある。
【主なSOKUYAKU導入企業名】
・ツルハホールディングス(ツルハドラッグ、ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、ビー・アンド・ディー、くすりの福太郎、レディ薬局、杏林堂薬局)
・I&H(阪神調剤グループ)
・株式会社大賀薬局
・株式会社マリーングループホールディングス
・総合メディカル株式会社(薬局向けサービスであるオンライン薬局を導入)
■薬局・ドラッグストアの登録は以下のURLから登録すると、事務局が施設情報を登録。アカウント発行連絡後の利用となる。薬局などの施設側で利用料がかからないのも特徴だ。
https://onl.sc/E5bwyKq
■ユーザーのアプリ登録は以下から可能
https://app.adjust.com/d5b78vv

ジェイフロンティア株式会社 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘●1980年、神奈川県相模原市生まれ。大学卒業後、ドラッグストアでの医薬品の販売業務からスタートし、EC向けインターネット広告代理店の責任者に就任。2010年よりジェイフロンティア株式会社代表取締役に就任。数多くのヘルスケア関連商品のEC事業の立ち上げ・マーケティング支援に携わる。2021年2月より「SOKUYAKU」アプリを配信開始。2021年8月、東証マザーズ(当時)上場