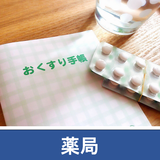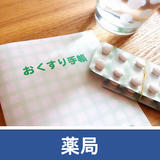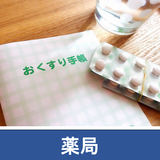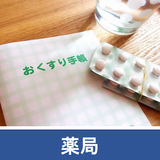省令は3月31日に通知が出ていた。
■「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000922763.pdf
日薬は翌日の4月1日に、都道府県薬剤師会宛に資料を発出した。その中では見直しのポイントを以下のように説明している。
・実施の都度、薬剤師の判断・責任により、初回からオンライン服薬指導の実施が可能。
・処方箋について、従前はオンライン診療又は訪間診療を行った際に交付された処方箋がオンライン服薬指導の対象とされていたが、今後は診療の形態に関わらず全ての処方箋が対象。
・薬剤について、従前はこれまでに処方されていた薬剤又はこれに準じる薬剤の場合がオンライン服薬指導の対象とされていたが、今後は原則として全ての薬剤がオンライン服薬指導の対象 (なお、初診の場合には処方しないこととされている薬剤 (麻薬や向精神薬等) がある)。
・「服薬指導計画」の策定に代えて、必要事項を示した上で行うこと。
・オンライン服薬指導は、患者の意向の範囲内で、かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ましいこと。
これに関連し、安部好弘副会長は適切に運用していくことが重要との見解を示した。
「薬剤師がフォローアップしなければいけないということがありますので、対面でフォローアップをするということを中心にしながら、それを補完するような形でオンライン服薬指導を適切に使っていただいて、その必要性やニーズにあったもので薬剤師が適切にやれば、それはフォローアップを実施して、医師と連携して薬物治療の安全を守るということにつながっていくのではないかと思っています」(安部副会長)
また、磯部総一郎専務理事は今回決まったルールにのっとり実施していくことが重要との考えを示した上で、「このルールをしっかり守ってやっていただいて、またおかしいところがあれば我々もまたいろいろ申し上げていかなければいけないだろうと思います」と述べた。
「オンライン服薬指導の場合は、薬というモノがあって、きちんと飲んでもらうために確認するということも含まれています。そういう意味で、いわゆる画面上でどうだということについては、現場からもその点はちゃんとできるのかという不安を持っておられる方はたくさんいます」と指摘し、対面かオンラインかの判断は薬剤師が行う必要があるとの考えをにじませた。
今回の省令ではオンライン服薬指導は「薬剤師の判断と責任」の下で認められており、薬剤師の可否の判断はポイントになるだろう。
3月31日に行われた厚労省「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」では、「オンライン服薬指導が不適切なケース」についての意見(第2回の意見に追加含む)もとりまとめられ、提示された。吸入薬やインスリンなどのデバイス使用説明などの場合のほか、抗精神病薬や抗コリン薬など画面上の副作用確認が困難な薬剤(口腔内・口臭など)、皮膚症状などを直接目視する等の必要がある場合などが不適切なケースとして挙がっていた。
この点について、日薬・磯部専務理事は事例を収集した上で、日薬のe-ラーニングなどに取り込むことで周知徹底を図っていく方向もあり得るとの考えを示した。
「オンライン服薬指導を適切に使用するために私ども担当役員、担当の委員会の方で今、e-ラーニングのコンテンツをつくっています。これは厚労省の予算事業として補助もしていただいて、実施主体は私どもです。どういうことに気をつけないといけないかということで実際に、研修資材を準備して公開もしています。オンライン服薬指導の不適切な事例については実は、一昨年度から帝京平成大学の亀井(美和子)先生、うちの常務理事もされていますが、厚労科研で実際にいろんな事例を集めてどういう問題があるかという整理をしています。それは今回のルール作りにもかなり活用していただいています。ただ、1つ悩ましいのが、0410通知を対象に網羅しているので音声のみでの実施が多いことです。今回は薬そのものを確認しながら薬識もちゃんと持ってもらうということを考えると、映像が必須だろうということになっているので、映像もあった上でどういう場合はどうなのかということについては、それほどの知見が集まっていないので、今後さらなる状況を見ながらどういう風にお伝えをしていくのかということだと思います。イーラーニングコンテンツもやらせていただいているので、そういった伝えなければいけないものについてはバージョンアップしていくということも含めて、やらせていただいていくということになると思います」(磯部専務理事)
なお、「第2回ワーキンググループにおける主な意見」資料の中でオンライン服薬指導の不適切なケースに関連する意見は以下の通り(⑤〜⑭は追加意見)。
3.オンライン服薬指導
論点1:オンライン服薬指導が不適切であり対面の服薬指導が必要となるケースとしては、具体的にどのようなケースが想定されるか。
①オンライン服薬指導は、顔色や表情が見えないという点に留意が必要。
②目指すべき薬局薬剤師について、アメリカでは届かない薬、服薬指導が行われていないという実態がある。利便性に振り切ると危ない。
③オンライン服薬指導の質を担保する上で、ガイドラインを作っていくべき。
④服薬指導に必要な情報を全てリストアップし、各情報がオンラインでも適切に得られるかを検討すべき。
⑤軽微な一過性の急性疾患・病態(急性上気道炎、急性胃腸炎、機能性頭痛など)や、急性疾患の後遺症、安定した慢性疾患に対する継続的診療についてはオンライン服薬指導による患者利益が大きいのではないか。ただし、精神疾患や膠原病、悪性腫瘍、気管支ぜんそくなどについては、医師による判断を挟んだ方がよいのではないか。
⑥対面での患者アセスメントが不可欠な場合や、患者・家族の理解力に課題があると想定される場合は、対面での服薬指導が望ましいのではないか。
⑦急性期かつ重症度が高いなどの疾患側の原因、生理作用や副作用が強いなどの薬剤側要因、薬物濫用や目的外利用が疑われる、認知機能低下があるなどの患者側要因を総合的に勘案して判断すべき。
⑧吸入薬やインスリンなどのデバイス使用説明、抗精神病薬や抗コリン薬など画面上の副作用確認が困難な薬剤(口腔内・口臭など)、一包化患者については、画面を通じたオンライン服薬指導は困難ではないか。
⑨患者が薬剤を目の当たりにして、粉の量が多い、錠剤が大きく飲めないと気づくケースもあるため、初処方薬については対物と服薬指導を切り離すのは望ましくない。
⑩皮膚症状などを直接目視する等の必要がある場合は画面を通じた評価をすべきではない。
⑪不安感が強い患者と信頼関係を構築するために、言葉以外のコミュニケーションが必要な場合は、対面による指導が必要。
⑫定期的な調査により検証を行っていくべき。
⑬オンライン服薬指導について、問い合わせや電話対応など患者からのアクセスを保証すること、有事の際の速やかな対応体制を確保すること、対面指導への切り替えや早急に服用が必要な薬剤の供給、自主回収への対応などは、確実になされるようにすべき。
⑭服薬フォロー、受診勧奨、患者の主治医、処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮すれば、オンライン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべき。
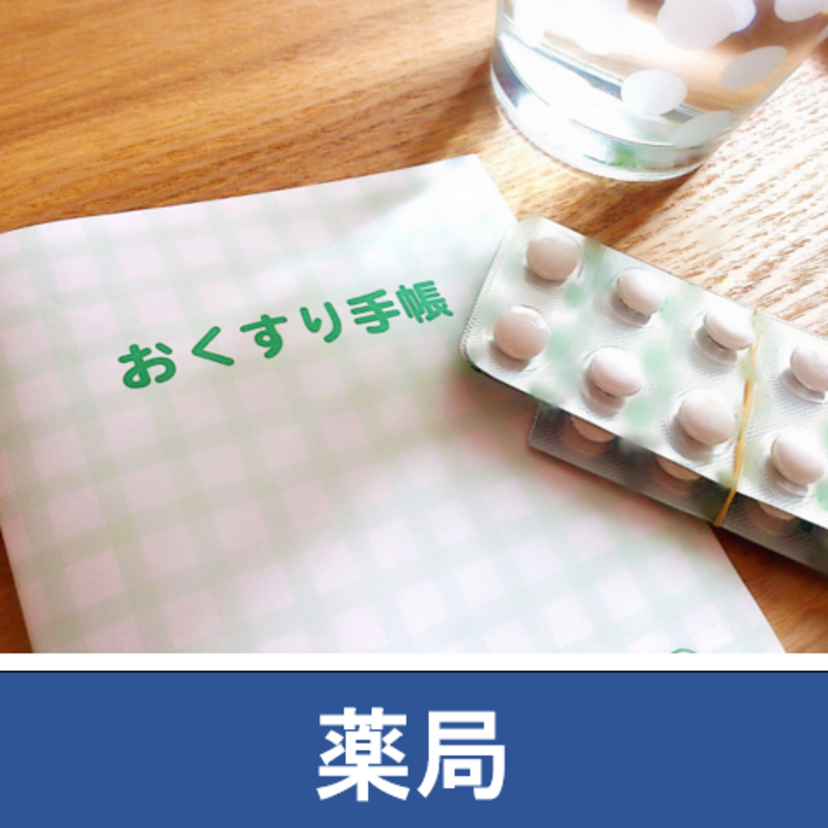
【日本薬剤師会】オンライン服薬指導の「不適切なケース」、e-ラーニングでの取り込みも視野
【2022.04.14配信】日本薬剤師会(日薬)は4月13日に定例会見を開き、オンライン服薬指導に関する省令の施行に関して説明した。この中で磯部総一郎専務理事は、「オンライン服薬指導が不適切なケース」の検討に関して、日薬のe-ラーニングの研修コンテンツとしてバージョンアップし周知を図るなど、今後、取り組む可能性があるとした。
関連する投稿
【日本薬剤師会】会員1671人減少、10万人切る/組織強化委員の報告書は年明け完成見込み
【2025.12.23配信】日本薬剤師会は12月23日に定例会見を開き、日本薬剤師会の全国会員数調査報告について報告した。
【日薬】森副会長「基本料1の議論、手をつけること考えていない」
【2025.12.03配信】日本薬剤師会は12月3日に定例会見を開いた。その場で中医協委員である副会長の森昌平氏は調剤基本料1を取り上げた議論に対して、日薬としては「対応は全く考えていない」と言及した。
【2025.12.03配信】日本薬剤師会(日薬)は12月3日に定例会見を開き、中医協での調剤報酬改定の議論について言及した。
【日本薬剤師会】財政審の改革提言に反論、「薬局増えても調剤報酬増えない」
【2025.11.05配信】日本薬剤師会は11月5日に会見を開いた。この中で、同日公表された財政制度等審議会(財政審)財政制度分科会の提言に対し反論した。
【2025.11.05配信】日本薬剤師会は11月5日に定例会見を開いた。その中で、岩月進会長が中医協での敷地内薬局をめぐる議論に対してコメントした。
最新の投稿
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【コミュニティファーマシー協会】ドイツ薬局視察旅行の参加者を募集
【2026.02.22配信】 日本コミュニティファーマシー協会はドイツの薬局を視察する旅行参加者を募集する。 旅行期間は2026年6月8日(月)〜6月13日(土)まで4泊6日。申し込み締切は、2026年3月5日(木)。
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。