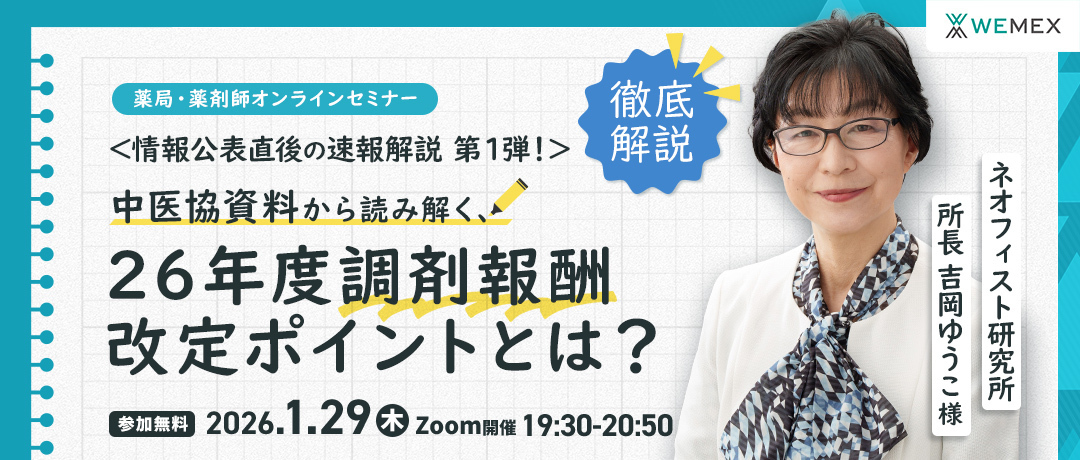健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、次のようにコメントした。
“
これまで中医協で議論してきました内容を踏まえまして、政府として医療保険制度の持続可能性の確保に向けて薬価改定を実施するという判断をいただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。
資料1ページも示されておりますが、改定の対象品目につきましては国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応するということで国民負担軽減を大前提としてメリハリをつける考え方が示されてたと受け止めております。
長期品の「0.5倍超」、「特許が切れたら速やかに後発品に市場を譲ると言う考え方に合致するもの」
その上で薬価改定骨子たたき台に向けて何点かコメント差し上げたいと思います。
まずはカテゴリー別に対象を設定することは、先ほど申し上げました通り、政府の判断ですので異論はございません。
長期収載品の対象範囲を平均乖離率の0.5倍超まで拡大することは、新薬メーカーが長期収載に依存せず、特許が切れたら速やかに後発品に市場を譲ると言う考え方に合致するものと評価しております。
また新薬創出加算については過去の薬価引き下げの猶予分を早期に返還するという観点から、適用ルールの④に示されております累積額控除は極めて妥当な判断だというふうに評価しております。
新創品「1.0倍超」、「将来の医療保険制度の持続可能性に影響するもの」
一方で、令和6年度薬価制度改革で改定前の薬価を維持する仕組みに充実したにも関わらず、新薬創出加算品目の実勢価改定の範囲を平均乖離率の1.0倍超とすることには、将来の医療保険制度の持続可能性に影響するものと考えております。
さらに新薬創出加算品以外の新薬の対象範囲を平均乖離率の0.75倍とすることは画期性や有用性が乏しいにもかかわらず、これまでの0.625倍から範囲を狭くすることについては、イノベーション推進にどのような影響があるのか、今後検証する必要があると指摘させていただきます。
これまでも実勢価改定の対象範囲を狭くすれば、不採算再算定や最低薬価に充当する財源が限定的になると申し上げてまいりました。今回、メリハリを付けつつも、全体として実勢価改定の範囲は狭くなるというふうに考えております。
続きまして、適用ルール③の不採算品再算定ついては、前回も指摘しました通り、そもそも特例的な薬価に引き上げを繰り返すべきではないことや、安定供給に関する効果が乏しいことを踏まえれば、臨時的にするのであれば、本当に必要な物の対象商品を絞るべきであり、最低薬価に引き上げを行うことを踏まえますと、不採算再算定の対象基準はむしろ厳格化すべきと考えております。先ほど説明がありました安定確保品の中でも、参考資料の15ページ、18ページ、19ページで今回お示しがありましたけれども、優先度が低いカテゴリーCを対象から除外することや、不採算品であったとしても平均乖離率を超える値引きを行っているものは対象にすべきではないということを改めてコメントさせていただきます。私からは以上でございます
”
委員からの指摘に関連して、事務局は次のようにコメントした。
“
ご意見頂きましてありがとうございます。今後、たたき台に向けて作業を進めてまいりたいと思います。
1点ですね、今回、医薬品のカテゴリーごとに分けたところでございまして、(健保連の)松本委員から、新薬創出加算については平均乖離率1.0倍とすることは将来の医療保険制度の持続可能性に影響するものというようなご指摘がございました。おっしゃりたいことは多分、今年度、いわゆる加算額で戻った額というものが、将来控除される額に含まれないというようなことになりますが、今回、これまでの中医協の議論の中でですね、イノベーションの評価というところがございましたので、特に新薬創出加算品につきましては今回1.0倍とすることによって、将来、後発品が出てきた後に控除されるところについても少し免除ができるということも、1つのイノベーションに向けて、新薬メーカーに開発していただきたいというメッセージだと思っております。
それから、2つ目、新薬創出加算品以外の新薬、こちらについては0.75倍ということで、従前よりも緩いのではないかという指摘でございますが、乖離率の実態から言いますと、前回ですと平均乖離率4.735%よりも大きいものが対象になっておりましたが、今回はもともとの平均乖離率が5.2%でございましたので、0.75を掛けますと3.9%以上の乖離率が対象ということで、乖離率自体としては前回よりも厳しい範囲、対象は大きくなっているという風に考えています。以上でございます。
”