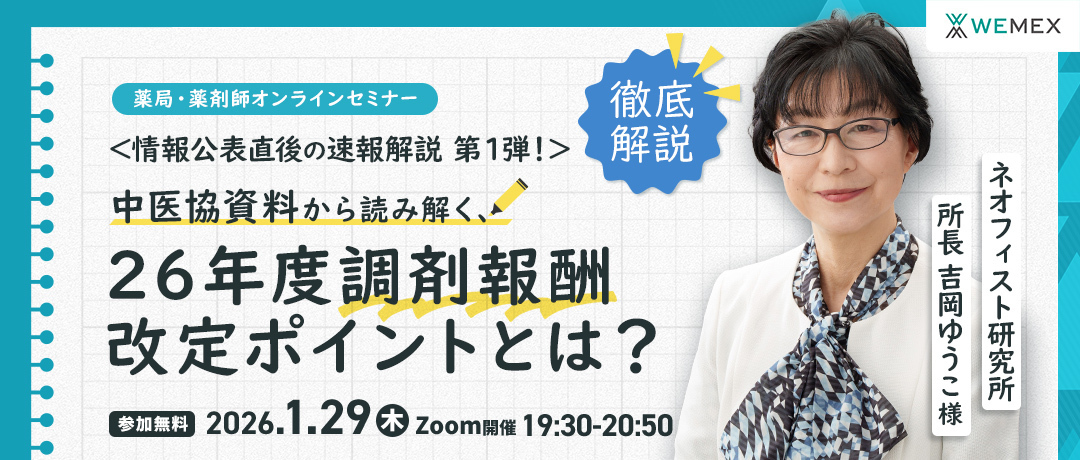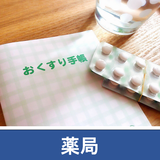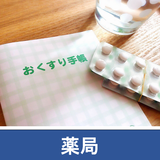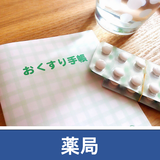コロナ禍でリアルイベントを泣く泣く中止した――。そんな企業や団体は多いのではないだろうか。
こうした中、あるドラッグストアが開催中止となったリアルイベントの内容を動画にしてオンライン配信するという形で実施し、注目を集めている。「リアルで行おうとしていたイベントを、ただ漫然と来年に持ち越すことで、逃すチャンスはないのか」。「そもそもリアルイベントは何を目的にしていたのか」。「その目的はオンラインでは実現できないものなのか」――。社内で議論を尽くした上で、5万人の集客を目標にしたオンラインイベント開催にこぎつけた同社の知見は、多くの企業の参考になるだろう。
「そもそもリアルイベントは何が目的だったのか」
実施したのは福岡県に本社のある新生堂薬局。同社は4月29日に、福岡国際センターで健康イベント「FUKUOKA ハッピーフェスタ 2020」の開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で中止を余儀なくされた。しかし、手法をリアル開催からオンライン開催へ変更し、「FUKUOKA オンラインハッピーフェスタ」として7月1日~8月31日まで開催することにした。
イベントサイトにアクセスすると、動画がテーマごとに分かれている。「薬と健康」「栄養と運動」「美容」「くらし」「動画で体験」「スペシャルトーク」といった具合だ。
イベントサイトにはクイズコーナーがあり、動画を観ることで回答が分かるような仕掛けになっている。クイズに答えるとプレゼント企画に応募できるようになっている。つまり、主催者にとっては動画再生にインセンティブを付けることができる仕組みといえ、生活者にとっては健康に関する情報を取得しながらプレゼント企画にも応募できる仕掛けがされている。
同社はどのような経緯で、今回の開催に至ったのか。
同社は昨年、福岡を会場とした「健康すこやかウォーク」(来場者約2000人)、熊本を会場とした「赤ちゃんフェスタ」(来場者3000人)でリアルイベントの開催実績があった。この2つに「健康」のテーマを加えた「FUKUOKA ハッピーフェスタ 2020」の第1回目を今年、企画していた。
開催の4月下旬が近づくにつれ、「開催するか、中止か」の決断を迫られることになったが、同社社長の水田怜氏は、「中止にするにしても、開催するつもりで準備を進めよう。それが来年のより良い開催にもつながる」と判断、ギリギリまで開催を前提にした内容が詰められていった。
開催中止を決定したのは、3月26日の実行委員会の会議上。中止は決めたものの、社員の思い入れが強く、水田社長は「ここまで進めたのだから、みんながよいなら、オンラインに切り替えて開催しないか」と切り出した。メンバーの全員が「ぜひ、そうしたい」と賛同。この日から同社としても初めてとなるオンラインイベントの開催に向けて準備が進められていった。
「オンラインイベントを開催するかどうかを考える時に、基本に置いたのは、“そもそもリアルイベントは何の目的で開催するものだったのか”ということでした。健康に資する情報を発信するという目的だったので、“それならオンラインイベントでも、その目的は実現できるのではないか”ということになりました」(水田社長)。
ただ単に来年に持ち越すことで逃すチャンスはないのかも議論された。折しも、社会全体が新型コロナウイルス感染症拡大懸念で、健康に対する情報を欲している時だった。「今、情報を提供することで果たせる使命がある」との判断が働いた。
実際に、同イベントのコンテンツには、コロナ下で求められている情報も付加される結果となっている。下半身の筋肉をつける運動を紹介するコンテンツは、コロナの自粛続きで運動不足がもたらす不調への啓発と生活の中で取り入れやすいものを紹介。そのほか、「マスクを付けている時のお勧めメイク法」などもある。
“前例がない”、協賛企業は半減
社員の思い入れが強かった背景は、もともと、イベントの準備が社員による“自前”で行われていたこと。イベント企画会社への委託とは、社員の熱の入れようが違っていた。今回のイベントサイトのデザインや構成も、普段店頭の販促ツール作成を手掛けている社員など、同社社員が考案した。あとは、デザインに従った動画の編集は、起業家支援の意味もあり、地元・福岡のベンチャー企業に依頼した。
開催にこぎつけるまでの苦労はなかったのか。
「苦労と感じることはなかったですね。社員が“ワクワクする”と言って楽しんで進めてくれていたので。協賛企業はリアルでは100社を予定していましたが、オンラインでは50社と、半減しました。“前例がない”と、慎重な企業があることはありました。しかし、“これからデジタルトランスフォーメンションの時代に向けての準備にもなる”と共感してくれる企業が多かったことも事実です。あとは今後の課題として、開催期間の2か月間で、目標としている5万人の集客までつなげられるかどうか。企業に協賛してもらっている以上、ここはクリアしなければいけない課題です」(水田社長)
ギリギリまで準備を進めていただけに、コンテンツに関してはリアルで展開しようとしていた内容を動画撮影するだけだったという。撮影スタジオは同社の会議室。まさに手作りで、熱意がなければ実現には至っていないだろう。
リアルとオンラインが融合される
来年にはコロナも終息しているだろう。「来年は無事、リアルでイベントが実施できますね」。水田社長にそう聞くと、意外な答えが返ってきた。
「いえ、リアルとオンラインの両方の開催になるかもしれませんね」
どういうことなのだろうか。水田社長に聞くと、「今後はリアルか、オンラインかは顧客が自分の都合によって選べる時代になるのではないか」との感触を持っているのだという。
「今まで唱えられてきた“O2O”(オーツ―オー、Online To Offline)は、オンラインをきっかけの一つにしてオフライン(リアル店舗)に顧客を呼び込もうという概念でした。しかし、今、言われているのはその先の“OMO”(オーエムオー、Online Merges (with) Offline)。Mergesは融合するという意味ですが、オンラインとオフライン(リアル店舗)の垣根なく、顧客が自分の都合によってオンラインかオフラインかをいつでも選べる状態になっていくという考えです。まさにオンラインとオフラインが顧客にとって境目なく、融合している状態です。そう考えると、このイベントも、会場に来てもよいし、オンラインで情報を取得してもよい、顧客がよりよい方を選ぶようになる可能性もあると思います」(水田社長)
本部社員は今後も在宅勤務を選べる
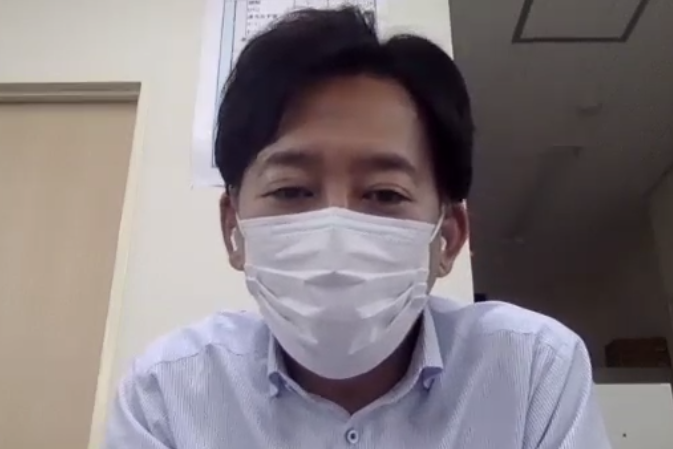
新生堂薬局本社オフィスにてZOOMでインタビューに答えた水田怜社長
こうした水田社長の新しい感覚は、何も今回のオンラインイベント実施に限ったことではない。実は新生薬局では、緊急事態宣言解除後も、本部社員は在宅勤務を選んでよい体制を継続しているのだ。
「社員が自分が最もパフォーマンスの上がると思う状態を選べばよい」と、水田社長はあっさり答える。
リアル勤務しなければいけない社員とのバランスの問題などは起きないだろうか。
「今、在宅勤務維持の体制について、社員にアンケートを取っている最中なので変更の可能性はあります」と前置きした上で、水田社長はこう明かす。
「なぜそうするのか、という部分をしっかり社員に伝えることが重要だと思います。例えば、緊急事態宣言下では当社は本部社員を全員在宅勤務とし、店舗の応援にも行かせませんでした。なぜなら、本部から感染者を出してしまえば店舗を支えるバックオフィス機能が維持できなくなるからです。目的は店舗を守ることだと。だから、徹底した対応を取る、と社員に説明したので、納得を得られたと思います」
「なぜ、そうするのか」
オンラインとオフラインの融合も、在宅勤務維持も、意外に社会で語られない“目的の追求”で根を一にしている取り組みだったのだ。