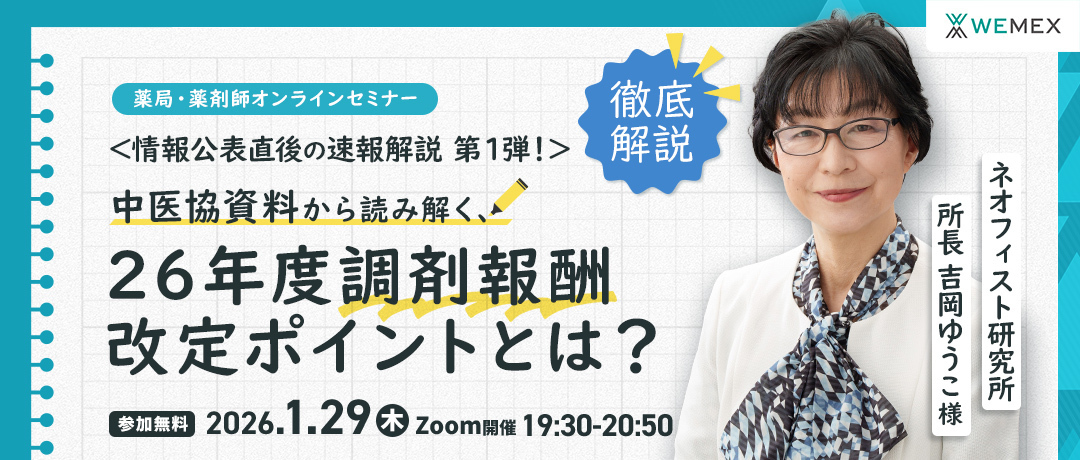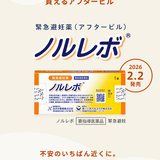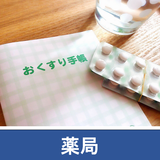同日の会議では一定の成果があった。スイッチOTC化までの工程で1段階を進めたからだ。
現在の検討会議では、「検討会議①」のあとにパブリックコメント(パブコメ)を実施し、その後、「検討会議②」を開催。検討会議としての意見書をまとめて「薬事・食品衛生審議会薬事分科会(薬食審)要指導・一般用医薬品部会」に送ることになっている。
緊急避妊薬に関しては、2021年6月に再要望がされてから10月、2022年3月、4月、と3回の検討会議を開催も、「パブコメ」の工程に移れないでいた。委員から議論に資する資料追加を求める意見などが出ていたたことや、パブコメ案自体も整理に時間がかかったためだ。
それだけ、検討会議での意見が多様であったことの表れでもある。特に専門家から性教育の遅れを指摘する声は根強かった。
そこで、同日開かれた4回目となる「検討会議①」では、事務局は課題を短期的・長期的なものに整理し、さらには検討会議での少数意見だったのか、多数意見だったのかをある程度まとめて意見を策定していく方針を示した。同日の「検討会議①」をもって、パブコメ実施に移ることが了承された。
実際の最終的な検討会議としての意見書は、パブコメを経て、「検討会議②」でまとめられることになるが、事務局が前述の方向性を示したこともあり、同日の会議では大きな課題であった性教育などについても長期的課題として、スイッチ化とは「同時並行」で進めるべきとの意見が出始めた。
日本医師会常任理事・宮川政昭氏は、緊急避妊薬に関する正しい知識を伝えていくためにも「医療が介在して守っていかなければいけない」と、なお慎重な対応を期すべきとの考えを表明。課題として、薬局の販売体制や研修、医療機関やワンストップセンターとの連携、加えて一般用医薬品に移行しない仕組みなどを挙げた。性教育に関しても「実効性担保を文科省にしっかり注文をつけていき文科省にも受けて立っていただきたい」と拡充を求めた。一方で、「とめるわけにはいかない」とも語り、「同時並行でいくためには仕掛けを実際にどうやって動かしていくのか知恵を絞っていくことが大事だろうと思う」と述べた。
また、日本産婦人科医会副会長の前田津紀夫氏は、緊急避妊薬をOTC化した場合も、「薬剤師の介在が必須」との考えを示した上で、現在のオンライン診療に関わる調剤の研修内容に関してはOTC化を前提としておらず不十分との考えを表明。「(現在の研修内容は)薬剤師の先生がたにも責任が発生する研修内容には至っていない。研修内容を変えていただかないと」と述べた。
加えて、要指導医薬品にとどめる制度も求めた。「数年ののちに一般用医薬品に自動的に変わっていくという仕組み」では、「手放しで賛成できない」とした。追加意見書でも医会は「スイッチ OTC と一般用医薬品への移行とは分けて議論すべき」とし、「緊急避妊薬については、要指導医薬品として継続できる例外的な措置をとることが望ましい」として、特性に合わせた柔軟な規制改革制度の適用を求めた。
さらに医会は「販売後に正しい避妊に結びつけることが重要」との意見を示した。これは販売後に産婦人科医に確実につなげる連携体制などを求めているとみられる。
「BPC創設」も長期的課題か
こうした中で、短期的、長期的課題は何だろうか。
短期的課題はまさに緊急避妊薬を薬局でも入手できるOTC医薬品にすることだろう。その中で薬剤師の研修拡充や医療機関につなげる連携体制担保の仕組みをつくっていくことが考えられる。
長期的な課題としては、薬剤師だけが扱えるBPC医薬品というカテゴリーを創設する必要があるのではないかという検討が挙げられる。BPCは「Behind the pharmacy Counter」の訳。緊急避妊薬のスイッチにおいては、BPC創設の検討が必要との意見が出ていた。
さらに長期的課題として、性教育拡充を筆頭とした社会的環境の整備も挙げられる。
これまでの会議の中では、我が国では中学生に性交や性交すれば妊娠する可能性があること、そして中絶についてなど学校教育では十分に取り入れられていないとの指摘があった。こうした課題についても、検討会議の意見書として明記していくことの意味は小さくない。
さらに我が国の性交同意年齢が13歳と諸外国に比べて低いことなどの指摘もあった。
日本産婦人科医会常務理事の種部恭子氏は追加意見書の中で、性交同意年齢の引き上げのほか、「子どもの性的搾取に緊急避妊薬を悪用するものへの処罰規定を設けるべきである」とした。加えて「未成年者が親権者同意なく医療に同意できる年齢について議論し立法を目指す場を設けるべき」とも提起している。
リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(SRHR:性と生殖に関する健康と権利)に関わる問題として、議論されてきた緊急避妊薬のスイッチOTC化の議論。女性にとっての権利、自己決定権、基本的人権に関わる問題であるだけに、「OTC化」という出口だけに矮小化することなく、社会環境の問題も進展する契機とすることが、この検討会議が長い時間をかけて議論してきた意味にもなるのではないだろうか。