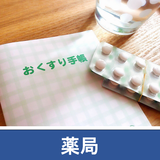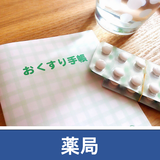連合「制度ごとではなく総合的な議論を」
同日の部会では、「診療報酬改定の基本方針について(前回の振り返り)」が議題の一つとなった。
冒頭、事務局は診療報酬改定と医療保険部会の関係を改めて説明。
診療報酬改定は、予算編成過程を通じて改定率は内閣が決定し、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会では「基本方針」を策定し、それに基づき中央社会保険医療協議会において具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議が行われるものと説明した。
その上で、前回の「令和2年度診療報酬改定の基本方針」が確認された。
前回は「1医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」「2患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」「3医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」「4効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」が基本的視点としてまとめられていたことが紹介された。
このうち、「2」の「具体的方向性の例」として、「薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化」が記載されていた。これが調剤料の見直しとフォローアップを評価する調剤後薬剤管理指導加算につながったことは記憶に新しい。中医協の議論と並行して社保審の議論は注視しておく必要がある。
まず意見を述べたのが、全国知事会社会保障常任委員会委員長(鳥取県知事の)平井伸治氏。保険料の在り方について、「医療費の額と連動して保険料が簡単に増加してしまう方式に関しては慎重な検討をお願いしたい」と話した。
日本労働組合総連合会(連合)副事務局長の石上千博氏は、医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進が前回同様、引き続き重要との考えを述べた。「制度別の議論では解決が難しいため、総合的に議論いただきたい」と要望した。
薬剤師会・森氏「医薬品のサプライチェーン全体の評価を」
健康保険組合連合会副会長の佐野雅宏氏は、感染症に対応できる医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの推進は「これまで以上に重要」との考えを述べた上で、「団塊世代が後期高齢者となる中、2022年度診療報酬改定では制度の安定性、持続可能性の確保の観点から、効率化・適正化の取り組みは非常に重要」と述べた。
コロナの特例的な診療報酬上の評価については、「まずは補助金と診療報酬の役割の整理、また特例的な対応の検証が前提条件となる」として「しっかりとした対応をお願いしたい」と述べた。
対して、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「全体を通して、前回の基本方針の継続が必要」との考えを示した上で、「前回策定時との違いは、新型コロナウイルス感染症の拡大ではないかと思う。薬局では感染予防対策をしており、ウィズコロナの中での医療提供体制確保への対応が一番の課題」と述べ、コロナ特例の継続を要望することを示唆した。
また森氏は、医薬品の安定供給スキームなどが策定されていることを紹介し、「このスキームを実効性のあるものにしていくことが重要」との見解を示した。
さらに、「医薬品の安定供給のためにはサプライチェーン全体の機能を評価すること、その仕組みを支える視点が重要と考える」と述べた。
その面で、昨年の薬価の中間年改定の影響を懸念。「医療の質向上につながったのか、関係者への影響はどうだったのかの検証が必要になっている」と述べた。
かかりつけ薬剤師に関しては「引き続き機能の推進が重要」とし、「患者に対する薬物療法有効性・安全性を確保するため、服用薬剤の一元的・継続的管理な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を推進し、評価していく必要が今後も必要となってくる」とした。
経団連「コロナ特例は平時でも続けられるべきことなのか」
日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会長の本多 孝一氏の代理として出席した参考人は、次回の改定はコロナ対応という緊急的な対応下となるとの認識を示した上で、「一方で中長期を見据えると、高齢化や現役世代の減少は構造変化は不変であり、社会保障制度の持続性の確保は重要」とした。「例えば急性期の入院は将来の医療需要の変化見合った提供体制を目指して改定をしてきたがこれは継続していく必要がある」とした。
「コロナで明らかになった平時と緊急時の体制のあり方については目配りをして対応していく必要がある」とした。かかりつけ医の対応や緊急時の役割分担などを議論する必要性を指摘した。
コロナの診療報酬上の特例的な措置については、「平時においても講じられ続けるべきものなのかどうか。さらには平時を想定して保険制度が成り立っているもので、これを保険制度の中で賄っていくことがよいことなのかどうかについても検証を行っていくことが重要」と話した。
薬価改定については懸念も表明。「適正化すべき点と評価すべき点のメリハリのある改定が重要ではあるが、適正化は薬価に起因することが大きいが国内の創薬力を評価することも医療の基盤であるため必要な対応を行うべきだと思う」とした。
オンライン診療に関しては、「活用する意義がコロナでさらに高まった。こうした新しい技術を活用していくことも重要。対面診療等の報酬との違いが阻害要因となっているのであれば検討をしていく必要がある」とした。
全国後期高齢者医療広域連合協議会会長(多久市長)の横尾俊彦氏は、6つほどテーマを挙げた。マイナンバー活用を筆頭にしたICT化推進の評価、地方の病院を支える方策、かかりつけ医への配慮、訪問診療への配慮、AIやICTへのサポートなどだ。
医師会、後発薬の国内製造の必要性を指摘
日本医師会副会長の松原謙二氏は、欧米に比べて多いといわれてきた日本の病床数に関して、「余裕がなければ難しい感染症対応はできなかった」との見解を述べた。
また、後発医薬品に関しては、「財政的に重要なこと」としつつも、国内で製造する必要性を指摘。「海外にばかり依存していると、各国のトラブルに関連して日本の医薬品がなくなるということが起きるので対応をお願いしたい」と述べた。
医師の働き方改革に関しては、「単純に働いているだけでなく、十分研修させてあげたい。もっと勉強したいのに働き方改革でできずにつらいという声を聞いている。働いている時間だけで切るということでなく、研修をさせてあげることは重要」と話した。
「一番の負担は医師が事務的な書類を書かなければいけないということ。医師でなければいけないことと、事務で対応できることは事務でということを行う必要がある」と指摘した。
オンライン診療に関しては、「対面で問診だけでなく触診や検査もしなければいけない」とした。
かかりつけ医については、「相談できるかかりつけ医を持つことは重要だが、法律で決めて制度化すると海外のように専門医にかかるまで時間がかかるということになりかねない。患者にとってはフリーアクセスが重要。大病院には集中しないようにかかりつけ医が対応している。制度化するのではなく、かかりつけ機能をさらに増進させる考え方で進めてほしい」とした。
日本慢性期医療協会副会長の池端幸彦氏は、コロナ対応の経験から、病床は多くても人員配置に余裕がないことが日本の問題だと指摘した。「コロナの患者をみようとすると何人もの看護師が対応しなければいけないこともある」とした上で、多職種配置について検討すべきだと提言した。「医師や看護師、薬剤師のほか、管理栄養士や看護補助者や介護士も必要になっている。どんな時でも対応できる病床というのはどれぐらい必要なのかを検討しながら、こうした多職種の配置を検討してほしい」とした。
オンライン診療に関しては、「あくまで対面の補完という前提を逸脱してはいけない」との見方を示した。
*********
<編集部コメント>
「診療報酬改定の基本方針について(前回の振り返り)」と言いつつも、薬局に関連するテーマとして、いくつか“新しい玉”が投げられている。
一つの重要なテーマは、調剤報酬では4点のいわゆる「コロナ特例」の継続だろう。ぞれぞれの立場によって、見解は分かれているが、通常業務に加えてコロナワクチン接種の準備に協力もしてきた薬局現場の苦労をみている限り、シンプルな延長はあってよいのではないかと思える。「補助金との役割との整理を」との意見も分からなくもないが、補助金は「かかった経費」の補填の側面が強く、既存の従業員の手間や労力など、金額に出にくい部分が補填されにくい。申請の手間で業務を煩雑化させ、条件も厳しいため、診療報酬上の手当が現場の支援には最も適していると考えられる。
一方、“新しい玉”としては、日本薬剤師会の森氏が「医薬品のサプライチェーン全体の評価」という言葉を診療報酬の基本方針への意見として述べたことだろう。
これはまさに、コロナ禍での明るみに出たサプライチェーンの問題と後発医薬品の不祥事への対応という、前回にはなかった検討事項となる。
森氏の紹介した「医療用医薬品の供給不足時の対応スキーム」では、「安定確保医薬品」において供給不足の可能性が発生した場合に、市場のシェアや同種同薬効のリスト化などの情報を経済課に集約し、企業と協力して対応にあたるようにしている。
同種同薬効で対応が可能な場合は、医療現場、医療関係団体等に同種同効薬や代替療法等により対
応してもらえるよう経済課から依頼するとしている。
この場合などには、薬局が医師と連携して代替療法に対応することになるだろう。
これはすでに後発医薬品の供給不足において、一部、起きている事例ではないだろうか。
深読みすると、これらの対応への報酬上の評価によって体制を支える必要性が出てきていることを示唆したとみることもできるのではないだろうか。