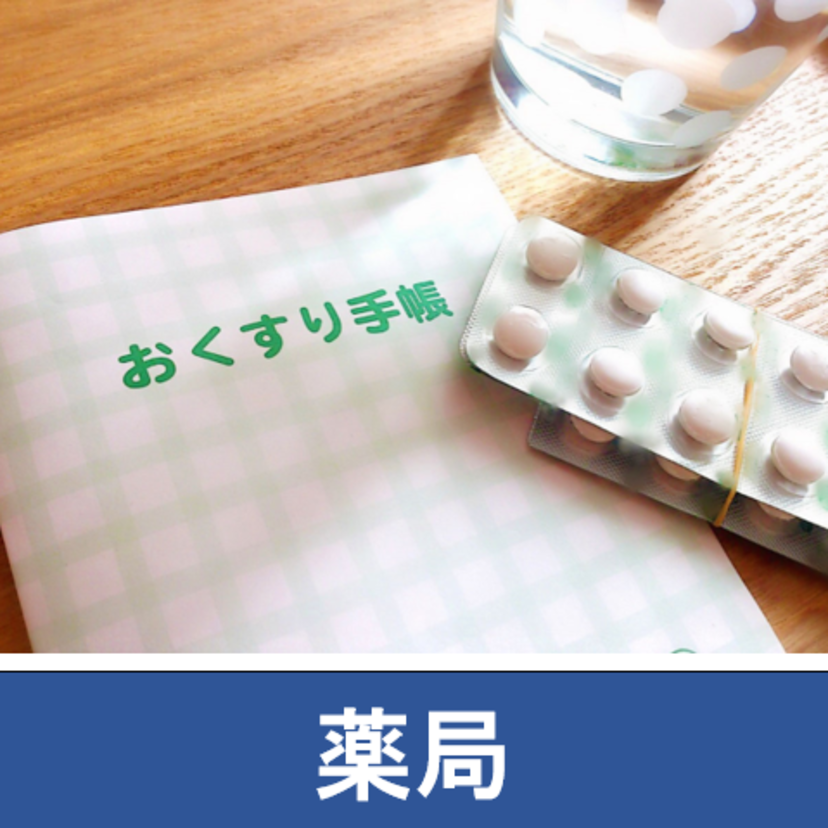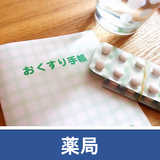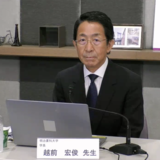感染症予防や情報技術を生かす能力の記載には評価
今回の改訂内容に対し、薬学教育に関わるある関係者は、「目指した内容には到達していない」と指摘し、「道半ば、いや3分の1程度ではないか」と改訂内容に対してコメントする。
無論、今回の改訂に向けた関係者の長い議論が無駄だったわけではなく、例えば、「A」の「薬剤師として求められる基本的な資質・能力」の項には「プロフェッショナリズムとして発展」を書き込み、この「A」項目を単なる1科目ではなく、全期間の薬学教育において関連性を意識することとしたことには評価の声がある。
また、「E」の「衛生薬学」の部分は、新型コロナ流行を受けて、感染症の予防やまん延防止に係る内容の充実を記載した。「B」の「社会薬学」には「情報・科学技術を生かす能力」を記載。「C」の「基礎薬学」に関しては各所に「基礎をなすもの」ということを意識した文言を入れた。この背景には、薬剤師として基礎薬学の最先端研究を目指すのはいいが、それだけでは薬剤師としての基本的資質能力を備えたとは言えず、「基礎薬学に裏打ちされた専門性の発揮」を求めたものといえる。
「公衆衛生薬学」の大項目への明記かなわず
一方、関係者が期待をして記載まで至らなかった領域の筆頭として、公衆衛生がある。これまでの薬剤師の養成に関する厚労省の各種検討会では教育現場から公衆衛生における教育が不足していたとの発言もあり、今回の改訂での拡充は大きな課題となっていた。
しかし、「公衆衛生薬学」という文言を大項目として記載することには至らなかった。「衛生薬学」の大項目にすでに含まれているとの意見が出たためだった。
こうした変化への歩みの遅さに焦燥感を抱く関係者もいる。ある関係者は、次のように指摘する。
「検討会の中でも委員から“一般から見て薬局の役割が見えにくい”との意見が出ていた。医師の診断を受ける前の人にアプローチすることも薬剤師の仕事であるし、薬局にはさまざまな役割がある。それを外から見えやすくすることも改訂の大きな意味でもあると思うが、決定権を持つ人たちの中に前例主義や仲間内感、責任回避の思想があるのではないかと思う。薬剤師は誰のために働いているのか、誰の利益を第一にするのかを考えれば、自ずと答えは出るはずだが、それを阻止するものは幾つもある。書かれたものを金科玉条にする思考をどこで手放すかが問題で、臨床現場を知らない教員が物事を決める危険性を感じる。今回の改訂で大きく変化した部分はあると思うが、まだまだ道半ばというか、3分の1以下ではないか。次回の改訂への課題を残したと思う」とする。
一方、同氏は教育現場と実際の医療現場の連携も無視できない観点として指摘する。
「現場が先をいっていないとコアカリも変わりようがない、という意見も委員からは出ていた。その通りだと思う。心ある活動を進める薬剤師は増えつつあるが、それをきちんと大学教育に反映できているか、またそれを職能団体が覚悟をもってサポートすることができるかも、今後の課題だと思っている」と語る。
編集部コメント
卒後研修の話題、卒前と卒後の一貫した取り組みの必要性が指摘される中、実業界である医療現場が教育への関わりをさらに強めなければいけない局面であることは、誰もが否定しないであろう。今後の取り組みの進展に期待したい。