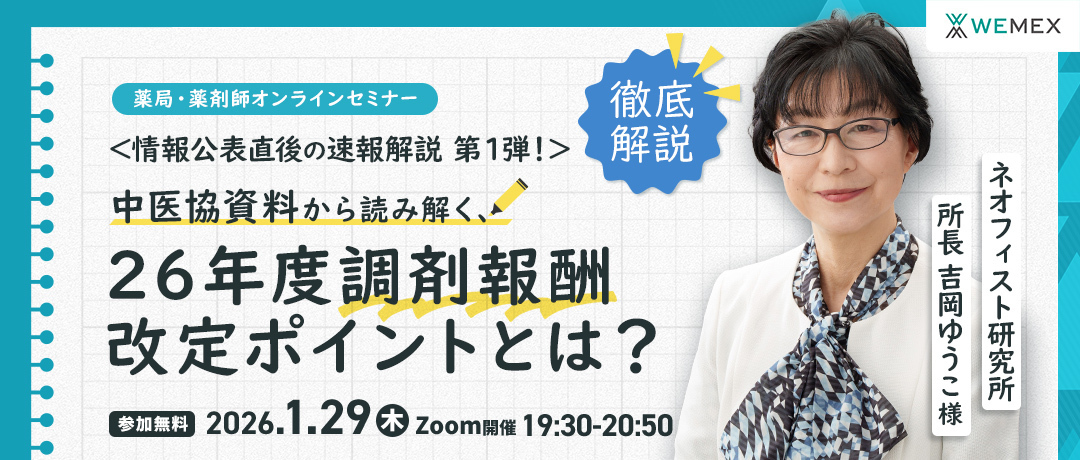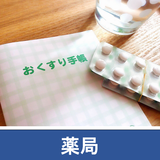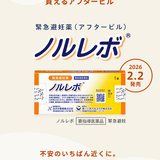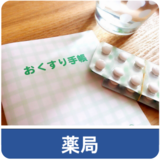全国自治体病院協議会・貞弘光章氏「問題は1社流通を解決してからではないか」
同日の流改懇では、個々の医薬品の価値に見合った薬価形成となるよう、「総価取引」ではなく「単品単価交渉」を推進する方向で、単品単価交渉の「定義」を定めることなどが議論された。「妥結率等に係る報告書」に関しては、新たに、卸が確認した内容を医療機関・薬局に提出する方向とするとした。「妥結率等に係る報告書」は、令和6年度診療報酬・調剤報酬改定において単品単価交渉等の流通改善に関する項目が追加になっていた。「報告書」は医療機関や薬局が厚生局に提出するもので、卸が医療機関・薬局に伝える内容は厚生局に提出するものではないとした。
単品単価交渉の定義については、「単品単価交渉と解釈できるか検討が必要な場合」の整理も必要とし、事務局は次のような事例を列挙した。
(1)チェーングループ(同一グループ)における取引価格の本部一括交渉について
複数の施設を展開しているグループ企業等においては、価格交渉が本部一括で行われた上で、各施設における医薬品の取引価格は、同一であることが一般的と考えられる。そのため、薬価が統一価格であることを踏まえ、取引価格を決めるにあたり、同一グループ施設の地域差や取引条件等を考慮し、品目ごとにその平均額に基づいた価格交渉であれば、単品単価交渉と解釈することとしては如何か。
(2)法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について
加盟施設(医療機関・薬局)ごとに法人格・個人事業主が異なることから、例えば、施設ごとに取引条件が異なる場合は、特に留意が必要と考えられる。そのため、取引価格を決めるにあたり、加盟施設ごとに地域差や取引条件等を考慮し、加盟施設の確認の下で品目ごとの価格交渉が行われているのであれば、単品単価交渉と解釈することとしては如何か。
(3)いずれの交渉(上記(1)及び(2))も「総価値引率を用いた交渉」や「全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉」の場合は、単品単価交渉とは考えがたいのではないか。
(4)その他、単品単価交渉と解釈するにあたって、検討を必要とする交渉にどのようなものがあると考えられるか。
こうした議論の中で、医療機関・薬局側からは懸念も示された。
「薬価は全国共通であるのに“地域差”を容認するように聞こえる。慎重に扱っていただきたい」(全国自治体病院協議会・貞弘光章氏)。
「川下のことばかり言われているが、単品単価交渉以外の交渉では“メーカー別や商品カテゴリー別の値引き率で交渉が行われる場合”とされている。卸さんにおいても今後、こういった提示以外をお願いしたい」(日本保険薬局協会・原靖明氏)。
「意図的限定出荷などがなくなることが単品単価交渉の基礎。努力していただきたい」(日本医師会・宮川政昭氏)。
定義や報告書の見直しについては大筋で了承とされ、関係者間ですり合わせを行なっていく方針となった。
こうした議論の中で、医療機関・薬局側から懸念として多く指摘が出たのがメーカーが卸を1社に限定する「1社流通」だ。
全国自治体病院協議会・貞弘光章氏は、「問題は1社流通を解決してからではないか。順番として。医療側としてはどんどんモノ(医薬品)が増えてきている。高額品だったり。それが価格交渉ができないということで。1社流通品を本当に単品単価の土台に乗せていいのかと。川上(メーカー・卸)の1社流通も明瞭にして、川上側の努力も一緒にしていただかないと、ここは一方的かなと思う」と述べた。
日本保険薬局協会・原靖明氏は、「単品単価交渉を進める中で今、逆ザヤが起きているという声が会員から多く出ている。これだけ物価が値上がりしていて、電気代もガソリン代も上がって、それをコストオンして小売さんは値上げしている。(一方で公定価格である薬価では)最低薬価も変わっていない中でメーカーさんも大変なんだと思う。最低薬価のあり方など薬価自体の問題も起きている。不採算品についてもどうやってもどうにもならない状況なので、まずそこを考えないといけないのではないか。その上で1社流通品の話もある。(限定されている)卸さんと違うところから買うと、逆ザヤになってしまう。しかも薬価が高いものが1社流通品になっていたりすると、技術料を超えてしまうことになったりしてしまう。逆ザヤの問題は大きい」と述べた。
日本薬剤師会・豊見敦氏、1社流通の情報提供は「求めた場合に提供されるということではないのでは」
また、さらに「1社流通」の議論が過熱したのが、流通改善ガイドラインの遵守状況をフォローアップするためのアンケート調査について議論した時だ。
事務局はアンケート調査表のイメージを提示した。
この中で、医療機関・薬局へのアンケート項目として「一社流通を行う医薬品メーカー・卸売販売業者の情報提供の実施状況」を掲げ、「1社流通の理由について情報提供を求めたところ、適切な回答がなかった品目の名称」などの回答を求めた。
これに対し、日本薬剤師会の豊見敦氏は、「1社流通の情報提供は流通ガイドラインでも安定供給のために必要と理解をしている。その点で考えると、情報提供を求めた場合に情報が提供されるということでなく、1社流通を行う場合は情報提供を行う必要があるとわれわれは理解をしている。加えて、情報提供があったかだけでなく、安定供給に支障がなかったかという点も重要ではないか」と指摘した。
日本保険薬局協会・原靖明氏「メーカにとって、“卸さんに出庫したんだからもういいでしょ”ということではない」
日本私立医科大学協会の小山信彌氏は、「1社流通の話が出てから2年近く経つと思うが、いっこうに減っていない、逆に増えている。うちの大学でちょっと調べたら100品目ぐらいある。どんな説明を受けているか担当者に聞いたら特殊な保冷の仕方など、これはわかると。もう1つは、これはほとんどと聞いているがモノの把握がしやすいと。1社流通の定義も問題で、地域別の1社流通もある。単品単価の定義の話が出たが、1社流通の定義もやっていただきたい。病院も公立では赤字が半分とされる中で価格交渉は重要。2000品目は不採算などで価格交渉してはいけないとか、早期妥結で全部しろとか、言われているが、ではメーカーは何をしているのと。1社流通でさらにいじめるのと。もう少しちゃんとした形が出ると嬉しい」と述べた。
日本保険薬局協会・原靖明氏は、「安定供給の定義とは何か、から始めないといけない。今日頼んだものを今日入れてくれとまで言わないまでも、1週間経たないと入らない状況が起きている時に、安定供給といえるのか。これがどれくらい患者さんに影響を与えるのか。メーカーさんにとって、“卸さんに出庫したんだからもういいでしょ”ということではない。しっかりその医薬品が全ての医療機関・薬局に届くような供給網を持っているところにお願いをしているということであると認識している。それは果たして叶えられているのかが重要。豊見先生が指摘された通り、1社流通の情報はメーカーさんの方から来るものだとわれわれも思っている。少なくとも新規納入先はわかると思うので、説明責任があるものだと思っている。1社流通の卸さん以外に注文して初めて1社流通だとわかるのでわれわれは1社流通がどれかわからないことが(購入側に1社流通の問題を聞いている)アンケート回答の問題点だ。加えて、問題は普段買っている卸さんから“これはウチからは入れられません”と言われた時に、“じゃあどこから買ったらいいですか”と卸さんに聞いても、メーカーさんに聞いても答えてもらえず、どこから買ったらいいかわからないことが現場で起きている。これは安定供給上、大きな問題ではないか。交渉以前の問題であり、1社流通はいいのか疑問に思っている」とした。
日本製薬工業協会・武岡紀子氏「個社とか、個々の製品について法令を違反していないものに対して、われわれの方で取り調べることはできない」
全国自治体病院協議会・貞弘光章氏は「1社流通の理由を卸の方に聞くと“メーカーから言われました”と答えられない。卸に理由を書いてと言っても卸側はできないかもしれない。コンプライアンスの問題もあるのかもしれない。1社流通が高額であったり新規であったりするのでクローズアップされてきている。医療機関は解決できていない」と述べた。
こうした議論を受け、日本製薬工業協会の熊谷裕輔氏は、「1社流通に関して、まず使命として安定供給を果たしていく。それから説明責任を果たしていくことは非常に重要。当初は温度管理とかオーファンから始まった1社流通だが、新しいモダリティなどが出てきて少し広がっている状況というのも認識している。1社でお願いする時にはきちっと安定供給ができるという契約を結んでいるとはいえ、まだまだご迷惑をおかけしている点があるのでここは業界内でも徹底していきたい」と述べた。
日本薬剤師会の豊見敦氏は、「1社流通の問題は、医療機関側へのアンケートの中に(項目が)入っているが、今のお話をうかがっていると卸・メーカーの方へのアンケートの中にこの項目が必要だと思う」と提起した。
日本私立医科大学協会の小山信彌氏は、「まさに(豊見氏が)指摘した通り。メーカーの質問はなくていいのか? 川下からいろんなことを聞くのはいいが。川上は何もしていないのでは。ここをちゃんとしていただかないと。われわれずっと苦労したままで大変ということになる」と疑問を呈した。
日本保険薬局協会・原靖明氏は、「小山先生のおっしゃる通りで、上流が濁ると、川下がいくら頑張っても濁ったままになるので。アンケートで問題が起きたことをアンケートとるのではなくて、1社流通に関してこれだけ話題になっているのであれば、どういうものがどういう理由で1社流通にしているのかメーカーに聞いていただきたい。 それを見ることによって全体像がわかるということになり得る」と述べた。また「先ほどのメーカーさんが卸を答えることに関して、何か違反になるのか」と質問した。
これに対し、日本製薬工業協会の熊谷裕輔氏は、「取引誘引など取引に関与することができない」と回答した。
日本保険薬局協会・原靖明氏は、「1社流通だったらそこに誘因されているのではないか」と疑問を呈した。
日本製薬工業協会の熊谷裕輔氏は、「価格交渉ができる、安定供給ができるということを踏まえている」と答えた。
日本保険薬局協会・原靖明氏は、「結局、薬局は(1社流通品の限定されている卸を)どうやって調べたらいいのか。非常に大きな問題になっている」と提起した。
日本製薬工業協会の武岡紀子氏は、「われわれは個社とか、個々の製品について法令を違反していないものに対して、われわれの方で取り調べることはできない。アンケートを通して、もしくは厚生労働省の窓口を通して問題を明らかにすることで改善していければと。ただ、製薬協の委員としてお約束できるのは、会員のメンバーに対して、患者さんの命に関わる医薬品を提供するものとして、安定供給すること、丁寧に情報提供すること、そして大切な医療資源を適正に扱うこと、これを繰り返し伝えることは可能だ。ただしわれわれ、やはり限界がある。なので私からの切実なお願いとしては、製薬協だけで流通改善はできない。ぜひみなさまのご協力をお願いしたい」と述べた。
日本医師会・宮川政昭氏は、「武岡委員の切実なお願いだが、誰がそれをできるのか。一番の最上流は武岡委員のところ(製薬企業)しかない。どうやってディスクローズしていくのか。どういうプロセスでなら回答にたどりつくのかも示していただかないといけない。アンケートをとっても、その先が見えない。ある程度、ロードマップも考えていただいて。何年も前から私たちは言っているのだから。問題点としてどう明らかにしていくのか」とした。
日本歯科用品商協同組合連合会の宮内啓友氏は「製薬協が個々の会社の調査ができないということなら、厚生労働省に乗り出していただいて。1社流通について、高額で保険適用されたものがなぜクローズなるのかと。3年ほど前にトレーサビリティの観点と言われた。3年経ったものがまだ解決されていない。いつそれが開放されるのかまで調べれば、情報公開になる」と述べた。
事務局は議論を受け、「公定価格がついている医薬品ということからすれば、全国の医療機関・薬局で使い得る状況にあることは必要。そういうことについてメーカーがどういうスタンスでいるのか、卸がどういうスタンスでいるのか。それが医療機関・薬局からどう見えるのか。念頭に置きつつ、しかし実態を明らかにするということについてどうしても制約がある。今日の議論を踏まえて、メーカー側・卸側・医療機関・薬局側のそれぞれからどういう形で実態を聴取することができるのか、ご相談をさせていただきながら進めていきたい」とした。