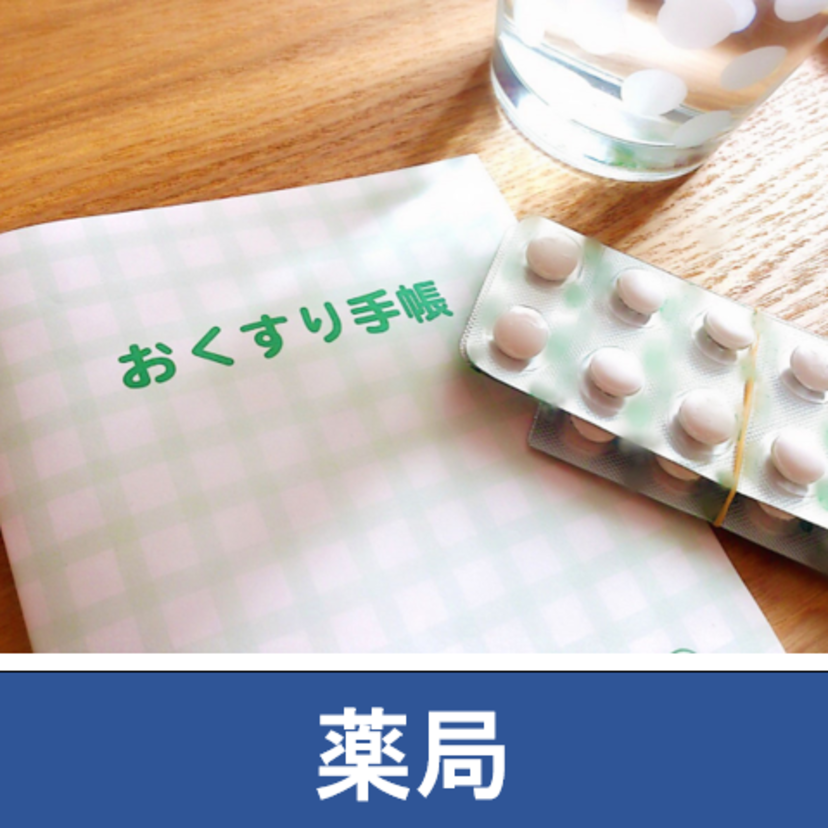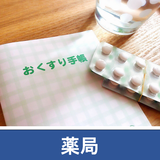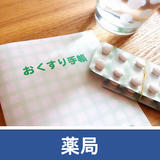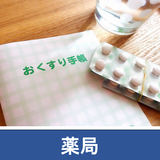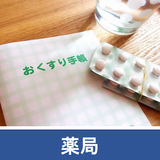地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げるという地域包括ケアの概念、「日本薬剤師会も同じ」
本日はこの後、日本医師会の松本会長にお話をいただく、(私の講演は)前座といいますか、そういった役割だなということを感じております。その前に、私から基本的な方針を皆様方にお伝えをさせていただく、こういう趣旨での企画だというふうに理解をしています。それでは早速、始めさせていただきます。
皆さん、よく見られている(人口推移の)数字でありますが、高齢化とともに総人口が減っていきます。いったん、令和4年に高齢化率(の上昇)がいったん止まりますけれども、これから、いわゆる団塊の世代も含めて、高齢者が増えていく。人口はもうピークアウトしていますので、こういった(人口減少・高齢化進展という)状況というのが、これから我々の社会のすべての分野で起こるということは、改めて感じておかなければならないと思います。
人が減ってくると何が起こるかというと、まず市場が小さくなりますよね。マーケットが縮小していきます。マーケットが縮小してくるということは、給料がそれなりに上がらなければ、所得も減っていきますので税収もそんなに伸びないはずですよね。すべてがシュリンクしていくという世の中は、日本は戦中、戦後、あとは大正デモクラシーの時代とかに、そういうシュリンクをする社会の経験していますけれども、実は初めてではないかと思うんですね。経済とか社会全体が縮小する傾向にあるところで国をどうやって運営していくのかっていうのは多分初めての経験だと思いますので、そこに対して政府は色々と先を見据えていろんな対策を打っているというふうに理解をしています。
ですから、規制改革なんかもそうなんですけれども。規制改革というのは効率化の追求ですよね。人が減っていくんで、少ない人数でまわそうとか、利益が少なくなるからどこで利益を出そうとか、人件費をおさえようと、そうなると機械化とかAIだとかっていうことを考える。効率化というのは、ある程度規模がないと達成できませんので、中間地であるとか、山間・僻地・過疎地といったところは効率化の対象から外れてしまいますから、どうやってそこに手を差し伸べていけるのかということが我々、医療とか介護とか福祉だとかっていう世界では、必ず答えを出していかないといけない課題だと思っています。
そこで考えられましたのが、地域包括ケアシステムでありまして、案内のように、来年が一つの目標年度になります。住まいと医療と介護予防生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築というのが目標でありますので、これに対して、これに関係する方々はどういったサービスを提供して、地域の方々に安心して暮らしていただけるということを提供するんだということになります。
高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。これも皆さんもよくお分かりですよね。私が住んでいます愛知県の刈谷市というところは、トヨタ系の大きな企業が6社ぐらいあるところでして、税収も非常にいいところで、高齢化率は低いです。ただこれだけの企業城下町でありますので、独身男性が非常に多くてですね、女性が少ないという歪な人口構成の街でもありますけれども、そういったところと、例えば昨日(の学術大会中に)もお話がありましたけれども、埼玉県の秩父方面ではですね、全然、状況が違いますよね。そうすると、その状況の違うところでやることを、例えば日本薬剤師会で「全国一律にこうしましょう」とか、都道府県薬剤師の中でも「県で一体的にやりましょう」ということが、なかなか通らなくなっていく。中央集権的な運営ができにくくなる、そういうこともお分かりいただけるんだと思っています。
ですから保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて(地域包括ケアを)作り上げていくことが必要です。
全く日本薬剤師会も同じだというふうに思うんです。
(地域包括ケアでは)介護・リハビリテーションとか医療・看護だとか保健・予防、こういったサービスが、住まいと住まい方、本人・家族の選択と心構えの上に、提供されるということであります。予防ですとか生活支援という、今の介護保険が導入されて、地域で皆さん考えましょうねって言った時に対応が変わってくる。「生活支援・福祉サービス」だったものが、「介護予防と生活支援」、順番が変わっていますけれども、そういったことにも注目しながら、来年の完成年を迎える。
我々は今、どこまでその目標に対してできているのか。当然、国の政策に則って、我々も地域の方々にサービスを提供しているわけでありますから、どこまでできるのかということは来年、日本薬剤師も含めて都道府県薬剤師会もそうですし、もちろん地域の薬剤師会も、自分たちの住んでる地域でどこまでそれができてるのかということは来年、検証しなきゃいかんですよね。
自信を持って「うちは大丈夫」というところがどれだけあるのかということは、たぶん我々だけではなくてですね、色々な業界も含めて、これは注目されることだろうと思っています。
薬局の“自助”として、地域に自薬局のやっていることを示す必要
平成25年の地域包括ケア研究会報告書にありますけれども、自助・互助・共助・公助という、順番で仕事を回していきましょうという概念図であります。自助はここにも書いてある通り、自分のことを自分でしましょう、そして自らの健康管理、セルフケア、これをしましょうと。市場サービスの購入との記載がありますけれども、公的医療保険ですとか公的介護保険制度とは別に、ご自身でやれることであるならば、市場の、民間サービスを使ってもいいでしょう、そういうことですね。一番たぶん特徴的なのがBSの番組とか、あるいはオンラインでCMが入るたぶん健康食品とかサプリの類だと思うんですね。やっていいですよと言うのなら、それはそういう業者が出てきて、そういう市場を形成するというのは、資本主義の世の中で当たり前のことです。ただ適正に運用されているかどうかはチェックが必要だと思いますけれども、そういうことを最初に決めているわけですから、こういったものが出てくるのも、当然世の中の流れだろうというふうに理解をしなければいけないと思います。
次に互助、お互いに、同業社であったりですね、異業種の連携をとって、お互いに助け合って、地域の中でサービスや資源を有効に使いましょうということになります。ここにありますけれども当事者団体による取り組みですとか、高齢者によるボランティアとか、生きがい就労とか、ボランティアですね。お互いに助け合いましょう、一人の困ってる人がいたら残りの9人助け合いましょうというようなことです。我々の(薬局の)世界でも、どんなことがこれに当てはまるのか。我々の業界、薬局、開局薬剤師の中でできる互助とはなんなのか。病院薬剤師さんでできる互助は何なのかということに取り組んでいく。その上で共助、もう少し広域の概念が広がりますし、地域も広がりますけれども、お互いに助け合いましょうと。
最後に国ですとか、地方自治体ですとか、団体を含めた公的、いわゆる保険の給付ですとか、あるいは補助金ですとか、そういったことを利用して困ってる人が出ないようにしましょうと。こういう概念だろうというふうに思っています。
これが薬剤師の世界ではどうなるかっていうのを見てみます。
当然、自助というのは自薬局でありますので、自分で努力してくださいということですね。
じゃあ薬局の努力ってなんでしょうと考えた時に、病院とか診療所というのは外から見て機能分化がわかりますよね。整形外科という看板を標榜していらっしゃれば、骨が折れたり怪我した時に行くんだなって分かるじゃないですか。それが大きい病院であれば、より高度な医療を提供してくれるんだってこともみてわかりますよね。
我々薬局はどうでしょうか。規模の大きなドラッグストアですとか、大規模調剤チェーンさんもありますし、身近にある近所の気安い薬局もありますよね。
しかし、これが機能分化が果たして地域住民の方々に見えてるかというと、おそらくそうではないのでしょうね。機能で分化されていれば、機能によって選択が可能になりますけれども、言いにくいことをはっきり申し上げますけれども、「医療機関の近くにあると便利でいいや」という方が多いのではないか。中には「あの薬剤師は気に入ってるから絶対に調剤してもらう」とかですね、そういうこともいらっしゃらないわけではないと思いますけれども、逆に言うとそれは多分、そこの薬局薬剤師の自助ですよね。努力をして患者さんに受け入れてもらっているということですから、決して地理的要件で選ばれた薬局ではないんだと胸を張っているんだと思います。
そういったことが、今言ったように、外から見た時に薬局の機能がわかるようになっているかと。これはまだまだ自助が足りないだろうというふうに判断しなければいけないと思います。
なので、ここ(プレゼン資料)に「医薬品」“だけ”ではない提供施設と書きましたけれども、たぶん、なんだって提供できますよね。ちょっと前まではタバコを売っている薬局も多かったですし、何でも販売できますよ。ですから、何を提供できるのか。ケアマネジャーがいるとかですね、昨日も分科会で発表がありましたけれども、栄養士さんと契約しているとかですね、理学療法士さんとか言語聴覚士さんとか、その言葉そのものが主語でありますけれども、電話帳に載ってない職業の方々を有機的に結びつけるというのもたぶん、自助の努力の範囲、あるいは他団体との連携があるとか。これは互助かもしれませんけれども。そういったことが自薬局でどこまでできるのかということを示す。地域の住民の方々に「うちの薬局は何をやってますよ」ということを見せるようにしないとですね、なかなかに、自助といっても、今のままでやっていてもなかなか見えないだろうなというふうに感じるところであります。
互助は近隣の薬局。「あの薬剤師さんは抗がん剤が得意だよね、と回せる勇気があるかどうか」
次の互助でありますけれども、近隣薬局が対象になります。近隣薬局をライバルだと思っている、うちの方が処方箋枚数が多いとかですね、そういう思いを持っていらっしゃる方はそんなにいらっしゃらないだろうと思っていますけれども、互助となると、近隣の薬局はライバルではなくて、まあ、お友達ですよね。コンペテーター(競合他社)ではありますけれども、まあ仲良くしてですね、医薬品の融通だったり、患者さんの紹介とか。例えば疾患領域で自分が得意ではない患者さんがいらっしゃったら、「ああ、あの薬剤師さんは例えば抗がん剤強いよね」となったら回せる勇気があるかどうかです。
いいんです、自信があれば自分でやっていただいてもちろん。それは薬剤師の沽券(こけん)に関わることでありますから、それはそれでいいんですけども、ただ、そういったことができるかどうか。
OTC医薬品の貸し借りですとか、医療用薬の融通もそうですけれども、そういったことがちゃんとできるかどうか。自分勝手なことやっていて、地域の、例えば薬剤師の活動に一切参加しないけれども、医薬品の融通だけはお願いね、という人がいるかということも、たぶん、地域の中ではあるんだろうと思うんですね。
これをみんなでどうやってその雰囲気を醸成していくか。これは地域薬剤師の仕事だと私は思います。
日薬でいくら言ったって、地域でやらなかったら、全然進まないわけですから。
これは地域でこれからどうやって関係を作るのか。これからたぶん話題に出てくるでありましょう、地域フォーミュラリーですとか、そんなこともそういう話ですよね。地域でみんなが医薬品情報を共有していればですね、例えばですけれども、新規で開業するドクターがいて、どんな薬を地域で持っているのかがわからないと、どういう薬を出したいのかという情報開示を、1軒の薬局だけに言えば事足りるよねと。そう思っているから門前分業なんですよね。
もし新規で処方箋出しますとか、新規で開業しますとお医者さんに、「地域で持ってる医薬品情報はこれだけです」「こういうお薬あります」「でも先生のご希望があれば地域の薬剤師会で揃えます」といったことを言えればですよ、それでも門前(薬局を)作りたいということが起こるかどうか。こういうことを分業の初期の段階でしてこなかったのは、おそらく門前分業といいますか、今のひとつの(要因)。全部そうですよね、在庫が少なくて済みますし。そういったことでこの20年間、30年間、やってきてしまったんですね。
これが、冒頭申し上げたように、シュリンクしてくるときは、今までのやり方が通用しなくなりますので、どうやったらその減っていく、小さくなっていく市場を効率よく回して、同じだけの収益がなければご飯食べていけないわけですから、こういうふうに考えないとうまくいかないですよね。
在庫を圧縮して利益を出したいからフォーミュラリーと言ってるではないですからね。患者さんに迷惑をかけない、地域で医薬品情報を共有して、薬剤師というものが集まっているんだったら、そこの地域で流通してる薬の情報みんなで共有してますということが目的ですから、そういったことをこれから考えて、地域薬剤師会はハンドリングしていかなければならないと思っています。
それが近隣薬局から広がって、今申し上げたのが地域の薬剤師会の役割だと思います。
地域薬局機能情報の共有。「あそこの薬局はこれが強いよね」とか、先ほど申し上げましたけれども、医薬品については「あそこの薬局は、例えば精神科領域の薬をたくさん持っているよね」ということを共有することが大事だろうと思います。
先ほど申し上げた中山間地ですとか僻地で医薬品をどうするんだという時に、例えばドイツでは、田舎に処方箋ポストみたいなのがありまして、手挙げ方式で「私、今月やります」というと、地域の薬剤師会が処方箋をそのポストに取りに行ってですね、調剤をして患者さんのところに薬を届けるという仕組みをやっているようでありますけれども、箱調剤でありますから、一箱いくらとお金を集めて、地域でそのお金を回してやっているような事例も実はあるようなんです。
じゃあ私たちも1薬局でずっと24時間365日はつらいですよね。犬の散歩にも行けないし酒も飲めないとていうのは辛いですから、じゃあ地域で誰が夜の当番をするのかというのは、この前、ホームページ上でリストを公開しなさいとなりましたけれども、あれをどうやって有機的にこれから運用していくのか。
表は作りました。世間に見えるようにしてました。どうやって運用するんでしょうか。
それを見えるようにしていかないと、「今月この薬局やってます」と。ドイツはご案内のように、当直薬局は新聞に載ってますよね、インターネットでももちろん開示していますけれども。
じゃあつくった表もインターネットで開示してますけれども、ホームページ見に行く人が何人いると思いますか。先生方、昨日も夜、お出かけになられた方は、おそらくスマホでどこかいいところないかな、とお探しになったでしょ。薬局にお見えになる方も同じですよね。夜の8時に空いてる薬局どこだろうって言って今はもも話しかけて、「Hey,Siri」とか言ってですね。「この近所で夜8時までやっている薬局を教えて」とて言ったら出てくるんですよ。そういう情報の中に載れるかどうかですよね。
「いやホームページで公開してますよ」って言って、薬剤師会のホームページを見に行く人がどれだけいるのかって考えるとですね、本当に大丈夫かとも思うわけですね。
無薬局地域の問題など、必ず「どうするんだ」と求められる。やらなければ規制緩和に
それから、共助は都道府県薬剤師会になります。
県は県の規模で、いろいろ県との折衝もありますし、補助金の話もあるでしょう。過疎地や遠隔地をどうするのかということもたぶん議題になってくると思うんです。
私の出身である愛知県薬剤師会では、実は無保険薬局の中学校区が11もあります。1軒しかないところが8区あります。言ってみれば1軒なくなると、無薬局になってしまうのが全部で19中学校区になります。まあ中学校区ですから、そんなに広い範囲ではないんですけれども、どうするか考えなきゃいかんですよね。
こういうことがこれから必ず求められる。すぐじゃないですけども、人口減少と高齢化の進展に伴って、必ず「どうするんだ」ってことが出てくると思うのです。
やらなかったら、行政にしてみれば、誰がやってくれたっていいですよね。そもそも行政サービスじゃないかという意見があるぐらいですから。その行政が、今はやっぱりシュリンクしていく経済状況の中で、あるいは人口減少の中で、どうやって行政効率を上げていこうかと考えた時に、民間がやってくれるなら民間にやってもらいましょうってなりますよね。
薬の配達、薬剤師会がやらないんだったら業者頼むわっていうことになるかもしれませんよね。
それで、やろうとした時に薬機法とか薬剤師法というのが規制で阻まれているというふうに考える人が出てくればですよ、この規制撤廃しましょうって話になりますよね。
われわれは、コロナ禍であれほど頑張ってマスクだとか消毒薬を提供したのに、終わってみたら、スーパーとかコンビニとかで、マスクも消毒もみんな売ってますよね。
努力したってそうなってしまうんですよね。
たぶん、薬局で買いにくかったという反省を私たちがしなきゃいけないのかもしれないと思っていますけれども、そういったことをこれからどうするかと考えると、今申し上げた順番で、自薬局があって近隣薬局があって、地域薬剤師会があって、都道府県薬剤師会があって、最後に、その結果検証とこれからどうするんだっていう戦略を立てるのが日本薬剤師の役割です。
ですから、これは別に来年の3月の代議員会で厳しい質問がこないように前振りをしているわけではないんですけれども、「日薬どうすんだ」っていう質問をするときは、必ず「うちはこうやったけど成果が見えない」とか「他にいい方法はないのか」ということでご質問いただきたいと思うんですね。
そうすると問題点とかも、代議員会の質問を通して皆さん共有できるようになります。「うちはこういうことやってるよ」とかですね、これもたぶん今からこれまで以上にやらなければいけないことかなと思っています。
在宅を含め、質の評価のベースラインを作っていくべき
調剤報酬の改定についてです。
皆さん、点数のところに目がいくので、「概要」というところってあんまりお読みになっていない方がいらっしゃるかもしれませんけれども、調剤報酬改定の「概要」というのが一番最初のところに出てきます。
今回の令和6年の調剤報酬改定では、「地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価」とあります。自分たちは地域で医薬品を供給している拠点としての役割を発揮できるかということを評価する点数ですね。
次に医療従事者の賃上げで調剤基本料の体制を評価する。それからもう一つは質の高い在宅勤務です。
質の高い在宅勤務って何でしょう。どうしたら質が高いと思ってもらえるんでしょうか。これは保険者が評価するとか、厚生労働省が評価するんじゃなくて、患者さんとその家族ですよね。どういう薬剤サービスを提供したら質が高い在宅業務の推進になるのでしょうか。
オンラインでやることでしょうか、頻回に訪問することでしょうか。質を求められていったときに、我々の業務の質のゼロベース、最低限これはやらないとダメでしょっていうところはどこにあって、それを上回る、期待を上回る結果が得られれば、たぶん事業者の方々は評価していただけるはずですよね。
「思ったよりいいじないか」ということですよね。それをちゃんと示さないと誰も評価してくれないですよね。
その基準は自分たちで作らないといけない。誰かが基準を作ってくれて、その期待を上回るってことはあまりありませんから。自分たちでベースラインをどうやって作っていくのか。
それから、「かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価」です。
言いにくいことを申し上げれば、今の薬歴っていうのは書くの大変ですよね。残業が大変とかという話をよく聞きます。薬歴というのは、次にお見えになる患者さんの為にどう役立っているのかという観点で書かれているのかどうか。あるいは自薬局の薬歴を全部まとめた時に、データソートして、こういうキーワードたくさん書いてるねとかってことがソートができるんでしょうか。・
実はそういったこと、まあDXとかって言ってますけれども、やっていかないとですね、地域薬剤師会とかあるいは都道府県薬剤師会、日本薬剤師会もそうですけれども、薬剤師の業務がデータで見えるようにならないですよね。
日本全国の薬剤師さんが薬歴にどんなワードを一番たくさん書いているのか。
「お元気で」と書いてあるのか。これは薬学管理でもなんでもないと言われてしまいますよね。「腎機能」とか「肝機能」というキーワードがいっぱい出てきているのであれば、「薬剤師さん、そこに一番目が向いているんだな」ということもわかるじゃないですか。
それをやるためには、テキストベースでやっていたってなかなか解析大変ですよね。どうしましょう。仕事が成果として見えるかどうかということも示していかないといけないですよね。宿題がいっぱいこういったように一つ一つあげてもいっぱいあるんですけれども、これやってるうちに、令和8年度調剤報酬改定がもう動き始めています。
ですから、もう待ったなしですね。自分たちが何ができるのかをそれぞれで考えて、もちろん一番最後の薬歴をどうするのかというのは日本薬剤師会の役割でもあると思いますけれども、そういう意見をぜひ委員会もそうですし、都道府県会長協議会もそうですし、意見をどんどん出していただきたいです。
もちろん、やれること、やれないこと、たくさんありますけれども、役員も、私を除くとですね、皆さん優秀な今回の役員でありますので、副会長、常務理事、理事ももちろんそうですけれども、でも限りがあります、チームには。ぜひ、たくさんのご意見をいただいて、どうやったら薬剤師全体がより良くなるのかっていうことを、もし成功事例があればですねそれをどんどん日薬にお伝えいただきたいです。
そういったことで、「これからみんなで薬剤師の将来を作っていきましょう」ということにしていきたいと考えています。
令和6年度調剤報酬の体系の「調剤技術料の加算」「地域支援体制加算」とか「在宅総合体制加算」とか「医療DX体制加算」につきましては、これ要するに薬局の機能を評価していると思うんですね。
体制加算ですから。在宅に何回出かけたから何回点数算定していいですよって点数と違いますよね。体制を評価してるんですから。これはちょっとうがった見方をすると、訪問するたびに点数つけると過剰請求じゃないかってことを考える人もいるわけですよ。じゃあ体制加算をすれば一回につきしか、あるいは処方箋1枚につきしか算定できないので、過剰請求なくなるんじゃないのって考える人がいても私は不思議じゃないと思います、肯定はしませんよ。
だから在宅医療をDPC化しようとか、包括にしてしまえばたくさん行かなくなるだろうって考える人も絶対いますよね、私がそれを推奨してるとかそういう意味ではありませんから誤解のないようにしていただきたいんですけれど、意見としてそういう意見も出てきますよね。
そうすると、薬剤師の業務、さきほどの質の向上といったことを、みせれば、「いやそんなことないですよ。余分なんか算定してませんよ」って言えます。そこもこれからこの先の改定を見据えると、そんな心配も、いらん心配であればすごくいいんですけれども、考えなきゃいけないと思っています。
特定薬剤管理指導などは従来型の点数配分ですよね。
調剤管理料の方ですけれども加算になっていますので、出来高払いですよね。これもやってみて過剰請求がもし疑われるとなれば、たぶん考えてきますよね。調剤後薬剤管理指導料とか在宅移行初期管理料。これもいわゆるステージに合わせて細かく点数配分をしたということでありますので、これはこれで中医協で森副会長がかなり努力をされて、こういった結果、もちろん、現場の先生方の実態を反映してですねこういった反映になっていると思いますけれども、こういったことがこれからどんどん2年ごとに起こります。
冒頭申し上げた、所得・給料の改善ですね。そこに結び付けなきゃいかんですよね。
調剤報酬上がった、だけど中間年改定で薬価の評価損が50万円あります、どうやって給料をひねり出すんだよってなりますよね。そういうことをどうやって考えてるかって、やっぱりいろんなところが効率化を避けて通れませんので、どうやったらうまく回るようになるかってことを考えながら、調剤報酬を考える。
この金額ありきで算定するというのは言語道断ですけれども、我々の中でできることは何なのかってことを考えながら報酬改定に対応していく。
しかも2年でまた変わってしまいますから、今から次の改定に向けてどういう準備ができるかってことをしておかなきゃいかんだろうと思います。
地域の住民や関連職への薬剤師の持つ機能をプレゼンテーションすることが重要
(次のスライド)「薬局の持つ機能を地域へ明示化」と書きました。
(機能を3つ記載)
例えば(1つ目「OTC医薬品の販売:在庫の見える化」)、今回、48薬効群のOTC薬を置けとなりました。
そもそも調剤薬局って言ってるので、地域の住民の方々はOTC医薬品を買いに行く対象施設として見ていないんですよね、薬局を。ドラッグストアでしょってなるわけです。
高齢者がですね、広い駐車場に車を停めて、1500アイテムの中から薬が選べるかというとなかなか難しい。そうすると高齢者が増えてきますので、身近なところで医薬品を買えるようにしておかないと問題だよね、でも置いてないじゃないと言われないように、とりあえず置いてください、見えるようにしてください、5年間置いておけば誰か地域住民が気づくでしょってことだと思うんですよね。
だから48薬効群置いてあるけど邪魔だからしまってあります、とかですね。問題外ですよね。
地域の住民の方々にうちはOTCも置いてますよってことを見せるってのが目的ですから。あることが分かればお買い求めになられる方もいらっしゃるでしょう。だけどその意図を理解せずに、期限が切れちゃうから、卸が見つからないとかって言っててもですね、その先を見据えたときに、今から何やるんだっていう観点で考えないと難しいだろうなと思います。
2つ目、医療措置協定の締結、感染症対策です。
防護服だとかマスクとかいろんなものを用意しますよね。
これを地域住民の方まで見せるように展示しておくというのはなかなか難しいと思うんですけれども、例えば地域である感染症対策の会議ですとか、訓練とかに薬局薬剤師が参加していることを地域住民の方に見ていただく。これは3つ目の災害時の役割もそうです。皆さん方の所属していらっしゃる都道府県でも、県の防災訓練やりますよね。私も愛知県の会長として何回も参加していますけれども、あそこに行っても業界関係者だとかその災害訓練に来てる人は薬剤師会やっているんだって分かりますけれども、地域住民にはわからないでしょう。
そうすると薬局は災害時の拠点としての役割もあるんですよっていうのは、行政がやってる防災訓練に薬剤師会として参加しないとですね、地域住民には見えないですね。
こういったこともやらなきゃいけない。
地域の住民の関連職への薬剤師の持つ機能をプレゼンテーションすることが大事です。
これからの調剤について、私見です。
例えば箱出し調剤になると、「返品取ってくれるから楽になるよね」って言いますけど、返品取るためには温度管理が必要ですよね。今、注射剤がそうですよね。0度から35度ですけれども、「大丈夫ですか、30度を超えてませんか、0度以下になってないですか」と保証あるのという風に言われたら、そういったログデータを出さないと、卸さんは返品取ってくれない可能性もありますよね。
それから一包化調製の外部委託先にですね、どんな分包機で誰が何時何分、どの分包紙を使ってどのロット番号の使用期限のどんな薬を使って一包化したのか、情報開示しないとお宅に任せられませんって言いますよね。じゃあ任せない時は任せるところと同じことやってますかって必ず言われます。
調剤の一部外部委託というのはですね、要求したことが全部自分達に返ってくることです。
自分の薬局は大丈夫でしょうか。
こういったことがこれからたぶん、パンドラの箱を開けたとは言い過ぎかもしれませんけれども、そんな感じがしているんです。
調整行為の見える化がこれで一気に始まるんだろうと思います。
こういったことを真摯に患者さんに見せて、お宅の調剤ちゃんとしてますよねっていうことが見えるようにすることによって、かかりつけ薬局とか薬剤師の機能ということで対応ができるんではないか。
「時間外への対応」と書きました。
時間外の受付っていうのは、例えば処方箋の受付ポスト。当然、処方箋は個人情報の塊ですから、厳重な、引っこ抜いたら持っていかれるようなことはもちろん困るわけですけれども、こういったことも考えなきゃならんことだろうと思います。
OTCの販売も書きましたけれど、これは医師・歯科医など関係する職種の連携もこれからもっと重要になってくると思います。昨日も分科会で申し上げましたけれども、OTCの販売のエンドポイント(到達目標)ってどこなのか。
頭が痛い、頭痛がするということに鎮痛剤を販売して、止まったらいいのか。
あるいは効かなかったらどうするのか。もっとひどくなったらどうするのか。病態の変化をどう読めるかっていうのはですね、処方箋調剤でやっているからこそOTCを薬剤師に任せても大丈夫ですよねってことに立て付け上、なってますよね。
要指導薬がそうじゃないですか。じゃあ保険調剤で患者さんの病態変化というのを捉えて、あるいは臨床検査値の変化をどうとらえて、どういった服薬指導とか、あるいは患者情報の収集をしているかとかですね、医師に処方提案ができているかっていう観点で、この能力とノウハウをOTC薬に全部注ぎ込むということが必要だと思っています。
当然その使用者に応じた適正使用に必要な情報提供とか、ここに書きましたけれども、当たり前のことでこういったことが世界にはなかなかないお薬手帳とか薬歴を使ってリストの情報共有と連携ができるようにしないと、OTC販売も、これからPPIも出てまいりますし、緊急避妊薬もおそらくOTC化も始まるでしょうし、難しい薬がたくさん出てくるという時代になりますので、そこに真摯に対応していればですね、イギリスは来年でしたっけ、卒業する薬剤師に処方権を全てに与えとかですね、カナダの一部やってるようですけれども、我々が処方権を欲しいかどうかは別です、だけどちゃんと医薬品を提供しているからこそ処方権を与えても大丈夫だという議論がたぶんあるんだろうと思いますね。
当然、不適切な場合には販売しないし、もしくは販売しても心配だったら必ずうちの薬局で書いたこの薬とこの情報提供を持って医師にかかってくださいっていうやり方のほうがいいでしょう。「わからなかったら受診勧奨だよね」ということにはならないと思うんですね。
ですから、こういった連携を前提として、あるいは薬剤師が先ほど申し上げた処方箋調剤で培ったノウハウをいかにOTC販売につぎ込むかっていうのはすごく大事なことだと思っています。
もう1つ、DXです。DXは先ほど申し上げましたけれども、実は電子化をする時に一番大事なのは業務フローの見直しなんです。今回のDXに関しては業務フローの見直しのないままに、電子処方箋とかいろんなものが個別に走っているような状況です。
これも申し訳ない、言いますけれども、ガソリンスタンドが急になくなりましたね。地下の埋設タンクの耐震基準を変えて市場から撤退させたんでしょうと私は勝手に思っていますけれども、DXもそうなんですね。
いろいろ問題があります、不都合もあります、お金もかかります。だけど、やらないと「もうやめてくれ」って言われたらどうしようかと考えると、やらなきゃいけない。処方箋を受ける側が先に整備しないと出せないですよね。
ですから、ここは本当にお金もかかりますし手間もかかりますし、技術やセキュリティなどいろんなことがありますけれども、ここは歯をくいしばって対応していかないと国が求める薬局DXにはついていけなくなりますので一生懸命頑張って、進めていきましょうということになると思います。
それから、小売業というのはやっぱり地域にどんな資源があってどんな患者さん、お客さんがいらっしゃってということをリサーチしないと成り立ちませんよね。
もう1つは、患者さんが次にいつ来るのかとか、あるいはあの人最近顔見ないけどどうなのかなっていう、顧客管理のノウハウも絶対に必要な仕事です。
そういったことをきちっと保険調剤とかOTC医薬品の販売、あるいはあの緊急避妊薬もそうでしょうし、あるいはコロナ検査キットもそうですけれども、そういったことができるようにこれからしていきましょう。当然、学校薬剤師の役割でありますヘルスリテラシーの向上もそうですし、こういったことをこれから薬剤師に求めていけばですね、一番最後の、心配することは心を配ることってなんかあの判じ物みたいであれですけれども、AIにはたぶん心を配るっていうのはあんまりできないと思いますので、これがたぶん一番の強みかなと思っています。
(最後のスライド)これはドイツの薬局の写真です。
中央に見えるガラス張りのところが医薬品庫というか、調剤室です。パッケージ調剤ですから。機械が自動的に運んでカウンターのところに薬が出てきます。
何がいいかというと、我々は処方箋を受け取ったら調剤室に引っ込んじゃうでしょ。会話が途切れちゃうんですけれども、これだったらずっと喋ったままで患者さんに薬が渡せるんですね。手間が省けるかということじゃなくて、患者さんをどうやって薬剤師の会話と引き止めるかという観点でも見ていただきたいと思いましたので、この写真をつけた次第であります。
ご清聴ありがとうございました。