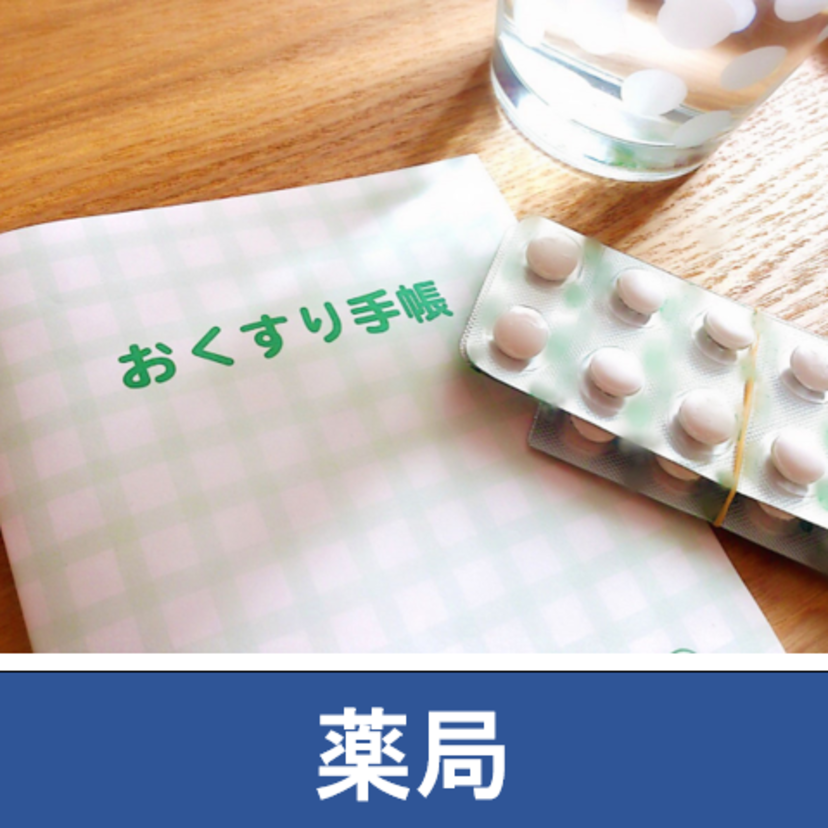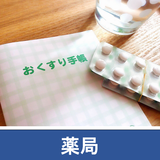日本薬剤師会は3月11・12日に第101回臨時総会を開催。一般質問の場で、東海ブロック・岐阜県薬剤師会の鈴木敏文氏が敷地内薬局の問題を取り上げた。
鈴木氏は、具体的な内容を説明。岐阜県においては2019年に岐阜大学医学部附属病院が、病院東側3階建ての技術棟、病院玄関前に2階建ての利用者サービス向上につながる提案施設、総事業費40億円を整備するにあたり、協力事業者を公募したところ、県内から3社の応募があり、2020年3月に、中部薬品(Vドラッグ)が交渉権を得て、2021年9月に事業者提案施設の1階に敷地内薬局として、開局した。
同大学はこの事業者の提案施設等の事業提案を“資金調達”と位置付けており、一時金として大学が10億円、残りは新たな技術棟での収入を原資に事業者に対する20年の分割払いとし、整備後は大学が所有権を獲得するものという。敷地内薬局の賃料は不明という。
一方、岐阜薬科大学附属薬局は1998年に全国で初めての薬系大学附属薬局として開設され、2004年に岐阜大学医学部附属病院の門前に移転。しかし、コロナ禍と敷地内薬局の影響で経営状態が悪化したとの理由で、今年3月31日をもって閉局することが決まったという。
岐阜薬科大学附属薬局はこれまで、リカレント講座、岐阜県薬剤師会の講演の定期的な開催による薬剤師の資質向上のほか、薬学生への実務実習への積極的な関与等があったといい、鈴木氏は「(閉局の)影響ははかりしれない」と指摘。「敷地内薬局は全国に256軒存在しているということであり、同様の理由で閉局に追い込まれる薬局は少なからずあり、これを放置することは、切り捨てとも取られかねないのではないか」と訴えた。その上で、「岐阜大学医学部附属病院の公募から4年あまりが経った。岐阜県薬剤師会として何ができたのか、今更ながら苦慮している。今後の対応のためにも何か具体策があればご教示願いたい」と日薬執行部に質問した。
これに対し、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は次のように回答した。
「今、現場での具体策があるかというと、正直、持ち合わせていない。ただ、4年前と今は大きく状況は変わっている。当時はどこで、どのような条件で敷地内薬局の公募が行われ、どのような条件で契約しているのかが分からなかった。その後、各県薬等から敷地内薬局の公募情報が寄せられ、日薬も情報収集を行い、実態把握をして、それをまとめて要望書をつくって要望を公表することで、今は広く関係者に敷地内薬局の実態を伝えることができたのではないかと思っている。その後、厚労省はもちろん、医師会、病院団体、保険者、与党など、さまざまなところを回って説明し理解を得て、その上で、医療保険部会・中医協でもしつこいと言われるぐらい発言をしたことで中医協の中でも医師会、保険者からも否定的な意見が出され、前回改定で対応された。国が目指す医療の姿に逆行しており、国民皆保険制度で成り立っているという財源の意味では公費・保険料等をこのような使い方をすることは適切ではないと理解されていると思っている。日薬だけでは止められない。関係者へのさらなる理解を深め、都道府県薬剤師会と日薬が両輪になって進めていきたい」。
記事更新:2023年6月24日 記事の一部を削除しました。