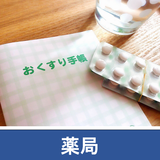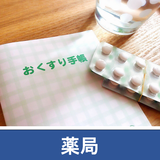手引きは、「1対応フロー」「2処方箋例」「3調剤日と調剤可能期間」などのコンテンツとなっている。
フローでは、受け取り時の確認、妥当性判断、服薬指導、服薬指導後の対応、必要に応じて対応、次回来局などの流れにそって、それぞれ留意するべきポイントをまとめている。
例えば、受け取り時には「レ点があるか」「使用回数」(上限3回まで)「医薬品種類」などを確認するとしている。
留意点としては、リフィル欄に手書き記載があった場合には偽造を疑い医療機関に確認するほか、投薬量に限度が定められている医薬品 (新薬や向精神薬、麻薬等)及び湿布薬 (63枚の制限あり)についてはリフィル処方箋による投薬を行うことはできないことなどを明記。
また、外用薬のリフィル処方の場合、 1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数の記載に加えて、投与日数の記載が必要(例:点眼液6瓶 1日6回両目に点眼 *30日分)としている。
リフィル処方可の薬剤と不可の薬剤が混在する場合(例:降圧剤と湿布薬)、薬剤毎にリフィル回数が異なる場合(例:降圧剤はリフィル3回、頓服使用の鎮痛剤は1回のみ) は、処方箋を別に分けて発行する必要がある。
さらに、有効期間を確認する。2回目以降は、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内を有効期間とする。
例として、「次回調剤予定日が6月13日だった場合、その日を含まない前後7日間である6月6日から6月20日の間で調剤が可能」などと記載している。
このように、それぞれのタイミングごとに確認事項などが細かく記載されていて分かりやすい。薬局現場で、間違いのないリフィル処方箋への対応に寄与しそうだ。
また「調剤日と調剤可能期間」の項では、カレンダー形式で調剤可能な期間を表示している。
巻末では、患者向けのリーフレットも掲載。患者に対してもリフィル処方箋の利用の流れを図説しているとともに、下部には「次回の処方箋有効期間」を大きく記入するスペースを設け、患者に期限切れが起こらないように促している。
協会では、今回の手引き作成、公表に関して、「リフィル処方箋は薬剤師の職能が試され、医薬分業の是非にも大きく影響しうるということを重く受け止める必要がある」とした上で、「手引きが国民にリフィル処方箋のメリットを感じていただき、薬剤師が医師と連携を図りながら丁寧・適切に対応していく一助となれば」としている。

【リフィル処方箋】手引きを日本保険薬局協会が公表
【2022.09.12配信】日本保険薬局協会は9月8日に定例会見を開き、その中で「リフィル処方箋の手引き」を作成したことを報告した。今後、協会ホームページで公開する予定という。
関連する投稿
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【日本保険薬局協会】門前薬局“減算”、「到底受け入れられない」/三木田会長
【2026.02.12配信】日本保険薬局協会は2月12日に定例会見を開いた。この中で会長の三木田慎也氏は、次期調剤報酬改定の項目、いわゆる“短冊”について触れ、「門前薬局等立地依存減算」について「到底、受け入れらない」と強調した。「患者さんの動向、患者の志向、いわゆるマーケットインの発想が調剤報酬をつくる側に全く意識されていない結果」と述べた。
【日本保険薬局協会】中医協での敷地内薬局批判に反論/合法なのに“抜け駆け”は「酷い表現」
【2026.01.15配信】日本保険薬局協会は1月15日に定例会見を開いた。
【保険薬局協会】地域加算「基本料1」と「それ以外」で点数・実績要件統一を/次期改定要望
【2025.12.11配信】日本保険薬局協会は12月11日に定例会見を開き、会長の三木田慎也氏が次期調剤報酬改定の要望事項を説明した。調剤基本料に紐づいて区分のある地域支援体制加算について、「基本料1」と「それ以外」での要件や点数を統一することを求めた。
【日本保険薬局協会】中医協「調剤」での「病院薬剤師」議論にコメント
【2025.09.11配信】日本保険薬局協会は9月11日、定例会見を開いた。この中で9月10日に開かれた中央社会保険医療協議会総会の「調剤について」の議論の中で病院薬剤師の不足に関して多くの意見が出たことについてコメントした。
最新の投稿
【2026.02.23配信】日本チェーンドラッグストア協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度調剤報酬改定に対する見解」を公表、説明した。
【2026.02.23配信】日本保険薬局協会は2月20日に会見を開き、「令和8年度改定の答申を踏まえた緊急要望書」を公表、説明した。「集中率カウント変更」に対して激変緩和措置を強く要望。また、「門前薬局等立地依存減算」の導入に対し、「断固反対」としている。
【コミュニティファーマシー協会】ドイツ薬局視察旅行の参加者を募集
【2026.02.22配信】 日本コミュニティファーマシー協会はドイツの薬局を視察する旅行参加者を募集する。 旅行期間は2026年6月8日(月)〜6月13日(土)まで4泊6日。申し込み締切は、2026年3月5日(木)。
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。