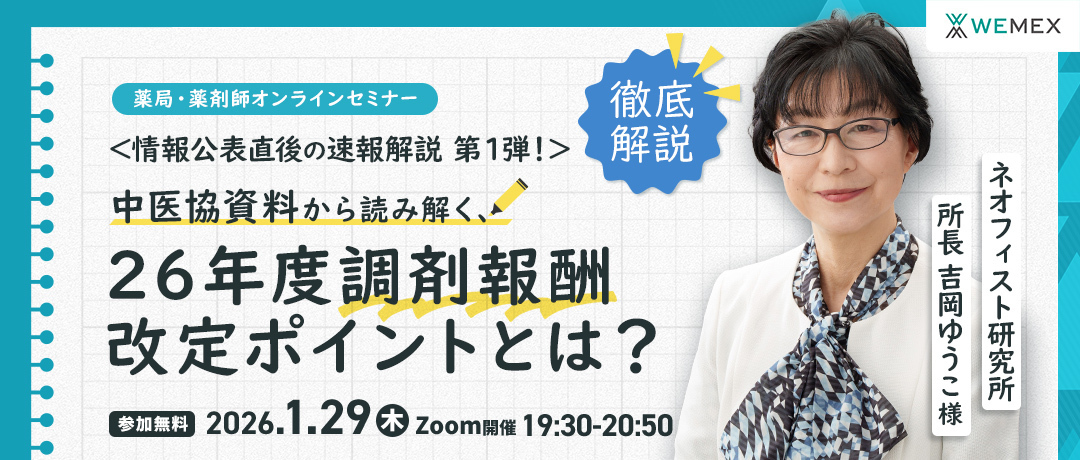■“派遣”体制など薬剤師確保に向け特別委員会設置し、必要な調査も実施へ
機能分化で求められる薬剤師連携に向け“病棟業務”拡充へ
ーー初めに会長としての抱負、役員体制についてお聞かせください。
武田 木平健治前会長の下で2期副会長を務めさせていただいきました。新型コロナ禍により木平前会長や各委員会の先生方もあまり思うような活動ができなかったのではないかと思います。新体制については、木平前会長の思いを、まさに引き継いでいくという考えです。加えて各先生方にとっても消化不良のまま、体制が大きく変わるということも避けたいとの思いもあります。
社会保障制度を財政的、仕組み的にも安定させることを目指す「社会保障と税の一体改革」が進められるなかで、病院の場合は機能分化と連携がテーマになっています。当然、我々病院薬剤師も各病院の機能に合わせ薬物治療管理のあり方は違ってくることから、それぞれに合わせた薬物治療管理をしっかり実践していくことが、進めるべき一つの方向であり、日病薬として支援していくべきことと思っています。
会員の多くが中小病院の薬剤師であり、マンパワー不足により厳しい環境にあるかと思います。その中でも、より高度な薬剤師業務への対応が求められ、一方で医師の働き方改革によるタスク・シフト/シェアもあって、その業務量と業務領域は増加の一途にあるといえます。
厚生労働省の「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」(以下、検討会)における薬剤師職能の議論を通じて、大いに期待されていることが示される一方、改革が求められていると感じています。これからの地域包括ケアに対する検討会での主な焦点は薬局薬剤師の業務に関してですが、当然、病院薬剤師の関わり、役割も大きいと感じています。地域の中で薬物治療管理をシームレスにつないでいくため、薬局・薬剤師の皆さんとの連携とともに、病院薬剤師同士の連携も当然必要です。当初目標の2025年まではあとわずかですが、その体制構築に向け機能分化への対応とともに地域包括ケアの中で薬物治療管理をつなぐ医療連携の推進が、私の目標の一つであり、日病薬として必要な支援をしっかりやっていきたいと思います。
人材確保」に向け特別委員会設置、新たな“報酬”体系の検討も
ーー機能分化が進む中で、病院薬剤師同士の連携は重要ですね。
武田 本当にそうなんです。患者さんは急性期に入院された後、回復期、あるいは慢性期を経て外来診療や在宅医療に移っていく流れがあります。それに合わせて、入院中の患者情報も一緒に動いていくことが重要です。そのため病院薬剤師同士がきちんと連携しなければいけませんが、現状はそこまでには至っていません。
その大きな要因として、未だ全施設の2割しか病棟薬剤業務実施加算の取得がされていないことがあります。なかでも中小病院や療養病床などで算定できず、結果として薬剤師サービスの充実ができていないのですが、その背景には薬剤師不足という大きな課題があります。
検討会の中では薬剤師の受給予想として、将来的に過剰になるとされています。しかし、現実には地域偏在や機能別病院間の偏在が見受けられ、施設によっては薬剤師不足であり、マンパワー確保が必須です。厚労省でも対応に動き出してはいますが、日病薬として対策を考えていかなければならないと思っています。
元々、地域包括ケア構築のための「地域医療介護総合確保基金」における事業の一つとして、医療関係者の確保対策がありますが医師や看護師が中心でした。現在は病院薬剤師の確保にも活用できると解釈されていますが、それほどその活用は浸透していません。
そこで今回の新執行部体制において、この基金を利用した薬剤師確保策について、マニュアルあるいはガイドラインを作成し、自治体との交渉に使っていただくことを考えています。一つは奨学金返還に関する事業があります。また厚労省からは、薬剤師不足の地域における薬剤師派遣が提案されています。具体的な考え方や方法などは示されておらず、日病薬として早急に策定したいと思っています。
一方、根本的な問題として、新卒者が病院に就職しない理由の一つとして、給与の低さがあると思います。しかし、いろいろな公的検討会等で示される調査・解析データでは、病院薬剤師の給与は高い、決して低くはない、といわれます。しかし、薬学教育協議会の報告書によれば、平成2年度の6年制学科卒業生の就職先別初任給は、国公立大学病院や自治体系病院、私立大学病院や一般病院、保険薬局、チェーン薬局、ドラッグストアの調剤部門という順番で低くなっています。
公的病院の場合は、俸給表に沿って年齢とともに上がりますが、一般病院では少なくとも初めは高めに設定されるなど、給与の年代別の変化、いわゆる傾きが違うなど、生涯収入を含め、病院薬剤師間でも給与格差は小さくないと感じています。当面、年代別に給与の変化を、データとして把握するべきと考え、調査をしたいと思っています。
ーー人材確保に関する検討体制についてお聞かせください。
武田 急性期病院では病棟業務が展開され、外来への関与も始まっていますが、中小病院や慢性期・リハビリテーション、精神科の病院では、薬剤師が足りないために病棟業務ができず、いわゆる調剤中心の業務に追われている例は少なくありません。入院患者の情報をシームレスにつなぐためには、送り出す側もそれを受ける側もしっかりとした体制がなければ成立しません。さらにかかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局との連携も同様で、まずは病院機能に見合う薬剤師確保が必要です。
先ほど基金の活用で述べましたが、奨学金の関係は、和泉啓司郎専務理事を中心に組織強化推進部に検討をお願いしています。また、薬剤師派遣の仕組みについては、新たに「病院薬剤師確保策に関する検討特別委員会」を立ち上げました。委員長は崔吉道理事(金沢大学附属病院)に、担当副会長には実際に薬剤師派遣の取り組みをされている眞野成康先生(東北大学病院)にお願いしました。
薬剤師派遣については、大学病院の医局制度の病院薬剤師版というのが私のイメージです。ただ、私の病院も薬剤師数の充足は厳しく、同様に地方の国立大学病院等には薬剤師が少ないのが現実です。公的医療機関を中心に自治体とのタイアップの基に、地域医療介護総合確保基金などの資金を運用していく仕組み、つまり国立病院機構や大学病院、自治体立病院が地方行政と一緒になって薬剤師を採用し、その枠の中で人を派遣していく仕組みが期待されます。
ただ、いわゆる都会と地方では環境が違い一律とはいきません。それぞれの地域医療構想に見合った薬剤師配置体制を是非考えていただきたい。勿論、地域薬剤師会、薬局薬剤師の方々とも連携し、地域に応じた仕組みづくりを進めていただきたい。
これらの検討は特別委員会にお任せしていますが、公的基金という時限的な財源と想定されるだけに、早急に進めると共に、継続し得る他の資金調達方法を考えなければなりません。
ーー薬剤師確保の面でも診療報酬の充実が一つ大切なテーマです。次期改定についてはどのようにお考えですか。
武田 既に医療政策部会が中心となり、次期診療報酬改定に向けて会員からの要望について調査の準備を進めています。これまでの要望も踏まえ回復期、リハ病棟に病棟薬剤業務実施加算を付けていく。中小病院に何らかの診療報酬をつけ、結果として薬剤師確保につなげていただくような対策、流れを作らなければいけないと思っています。
要望にあたってはエビデンスが必要であり、今後の調査、検討が必要です。ただ、中小病院の方々が、「こういう業務に対して報酬が欲しい」と言って、自らエビデンスを作るという環境にはないと思っています。執行部側からも、新たな項目や加算、要件の見直しの提案なども出し、双方でアイデアを出しあって取り組むことが重要だと思います。特に回復期・リハ病棟、中小病院で病棟薬剤業務実施加算の算定につながるような方策を考えていきたいと思います。
とはいえ、大きな病院では病棟配置すれば入院患者も多く、大きな収入が期待されます。しかし、例えば中小病院で2病棟しかなければ、2人配置したとしても新たに薬剤師が雇用できるほどの診療報酬は得られません。実際に現場の先生方からは、大きな病院と同じ診療報酬体系では、雇用者側を説得できるような武器(理由)にはならないと指摘されています。大きな病院とは異なる業務に報酬をつけ、人を雇い、結果として病棟配置につながるという流れを作らなければ難しいのかも知れません。
ーー今回の診療報酬改定で地域フォーミュラリが注目されました。ご自身の病院の状況を踏まえ、どうお考えですか。
武田 私自身は、薬物治療の標準化という意味ではすごく大事だと思います。その観点から、地域フォーミュラリが作れるものについて作るということは良いかなと思います。
病院薬剤師も、フォーミュラリには興味があると思いますが、その関心の中心は、在庫整理と薬物治療の標準化だと思います。私自身は、大学病院ですので同じ疾病に対する同種同効薬が何種類もあります。採用医薬品の種類と数の整理という面から一本化してほしいのですが、専門医の先生方の考えがありますので難しい面はあります。フォーミュラリの基本概念は経済性を加味した医薬品選択ということですので、日本フォーミュラリ学会が策定しているフォーミュラリを地域の特性に合わせて地域で検討・選択していくのがよいのではないでしょうか。地域フォーミュラリの運用に関しては次期診療報酬改定でも議論される可能性があるのではないかと思います。
卒後研修のあり方は焦点だが、まず「卒前実習の充実」が望まれる
ーー前述の検討会でも卒後研修が焦点の一つになっていますが、主に受け入れることが想定される病院の立場ではいかにお考えですか。
武田 薬剤師卒後研修の制度化が検討されていますが、どうしても研修生の給与問題が避けられないと思います。年間約1万人の薬剤師が誕生する中で、全てを受け入れることは難しいかもしれません。そこを可能にしていくためのネックは、やはり財源問題と受け入れ側、つまり我々の体制にも課題があると思っています。
例えば、病院独自にレジデント制があり、そのほとんどが高度急性期病院です。いわゆる英才教育的な研修を行っています。病院・保険薬局の機能分化が進む中で、一定数の専門領域を目指す人がいる一方で、いわゆる地域貢献を目指す人もいます。
これは個人的な意見にはなりますが、免許取得直後の全員を対象に、臨床研修を行うという前提であればジェネラリスト研修が中心になると思いますが、薬剤師が各々目指す方向に合わせた複数の卒後臨床研修をつくるという考え方もあると思います。
高度急性期医療に携わるためのレジデント研修制度を残し、一方で病院におけるチーム医療の経験は地域貢献においても重要ですので、各地域で病院と薬局とがきちんとグループを組み、医師卒後研修と同様に、双方でマッチングをかけるような制度設計があればいいのではないかと思います。また、一定期間の卒後研修をさせるのであれば、薬剤師にも国からのサポートが必要だと思います。
我々薬剤師にとって、新任薬剤師の資質向上は最大の問題であり、卒後研修が重要だということは理解しています。ただ、その前に薬剤師になる資質、意欲をもつ学生を入学させる施策が必要だと検討会でも言い続けてきました。そして卒前実習を充実させた上で、卒後研修のあり方を考えるべきではないでしょうか。個人的には少なくとも1年間は卒前実習をすべきと思っています。
ーー日本薬剤師会を始め関連団体との連携、地域における薬局との連携は重要なテーマです。そのなかで日薬との統一の話題が上がっています。
武田 分離当時の日薬とは考え方や方向性が違ってきたという経緯があり、木平健治前会長や堀内龍也元会長の言葉を借りれば、過去に分かれる経緯になった事柄が片付いて行かないと、直ぐに一緒になることは難しいとおっしゃっています。まさにその通りだろうと思います。
勿論、薬剤師としての職能や薬物治療に対する責任という意味では、当然同じですが、診療報酬上は医科と調剤とで異なり、その働く環境が違っています。しかし、今後とも日薬との協力体制を堅持し、連携はしっかり取っていきたい。一方、地域での統合については、それぞれの環境・事情があり、それぞれ考えていけばいいと思います。
我々病院薬剤師のベースとなる各種病院団体との連携においては、病院団体側からも薬剤師不足を訴えていただいています。今後とも薬剤師確保に向けて、是非協力いただき、声を上げていただきたいと思っています。
また、各地域薬局との連携に関しては、薬局は地域に密着し、医薬品をあまねく供給する体制づくりが求められており、そのための連携が大切だと思います。それらの薬局では在宅医療への対応や健康サポート機能が求められると思います。そういう領域で活躍される薬剤師の方には、住民の相談内容に応じた“トリアージ”をし、実際に患者さんが病院に行く場合には、病院薬剤師に必要な患者情報を提供していただく。逆に、退院して地域に戻るときには院内での患者情報を、かかりつけ薬局側に提供していく、そういう連携が求められると思います。
ただ、薬局も薬機法上で機能が示され、大きく三つに分類されるかと思いますが、病院側としてはその違いを踏まえながら、どの薬局とどういう連携、協力体制を作っていくべきか、どの薬局に情報を伝えればいいのか、そういう点がクリアになることを期待しています。私自身は地域薬局の先生方と一緒に体制づくりをしてきました。地域特性に合わせた、まさに地域包括ケアシステムをそれぞれの地域薬剤師会が中心になり、我々も含め自治体とともに、適正な薬物治療管理が提供できるよう、薬局配置を含め、地域医療構想の一環として全員で考えていかなければいけないと思います。