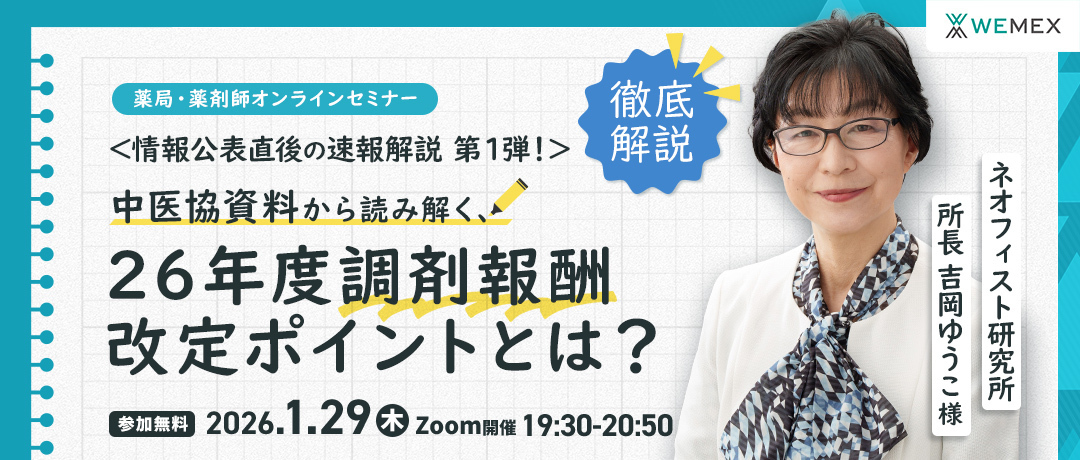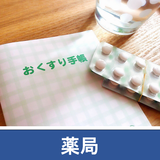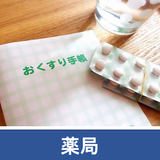スギメディカルはスギ薬局を擁するスギホールディングスのグループ会社。杉浦伸哉氏が社長を務めており、訪問看護事業などを手掛けている。
同日の会議では、同社が在宅における薬剤師による点滴薬剤の交換行為などを医師の指示の下で容認するよう要望した。
点滴薬剤の交換は「診療補助」に当たり、現在は薬剤師が行えないため、せっかく薬剤を届けても、医師か看護師が来るまで使用を待たなければならず、患者が薬剤を使用するまでにタイムラグが生じているとした。薬剤師に認めることで、タイムラグが解消できるとした。
一方、検討すべき課題として、3点を挙げた。
1つは、どのような行為を認めるべきか、具体的な診療補助内容を定める必要があること。
2つ目は行為を認める薬剤師のスキルをどのように習得するのか、あるいは特定の認定を受けた薬剤師だけに認める必要があるかどうかの検討だ。
3つ目は、報酬のあり方。調剤報酬制度による評価(点数)を設定するのかどうかという点だ。
さらに、具体的な現場の事例を2つ報告した。
1つ目が「 がん末期患者の疼痛コントロール」の事例。
在宅療養中のがん末期患者の疼痛が増強して、医療用麻薬(点滴薬剤)の増量が必要になったケースだ。
現行規制下での対応としては、医師が医療用麻薬などの増量を判断して、処方せん発行したのち、医師の指示と処方せんに基づき、薬剤師が患者宅を訪問し薬剤を届ける。その後、看護師が訪問して、薬剤師が届けた薬剤を受取り、点滴の交換・充填を行う。
薬剤によっては、薬剤をそのまま患者宅に置いていくことができず、薬剤師が看護師の到着を待って手渡ししなければいけない場合もあるとした。
ここでの課題は、患者にとっては薬剤師の訪問と看護師の訪問までに時間がかかる場合、速やかな薬剤の変更(増量)が行えず、患者が疼痛に長時間耐えなければいけない事態が発生する可能性があることだ。
看護師にとっても、薬剤師の訪問に合わせて、点滴の交換・充填のためだけに訪問しなければならず、業務効率が悪化する。
求められる規制改革の方向性としては、薬剤師が薬剤のお届けと同時に点滴の交換・充填も行えることとした。これにより、患者のQOL向上(疼痛のスムーズな緩和)と共に、看護師の業務効率も向上するとした。
本ケースにおける具体的な規制改革内容は以下の行為を薬剤師でも行えるようにすることとした。
• PCAポンプへの充填およびプライミング
• バルーンインフューザーの交換 など
具体的な事例の2つ目は褥瘡が発生している患者。
在宅療養中の患者に、褥瘡が発生して、処置(薬剤塗布など)が必要になったケースだ。
現行規制下での対応では、医師が褥瘡の治療・処置を判断して、処方せん発行したのち、医師の指示と処方せんに基づき、薬剤師が患者宅を訪問し、薬剤を届ける。その後、看護師が訪問して、薬剤師が届けた薬剤を受取り、患部を確認して褥瘡をアセスメントしたうえで、軟膏の塗布や創傷被覆材の貼付などの処置やケアを実施する。
ここでの課題は、患者にとっては薬剤師の訪問から看護師の訪問までに時間がかかる場合、速やかな薬剤使用やケアを行えない事態が発生すること。
看護師にとっても、薬剤師の訪問に合わせて褥瘡の処置やケアのためだけに訪問しなければならないケースにおいて、業務効率が悪化する。
求められる規制改革の方向性として、薬剤師が薬剤のお届けと同時に、褥瘡の処置やケアも行えれば、患者のQOL向上(褥瘡治療のスムーズな開始)と共に、看護師の業務効率が向上するとした。
本ケースにおける具体的な規制改革内容以下の行為を薬剤師でも行えるようにすること。
• 軟膏の塗布
• 皮膚欠損用創傷被覆材の貼付 など
なお、褥瘡の処置は、単に薬剤を塗布・貼付するだけでなく、褥瘡のアセスメントとケア、患部の状態に応じた薬剤等の医師提案も必要になってくるため、その技能の習得や質の担保が課題となるとした。
これらの規制改革にあたっては、保健師助産師看護師法に規定する診療の補助(一定の医行為)が認められる現行制度が参考になるとした。
「保健師助産師看護師法」では規定する診療の補助(一定の医行為)の範囲内であると医師が判断すれば、看護師の具体的能力に応じた「医師の指示」のもと、看護師が当該行為を行うことができるようになっているとした。
一方、厚労省側は薬剤師のタスクシフト/シェアに関しては、「現行法上、診療の補助を行うことができるのは看護師その他の医療関係職種に限られており、薬剤師が当該行為を実施することはできないこととされている」とした上で、「一方で、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等
において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものや、医師、看護師、薬剤師等による協働・連携の在り方等については、『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)』(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)のほか、『医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について』(平成22年4月30日付け医政発0430第1号厚生労働省医政局長通知)等においてお示ししてきたところ」と説明した。
また厚労省は、医師の時間外労働の上限規制の適用に向けて、「医師の労働時間短縮を強力に進めていくための具体的方向性の一つとしてタスク・シフト/シェアが挙げられており、薬剤師について
は、手術室・病棟等における薬剤の払い出し、手術後残薬回収、薬剤の調製等、薬剤の管理に関する業務に加え、事前に取り決めたプロトコールに沿って、処方された薬剤の変更(投与量・投与方法・投与期間・剤形・含有規格等)、効果・副作用の発現状況や服薬状況の確認等を踏まえた服薬指導、処方提案、処方支援が職種ごとに特にタスク・シフト/シェアを推進すべき業務として挙げられている」とした。
こうしたことを踏まえ、厚労省では、「現在、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例やタスク・シフト/シェアを推進するに当たっての留意点等について整理を進めているところ」とした。