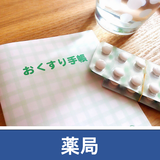事務局の骨格案によると、かかりつけ医機能の項目については、具体的には①外来医療の提供(幅広いプライマリケア等)、 ②休日・夜間の対応、③入退院時の支援、④在宅医療の提供 ⑤介護サービス等と連携ーーなどを想定している。
これらの項目について4つで表記する。「◎:自院のかかりつけ患者に対し、当該機能を単独で提供できる」、「○:自院のかかりつけ患者に対し、当該機能を他の医療機関と連携して提供できる
(連携する医療機関も報告。③の○は他院と連携して病床を確保している場合が考えられる。)」、
「×:当該機能を担う意向はあるが、現時点では提供できない」、「ー:当該機能を担う意向がないい」の4つ。これらを医療機関から都道府県に報告する。
〇や◎が揃う医療機関を都道府県は公表する。
〇や◎だけでない医療機関については、地域の協議の場において、各医療機関の意向を踏まえつつ、地域で不足している機能を充足できるよう、支援や連携の具体的方法を検討していく。
医師により継続的な管理が必要と判断される患者と医療機関が書面交付と説明を通じてかかりつけの関係を確認できるようにする。
地域におけるかかりつけ医機能の強化のための方策については、具体的な方策の例として、病院勤務医が地域で開業し地域医療を担うための研修や支援の企画を実施したり、地域で不足する機能を担うことを既存又は新設の医療機関に要請することなどが考えられるとしている。
あるいは医療機関同士の連携を強化したり、在宅医療を積極的に担う医療機関や在宅医療の拠点を整備していくことを検討する。地域医療連携推進法人の設立活用も視野にし、より簡易な要件で設立できる新類型を設けるとした。
これらの整備に対しては診療報酬による適切な評価などにより国が支援していく。
研修や国民向け情報の共有基盤等の整備も国が推進する。
報告制度に関しては法改正が前提になるとし、年内に医療部会で審議し、令和5年度頃医療法に基づく「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針(告示)」を検討、令和6年度~令和7年度頃から個々の医療機関からの機能の報告、地域の協議の場における「かかりつけ医機能」に関する議論を行うことを想定しているとした。令和8年度以降に医療計画に適宜反映させる見込み。
委員から「事務局骨格案には、義務ではないといった記述がないがどういう認識か」との質問が出ると、事務局は資料には義務ではないなどの記載はないものの、患者においては「国民・患者はそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用」とし、医療側については「医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化」と記載しているとし、「双方において義務ではないという理解だ」と述べた。
こうした骨格案に対して、日本医師会常任理事の釜萢敏氏は、制度の大筋が了承されたのちに、さらに必要な項目などについて議論していくという、今後の進行を確認。その上で、かかりつけの関係の確認については、現在の診療報酬上の届け出にも使用している地域包括支援診療料の活用が「イメージされる」と述べた。
また、「糖尿病と喘息、認知症などを患っている患者さんは、異なる医療機関にかかることもある。患者さんは複数の医療機関とかかりつけの関係を持てる必要がある」とした。
協議の場については、「地域にどんな機能が必要か、連携を図るためにも自治体と医師会の役割は大きい」と話した。
加えて日本医師会副会長の角田徹氏は、「(かかりつけ医は)患者の権利であり義務ではなく、登録制でもない」と指摘。そのほか、足りない機能の検討の場については、「2次医療圏では大きすぎる」とし、市町村単位が望ましいとの考えを示し、協議において郡市医師会も役割を果たしていくとの考えを示した。
健康保険組合連合会専務理事の河本滋史氏は、かかりつけ医の質を担保するためには、医療機関からの報告だけでなく、認定などが必要との考えを示した。「受講を必須とするなど、現状追認ではなく、機能を強化することが必要だ」とした。
都道府県がガバナンスを効かせることが重要であるとし、診療報酬に関しては「重点化などのメリハリを中医協でしっかり議論してほしい」とした。対象の患者については、「国民の考えを反映すべきで、“医師により継続的な管理が必要と判断される患者”などでは限定的であり、入口で医師が絞る必要はない」とした。
「患者との関係は1対1を基本とすべき」とも述べた。
さらに、医療DXを視野に入れた取り組みを要望。「書面のやりとりにとどめず、登録して、保険者が情報を確認できるようにすることで円滑な連携が可能になる」とした。
事務局は「全世代型社会保障構築会議の論点にもあるように、1対1ということは考えて提案はしていない」と述べた。