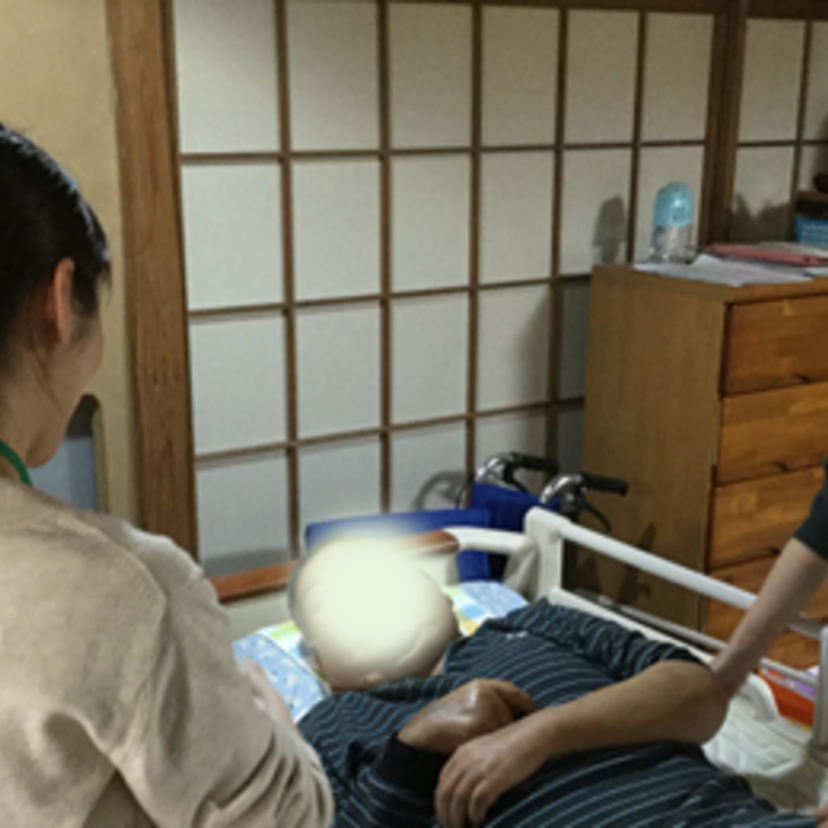手が行き届いていない「医療的ケア児(者)」
薬局の評価の在り方について話を聞いたのは、広島市を中心にすずらん薬局を展開する株式会社ホロン会長の古屋憲次氏。「在宅医療や地域コミュニティー活動など、これまでに長年取り組んできた中から、地域包括ケアを推進する上で薬局が果たすべき役割は多い」と指摘する。
「それらを実践し薬局の社会的存在意義を示すため、喫緊の社会的課題である『医療的ケア児(者)へのサポート体制の確立』、『疾病予防・重症化予防・介護予防・健康寿命延伸における薬局の総合力の活用』、またそれらを継続的に行える『薬局の評価のあり方』などが必要だ」と話す。
古屋氏が最も関心を寄せているのが、「医療的ケア児(者)へのサポート体制の確立」。最近、喫緊の社会的課題として取り上げられることが増えているテーマだ。
すずらん薬局では現在、医療的ケアを必要とする患者を10〜15人程度フォローしている。薬局の経済的・時間的負担の大きさから、一部の薬局に業務が集中しているのが現状。医療の進歩を背景に、年々、対象者は増加しており、長期にわたるフォローで患者家族の負担も大きい。
必要なケアも人工呼吸や胃ろう・たん吸引など、調剤も粉砕や個別の分包など手間のかかるケースが多く、「1件に3~4時間はかかるケースもざら」(古屋氏)という。
患者家族の自宅周辺に受け入れてくれる薬局がなく、主治医、同じ疾患のお子さんを持つ保護者の紹介で同社への相談につながることがほとんど。「地域でサポート体制の構築が急務であると感じている」(古屋氏)。
医療的ケアを必要としている患者が「どこに」「どのような環境でいるか」を可視化した、“サポートマップ”を自治体ごとに作成し、行政、医師会、薬剤師会等が連携することで、支援体制を拡充すべきと指摘する。まだまだ手を差し伸べられてきれていない患者がいるのではないかとの懸念からだ。
多くの薬局が支援に当たる上で障壁となるのは、患者1人につき3〜4時間以上もかかることがあるにもかかわらず、負担に応じた報酬が得られないことを挙げている。
そのため、「医療的ケア児(者)加算」といった報酬項目の新設を要望している。
そのことで、希少な薬剤を取り揃えなければならず、しかも期限切れとなってしまうことも少なくないといった薬局の経営的な負担も、いくらかは軽減することができると考える。
医療的ケア児(者)だけでなく在宅緩和医療など、きめの細かな支援をしようとすればするほど、経営的負担は重くなる。報酬制度とは別に、地域ごとに国や自治体製薬企業等と連携した「在宅拠点薬局」を全国的に構築し医療材料や特殊薬剤などの供給を円滑にし、社会資源の無駄をなくすことも以前からの古屋氏の考えだ。
また、自然災害時やパンデミック等に備えたさまざまな備蓄も「流通備蓄体制の整備」に行政や医薬品卸とともに薬剤師会としても関わっていくことで社会に認められるのではないかと考えているという。
さらに、「医療ケア“児”」に焦点が絞られすぎると、一定の年齢を超えた途端に支援が届きづらくなるとの懸念から、「医療的ケア児(者)」という広い概念での制度設計が不可欠であることにも触れている。無菌製剤の乳幼児加算についても同様という。

胃ろうからの薬剤注入などきめの細かな対応が求められる医療的ケア児(者)<写真はすずらん薬局提供>
居宅療養管理指導に関する厚労省令に「栄養士」追加を
2つ目の「疾病予防・重症化予防・介護予防・健康寿命延伸における薬局の総合力の活用」については、このいずれをとってみても、管理栄養士の持つ職能が果たす役割は大きく、実際に薬局の管理栄養士が活躍する場が増えているという。
例えばすずらん薬局では、早い時期から在宅療養現場に管理栄養士が出向き栄養指導を行ってきた。多くの医師やケアマネージャーなどと連携しながらの活動で、多職種からの信頼も得てきた。実際に在宅の現場や地域で活動できる管理栄養士は現状では少なく、地域包括ケアを推進していく上で薬局の管理栄養士の活用は欠かせない。
また、薬局が行っている健康教室や測定会などの場で、薬剤師とともに測定結果によって個別食事指導などを行っている。腎臓に疾患がある人に向けた特殊食品を使った料理教室やレシピ紹介などでも管理栄養士は活躍している。それが行政と連携した糖尿病予防事業へと発展し、今年度からは広島市の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」につながっている。
全国的にも栄養士がいる薬局は増えており、予防事業に欠かせない存在になっている。薬局の新たな機能・事業としての可能性を秘めている。
一方、医療や介護報酬で評価されるべき在宅での栄養指導は現状、対象になっていない。
一つの障壁は、平成11年3月の厚生労働省令「居宅サービス等の事業の人員配置設備及び運営に関する基準」である。この中で、薬局での居宅療養管理指導の人員としては「薬剤師」としか入っていない。これが一定の縛りになっているのではないかとする見方だ。しかし、この省令は20年以上前の介護保険以前のものであり、薬局における管理栄養士の活躍が想定されていなかった時のものである。社会環境の変化によって、適宜見直しが求められることは言うまでもなく、ここに「管理栄養士」を加える取り組みが必要と古屋氏は指摘する。
市町村が行う日常生活総合事業において、広島市では「短期集中予防支援訪問サービス」などを展開しており、ここでも管理栄養士は活躍しているという。こうした評価を公的保険の枠組みでも広げていくことは、我が国の高齢化進展の状況を考えると、意義は大きいといえる。
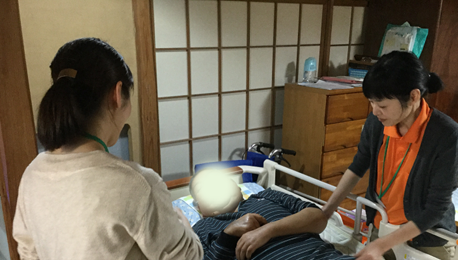
訪問栄養指導も実施している<写真はすずらん薬局提供>
「薬局は組織として対応している」「薬局の評価は機能と実績で」
在宅での緩和医療や医療的ケア児(者)や健康サポート薬局としてさまざまな活動を継続していくには多くの人的・経済的負担が必要である。
特に休日・夜間の体制を継続していくにはチームであり組織での対応が不可欠だ。
すずらん薬局でも、在宅に取り組んだ初期の頃は一部の人への負担が多く、真面目に取り組む人ほど疲弊し「燃え尽き症候群」になるケースもあったという。
組織で対応していくためには、多くの薬剤師がさまざまな経験を積むことが重要で、そのためにも若い世代の薬剤師にいくつかの特徴ある薬局での経験は必要だというのが古屋氏の考えだ。
「かかりつけ薬剤師制度を進めていくことに異論はない。しかし、薬局の評価においては、現行のかかりつけ薬剤師制度では、店舗での勤務年数、薬剤師の就業時間を要件にしているものの、出産・引越・病気・介護などによって管理薬剤師の勤務状況に変化が起きた時に対応がしづらく、労働においてさまざまな問題を抱えている薬剤師にも負担を強いている側面が否定できない。さらには特定の薬局の勤務にこだわることより、多様な薬局で勤務することでキャリアを積めるメリットもあるのではないか」(古屋氏)。
もう1つの視点が、「提供している機能と実績を中心に評価すべきではないか」ということ。
現行の調剤報酬制度では、「処方箋枚数の多い薬局の報酬単価(基本料)の引き下げ」「処方元の医療機関が限定されている集中率が高い場合の引き下げ(同)」などの手法が取り入れられているが、「それらは患者が享受している薬局の価値とどのような関係があるのか」という疑問がある。
以上のような考えから、まずは薬局に求められる機能を定義し、その機能を提供しているか否かによってポイント制などを導入することも一案なのではないかとする。
「在宅医療への参画、緩和ケアへの従事、医療的ケア児(者)へのケアなど、薬局に求められる機能をK P Iとして複数設定し、必ず必要な項目、個別評価項目に分け、ポイント制にして評価する方式にしてはどうか」と提案している。
「地域の状況によって求められる機能は異なる。地域ニーズに応じて、薬局ごとに特徴があってもいいのではないか」(古屋氏)と指摘する。
評価されるべき「対人業務」とは何なのか
国は、薬局に対して、「モノからヒトへ」をキーワードに、医薬品を中心とした対物業務から患者を中心に据えた対人業務へのシフトを迫っている。今後、薬剤を取り揃える「調剤料」への報酬は逓減させていく方針だ。
その中で、評価されるべき「対人業務」とは何なのか。
今、まさに薬局現場からの提案こそが求められている。
古屋氏の提案からは、「医療」だけでなく、障害者や子育て世帯の課題を含めた福祉領域でも、薬局が地域包括ケアで担うべきテーマは数多く存在していることを考えさせられる。

すずらん薬局(広島県)

すずらん薬局を展開する株式会社ホロン会長の古屋憲次氏