医薬品提供に関しては、規制改革推進会議などから「在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていない」などの指摘があり、訪問看護ステーションへの配置薬剤を拡充するなどの提案がされてきた。
厚労省でも「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」を実施し、今年3月には「これまでの議論のまとめ」 を公表していた。
こうした動きを受け、日本薬剤師会でも「アクションリスト」を策定する方針をこれまでも示してきており、夜間・休日での薬剤提供や地域に必要な薬局・薬剤師機能を発揮するための薬局間連携を後押ししたい考え。
これらの取り組みは訪問看護ステーションへの薬剤配置の問題といった限定的な課題への対応だけでなく、少子高齢化の進展に伴い医療需要が増大する一方で、医療の担い手確保が困難になることが想定される中、どのように在宅患者を含め地域の医薬品提供体制を確保するかという喫緊の課題への対応となる。
こうした社会情勢変化に薬剤師、薬局が対応する覚悟表明ともいえる。
アクションリストの骨子では、まずすでに整備が始まっている地域における薬局機能の把握、すなわちリスト化を広く地域での活用を進めるとともに、継続的なメンテナンスを規定する。
加えて、地域の医薬品情報の把握・共有を目指す。これは医薬品提供が不安定になっている中、地域資源の有効活用にもつながることが想定される。
さらに、こうした情報把握をベースとして、地域の医療体制と薬局機能を分析し、課題発掘や対応を協議することになる。
特に地域の一次救急体制に応じた体制の整備などを通して、休日・夜間における医薬品提供体制の構築を強化する。
また在宅医療における医薬品提供体制は薬局支援や薬局間連携の促進などを通して強化する。
他職種との協議・連携では連携の窓口となる受け皿の設置を想定する。
離島・へき地、薬局がない地域にも対応することを見込む。
これら「アクションリスト」はあくまで指標となるものであり、地域の実情に応じた対応の協議や実施が必要となると見込まれる。
地域薬剤師会や都道府県薬剤師会の活動、また地域での多職種間や行政との連携が重要となる。
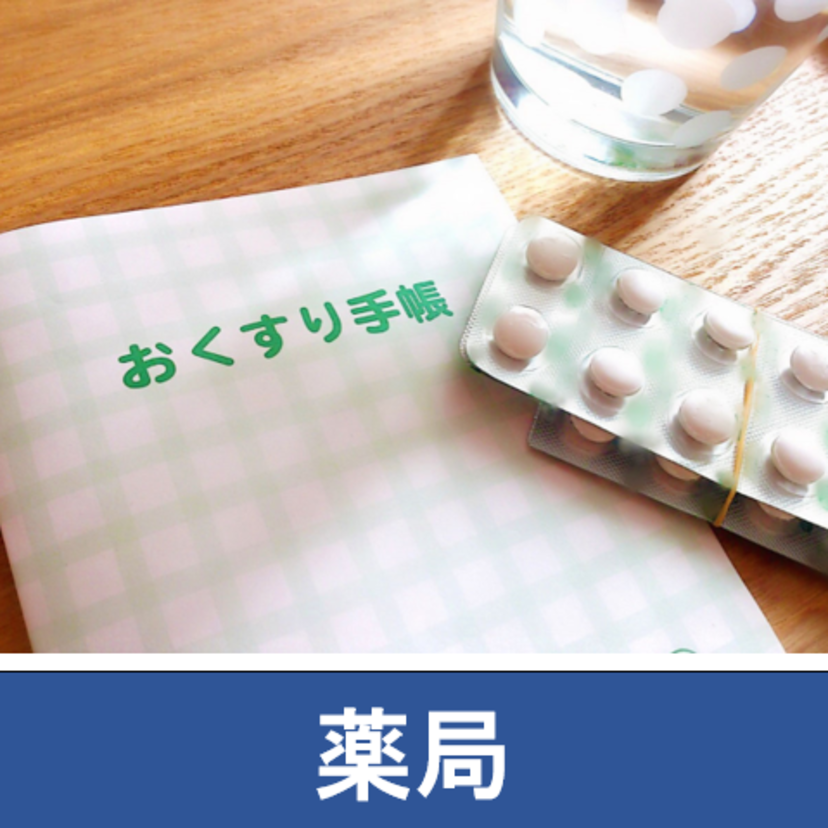
【日本薬剤師会】地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト骨子を策定
【2025.05.13配信】日本薬剤師会はこのほど、「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト」の骨子を策定し、都道府県薬剤師会や地域薬剤師会への説明を開始する。
最新の投稿
【大木ヘルスケアHD】アフターピルの情報「しっかり届ける」/慎重な対応強調
【2026.02.13配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は2月13日にメディア向け説明会を開いた。その中で、アフターピルの情報提供について触れ、慎重な対応を強調。ただ、メーカー資材を中心として「必要な時に必要な情報を届けられるようにすることも仕事」とし、取り組んでいることを説明した。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。後発薬調剤体制や供給体制、地域支援の要件を求める「地域支援・医薬品供給対応体制加算」はこれら要件の旧来の点数の合算から考えると3点の減点ともいえる。
【答申】調剤管理料「2区分」化では「7日以下」では増点の結果
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤管理料(内服薬)では、「長期処方」(28日分以上)以外は10点となる。長期処方は60点。
【2026.02.13配信】厚生労働省は2月13日に中央社会保険医療協議会総会を開き、令和8年度診療報酬改定について答申した。調剤基本料「1」と「3ーハ」で2点増点する。
【日本保険薬局協会】門前薬局“減算”、「到底受け入れられない」/三木田会長
【2026.02.12配信】日本保険薬局協会は2月12日に定例会見を開いた。この中で会長の三木田慎也氏は、次期調剤報酬改定の項目、いわゆる“短冊”について触れ、「門前薬局等立地依存減算」について「到底、受け入れらない」と強調した。「患者さんの動向、患者の志向、いわゆるマーケットインの発想が調剤報酬をつくる側に全く意識されていない結果」と述べた。


















